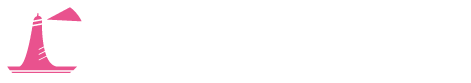「デイサービス」で記事を検索しました。
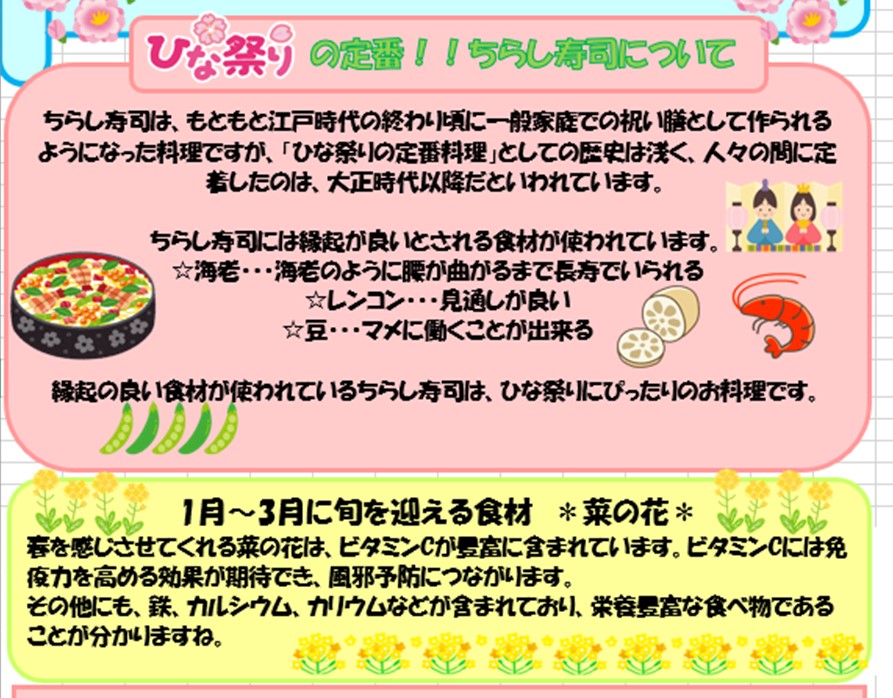
2022.02.28
デイサービス
2022.02.25
デイサービス
2022.02.21
デイサービス
2022.02.02
デイサービス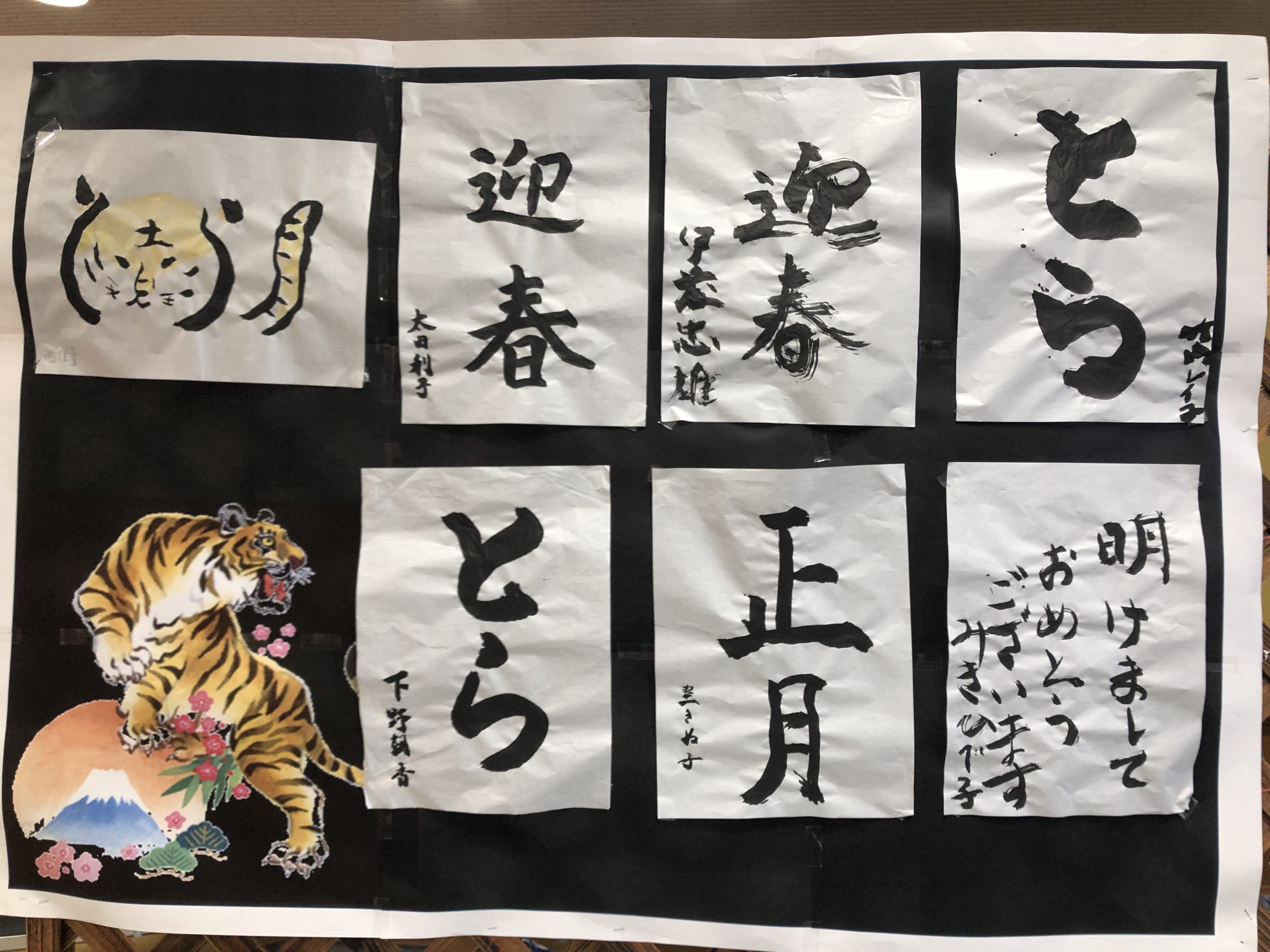
2022.01.11
デイサービス
2022.01.05
デイサービス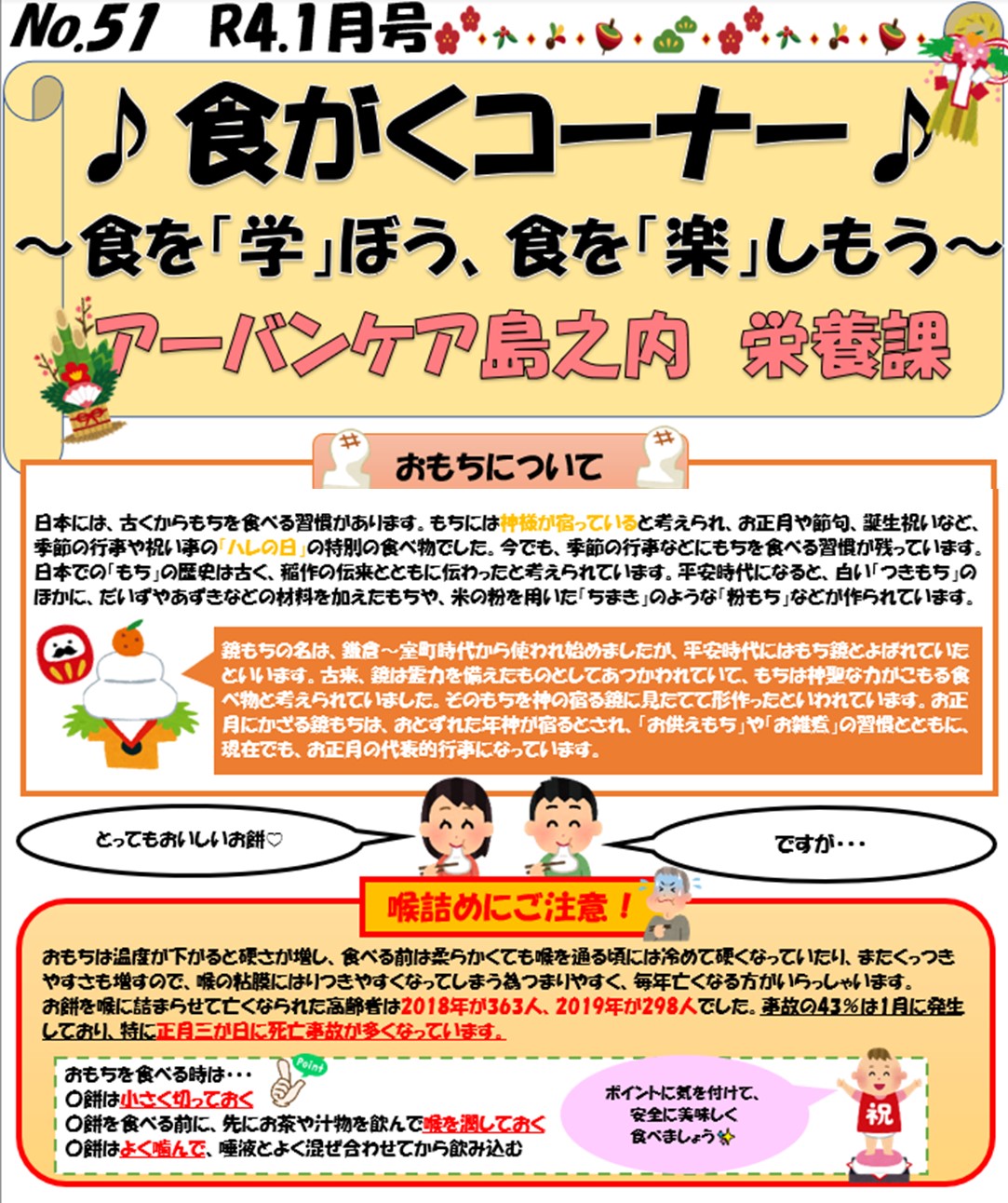
2021.12.17
デイサービス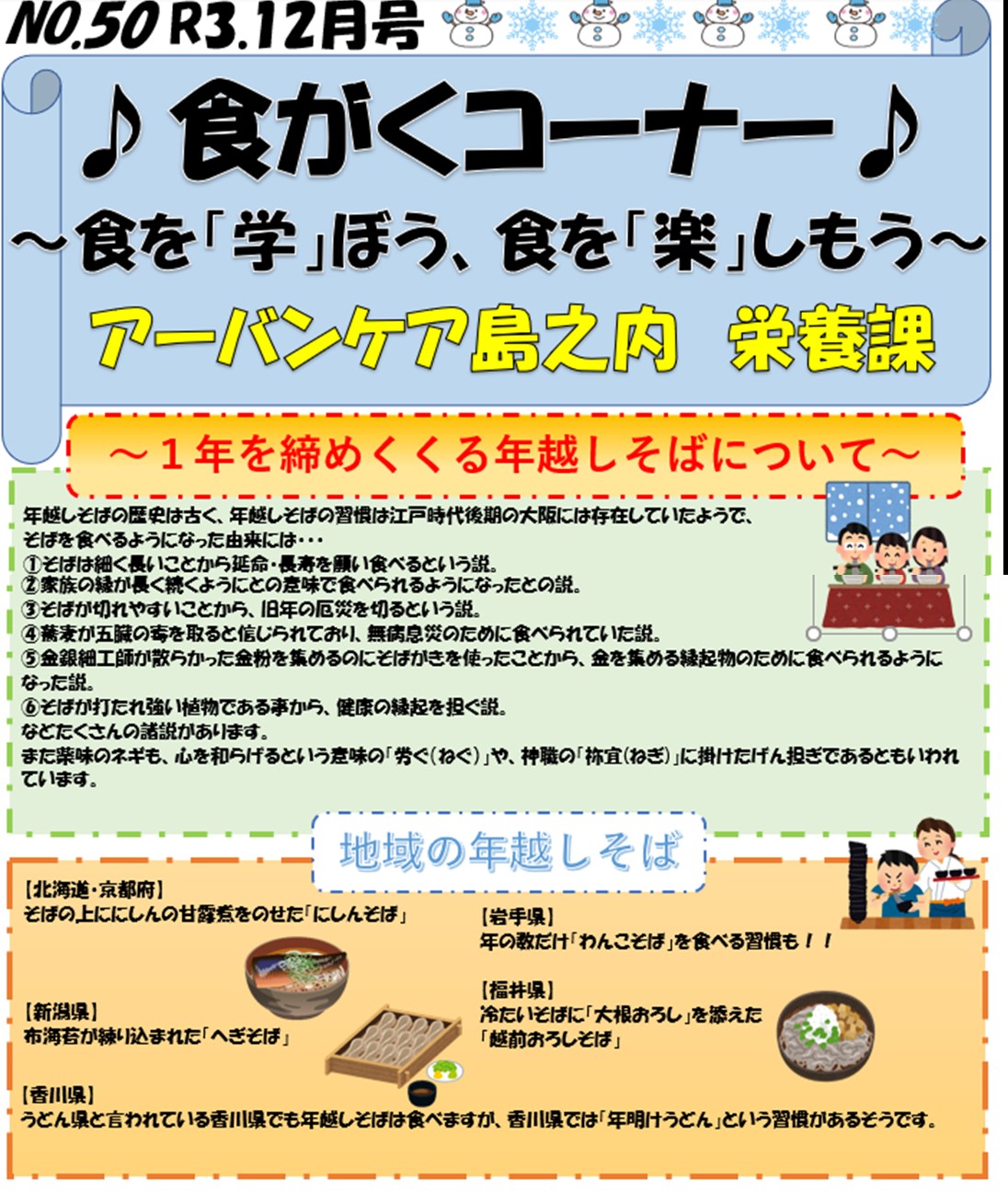
2021.12.08
デイサービス
2021.11.16
デイサービス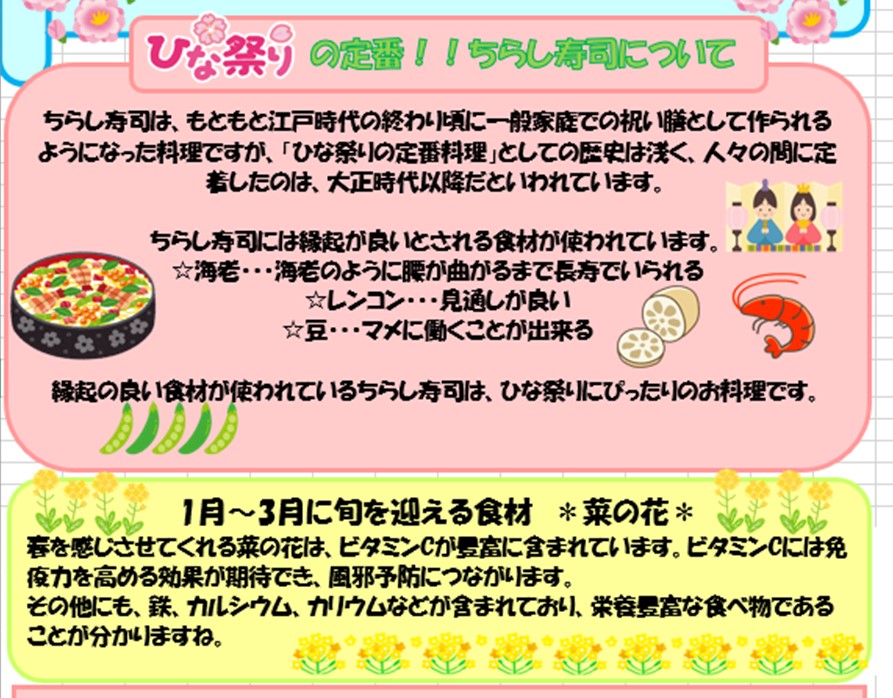
2022.02.28
デイサービス もうすぐ2月も終わり・・「雛祭り」🎎ということで!!
デイサービスのご利用者様が、雛人形を飾ってくださいました~♪ (*^-^*)v
👆ご利用者様が、「ひなあられ」と「ちらし寿司」を ペーパークラフトで見事に!😲
再現してくださいました!! すごいですよね~😊
次回作も考えてくださっています♪ 楽しみです!
こちらは、ご利用者様と共に作成した「お内裏様とお雛様」🎎を
大型貼り絵を壁画としてデイホールに飾っています!
お雛様の前で記念撮影📷✨ 乙女な心のご利用者様です!(^^)!❤
こちらは、2月~3月の季節のお花‥という事で「水仙🌼」のペーパークラフトを
壁画としてデイホールにて飾っています♪
中庭には・・「いちご🍓」の花が咲き・・「チューリップ🌹」の芽が顔を出し始めました😊
春が待ち遠しいですね~♪♪
「早生そら豆」も綺麗な紫色の花が咲きました!
「玉ねぎ」もすくすく成長しています♪ 収穫が楽しみですね~
「エンドウ豆」・・豆ごはんが出来るぐらい収穫できたらいいですねぇ~(*^-^*)
もうすぐ2月も終わり・・「雛祭り」🎎ということで!!
デイサービスのご利用者様が、雛人形を飾ってくださいました~♪ (*^-^*)v
👆ご利用者様が、「ひなあられ」と「ちらし寿司」を ペーパークラフトで見事に!😲
再現してくださいました!! すごいですよね~😊
次回作も考えてくださっています♪ 楽しみです!
こちらは、ご利用者様と共に作成した「お内裏様とお雛様」🎎を
大型貼り絵を壁画としてデイホールに飾っています!
お雛様の前で記念撮影📷✨ 乙女な心のご利用者様です!(^^)!❤
こちらは、2月~3月の季節のお花‥という事で「水仙🌼」のペーパークラフトを
壁画としてデイホールにて飾っています♪
中庭には・・「いちご🍓」の花が咲き・・「チューリップ🌹」の芽が顔を出し始めました😊
春が待ち遠しいですね~♪♪
「早生そら豆」も綺麗な紫色の花が咲きました!
「玉ねぎ」もすくすく成長しています♪ 収穫が楽しみですね~
「エンドウ豆」・・豆ごはんが出来るぐらい収穫できたらいいですねぇ~(*^-^*)

2022.02.21
デイサービス
2022.02.02
デイサービス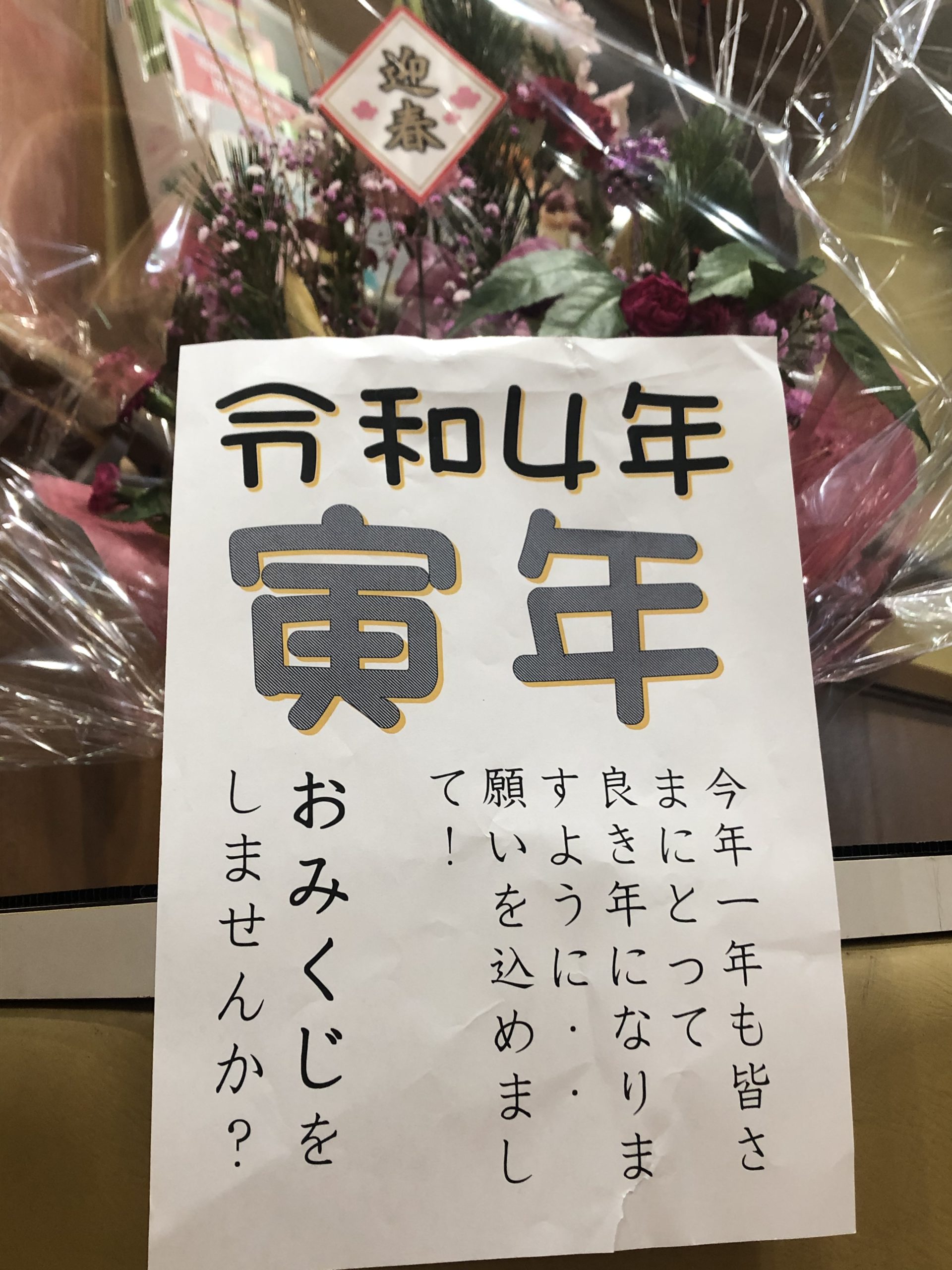
2022.01.11
デイサービス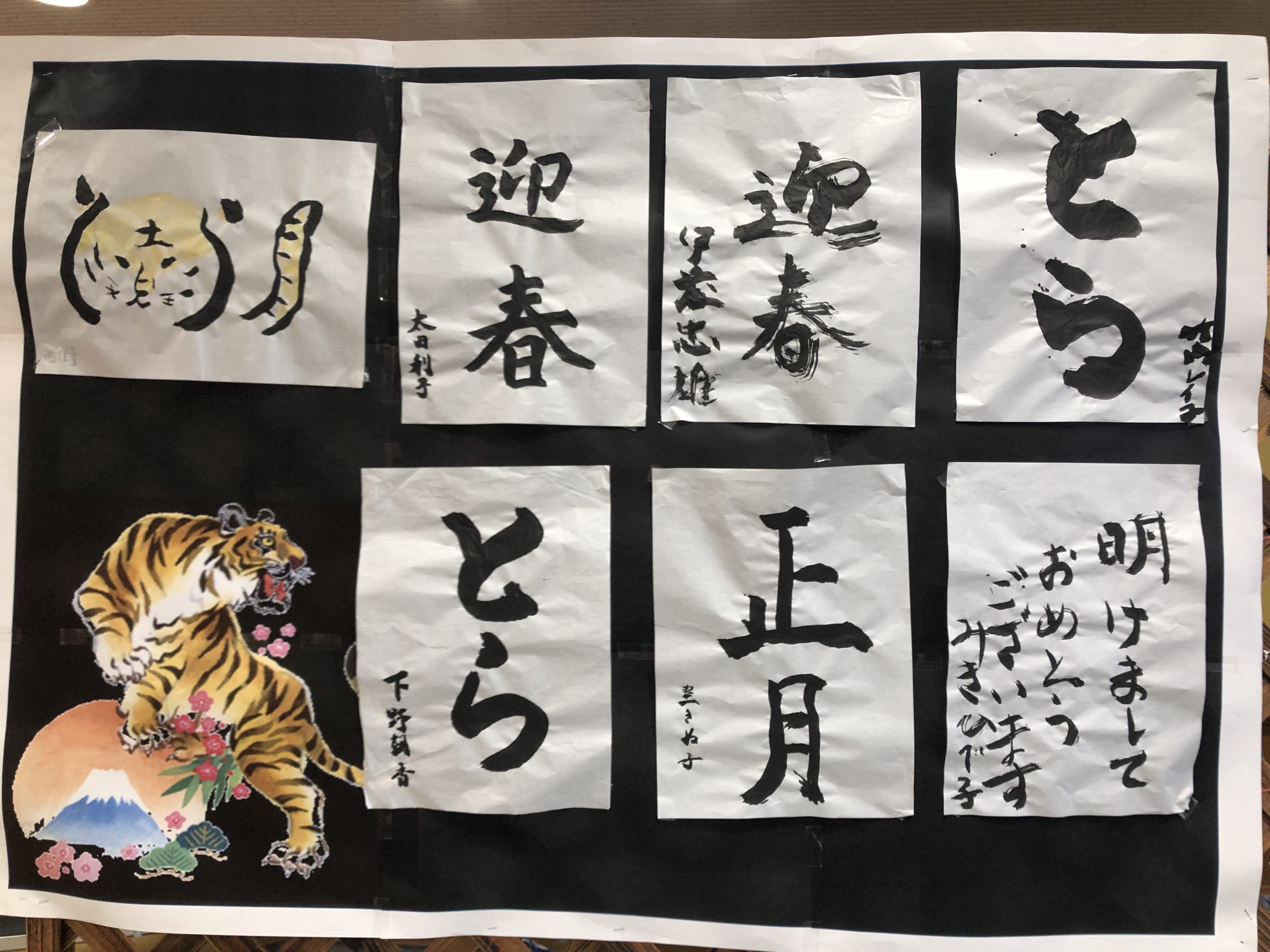
2022.01.11
デイサービス あけまして おめでとうございます!!
2022年 🐯寅年
本年もどうぞよろしくお願いいたします
こちらは、デイサービスのご利用者様が書かれた作品です
素晴らしい「謹賀新年🎍」です!!
今年は、職員手作りの「島之内神社⛩」で デイサービスの皆様をお迎えしました!
早速 初詣?!(笑)
参拝される方もいました・・m(__)m
今年一年も皆様にとって、幸多き一年となりますよう お祈り申し上げます
折り紙や画用紙・・毛糸で作った「今年の干支・寅🐅」と 「寅柄のトラ花✿」です
ご夫婦のツーショット写真📷✨を 撮らせていただきました(⋈◍>◡<◍)。✧♡
本年もお二人仲良く❤ ご健康とご多幸をお祈り申し上げます
昨年または、今年の漢字をそれぞれ ご利用者様に 書いていただきました
「鏡餅🍊」に見立てた貼り絵の作品です!! (*´▽`*)/
お餅のところに、新年の挨拶や今年の抱負を 書いていただきました
こちらも、お正月飾りの大作です!!
「千羽鶴で見事な羽子板✨」が出来上がりました〜
毎年12月31日〜1月3日まで、デイサービスをお休みさせていただいております m(__)m
今年も1月4日から、初デイサービスが始まりました (^^)/
ご利用者様は変わらず、元気に来てくださっています!!
2022年も・・ご利用の皆様に「今日もアーバンケア島之内に来て良かった♪」と思っていただけるよう
職員一同 心を込めて・・より良いサービスを提供していきます☺
今後とも、よろしくお願いいたします
あけまして おめでとうございます!!
2022年 🐯寅年
本年もどうぞよろしくお願いいたします
こちらは、デイサービスのご利用者様が書かれた作品です
素晴らしい「謹賀新年🎍」です!!
今年は、職員手作りの「島之内神社⛩」で デイサービスの皆様をお迎えしました!
早速 初詣?!(笑)
参拝される方もいました・・m(__)m
今年一年も皆様にとって、幸多き一年となりますよう お祈り申し上げます
折り紙や画用紙・・毛糸で作った「今年の干支・寅🐅」と 「寅柄のトラ花✿」です
ご夫婦のツーショット写真📷✨を 撮らせていただきました(⋈◍>◡<◍)。✧♡
本年もお二人仲良く❤ ご健康とご多幸をお祈り申し上げます
昨年または、今年の漢字をそれぞれ ご利用者様に 書いていただきました
「鏡餅🍊」に見立てた貼り絵の作品です!! (*´▽`*)/
お餅のところに、新年の挨拶や今年の抱負を 書いていただきました
こちらも、お正月飾りの大作です!!
「千羽鶴で見事な羽子板✨」が出来上がりました〜
毎年12月31日〜1月3日まで、デイサービスをお休みさせていただいております m(__)m
今年も1月4日から、初デイサービスが始まりました (^^)/
ご利用者様は変わらず、元気に来てくださっています!!
2022年も・・ご利用の皆様に「今日もアーバンケア島之内に来て良かった♪」と思っていただけるよう
職員一同 心を込めて・・より良いサービスを提供していきます☺
今後とも、よろしくお願いいたします
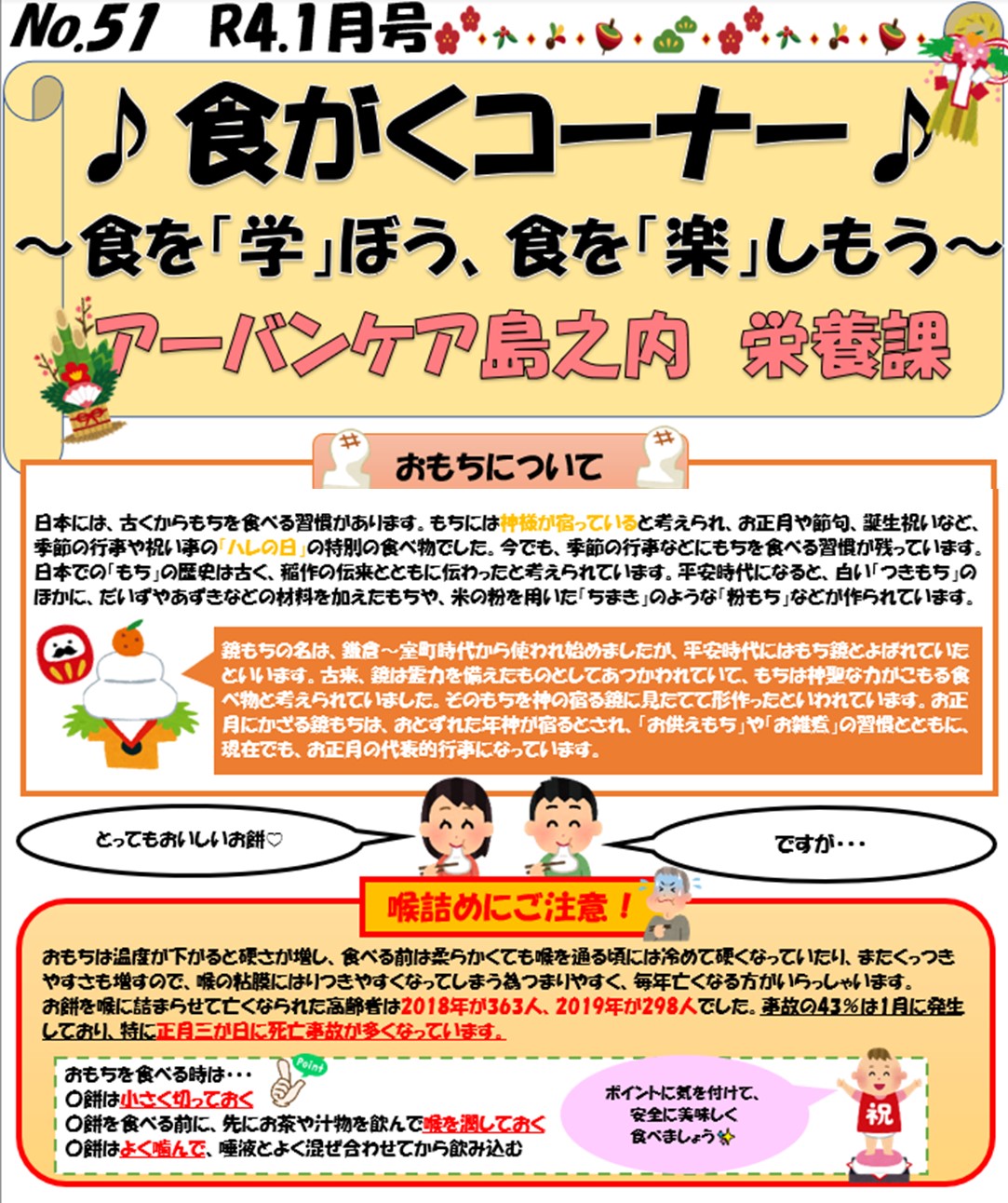
2021.12.17
デイサービス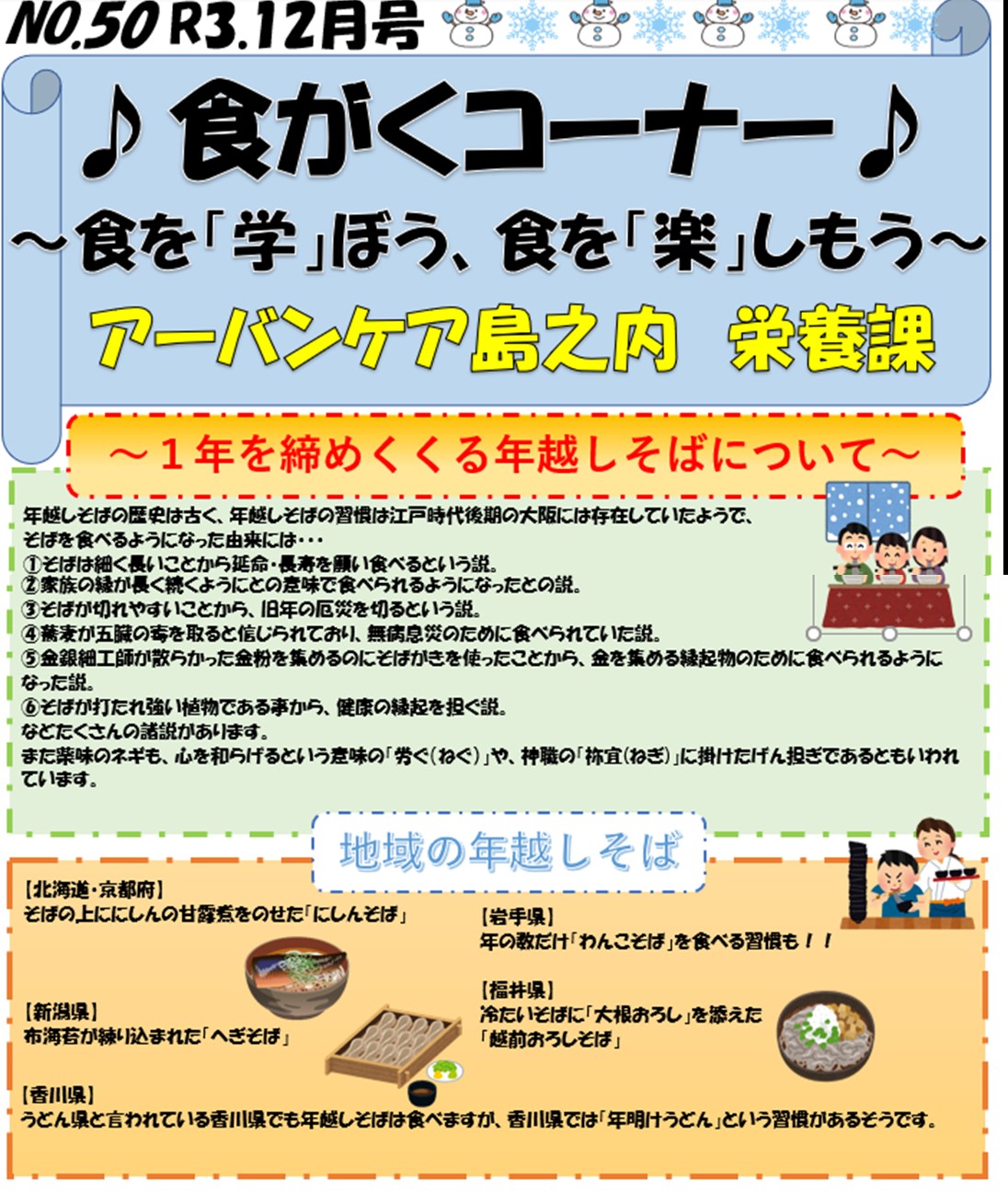
2021.12.08
デイサービス
2021.11.16
デイサービス