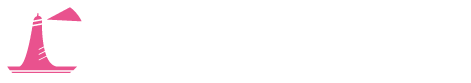「行事食」で記事を検索しました。

2022.05.07
行事食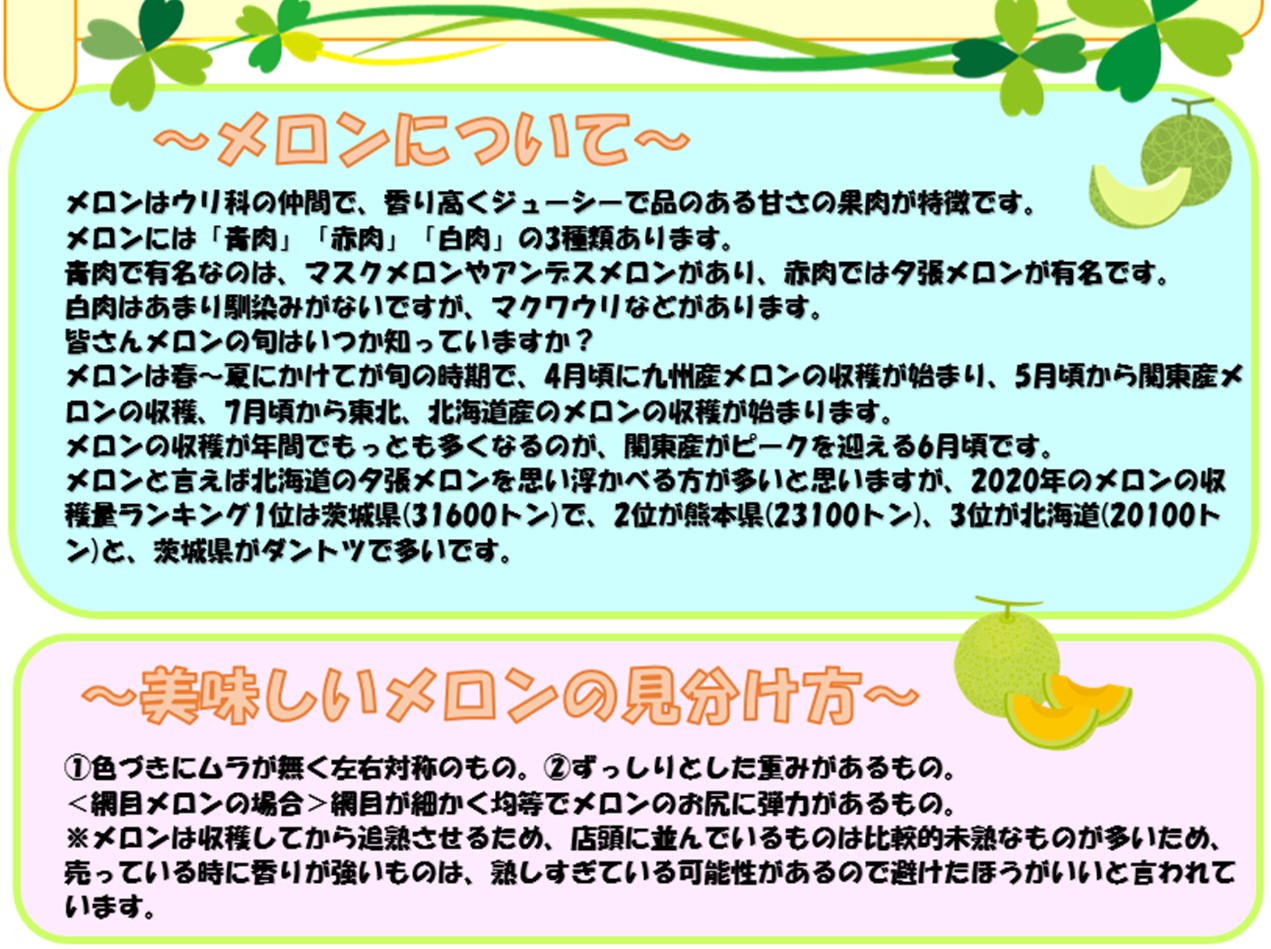
2022.05.02
行事食
2022.03.28
行事食
2022.03.22
行事食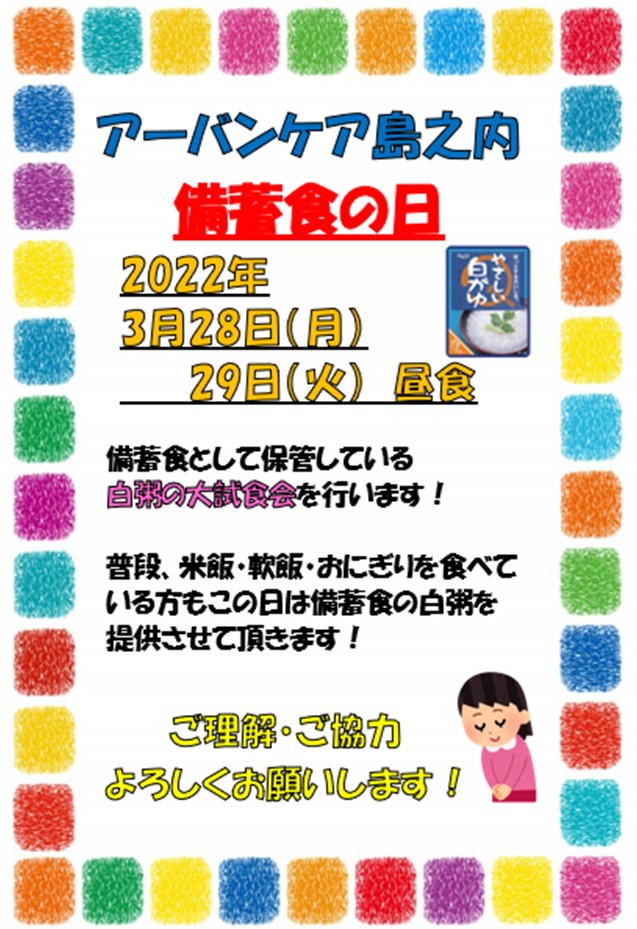
2022.03.09
行事食
2022.03.03
行事食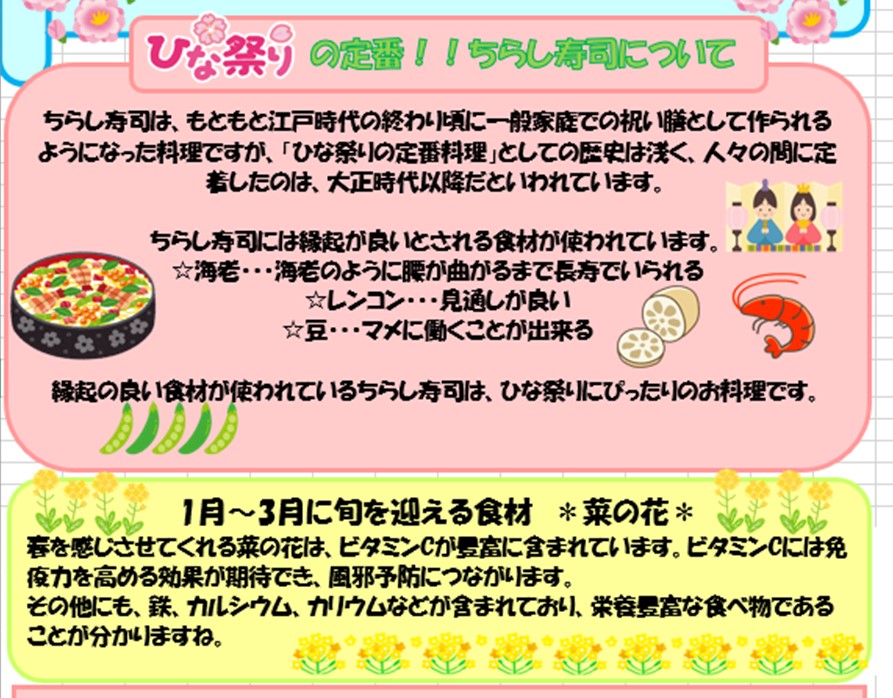
2022.02.28
行事食
2022.02.03
行事食
2022.01.03
行事食
2022.01.01
行事食
2022.05.07
行事食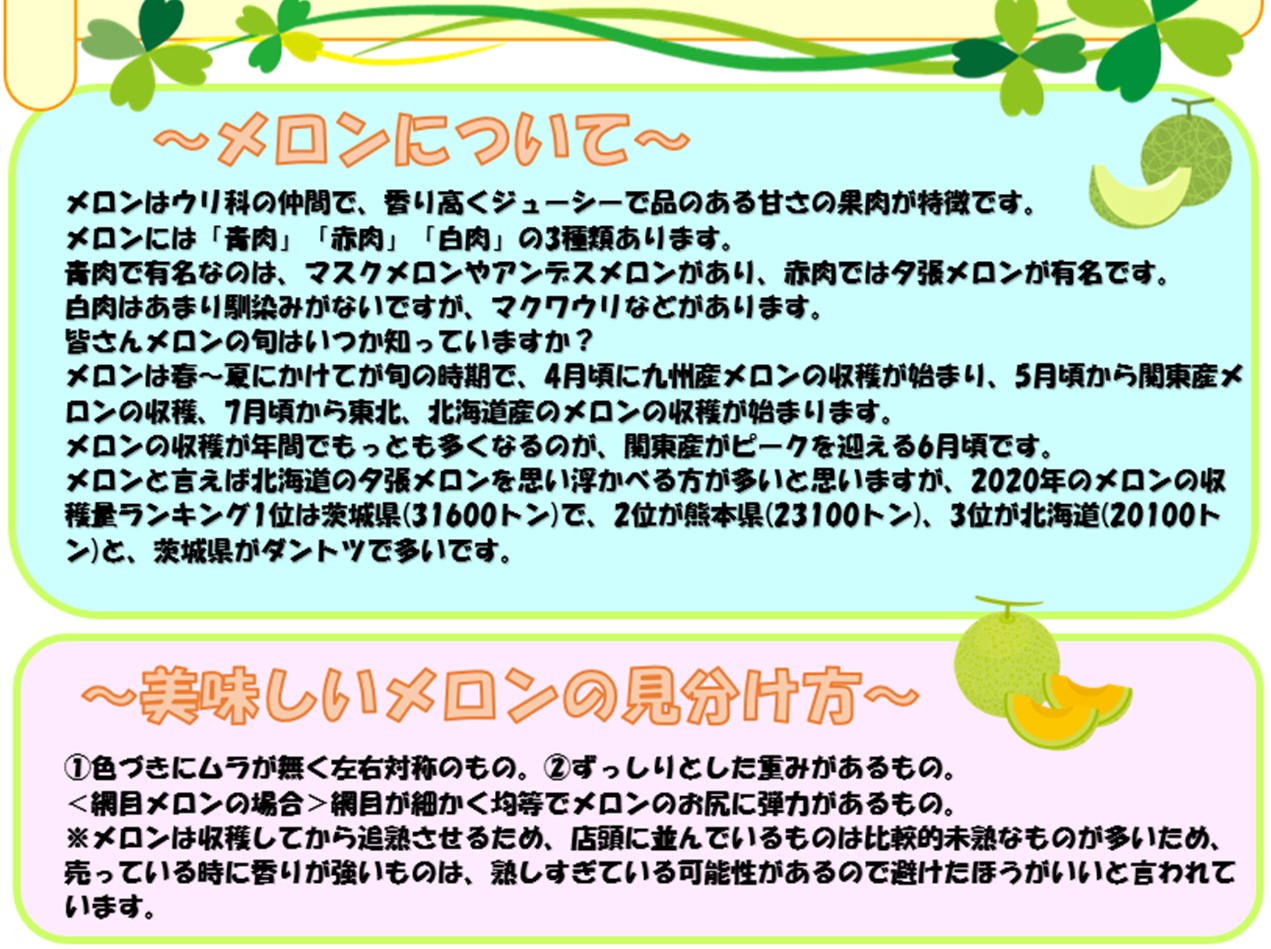 こんにちは!
管理栄養士の長井です!
今日5月2日は八十八夜ということで、先日はお茶についての食がくを載せましたが・・・
今回の食がくはメロンについて🍈
高級なイメージのあるメロン🍈
しかし、価格帯は様々でデパートの高級品からスーパーで買えるお手頃なものまであります。
種類や網目のきれいさによって価格は異なるのです。
メロンはウリ科の仲間で、香り高くジューシーで品のある甘さの果肉が特徴です。
メロンには「青肉」「赤肉」「白肉」の3種類あります。
青肉で有名なのは、マスクメロンやアンデスメロンがあり、赤肉では夕張メロンが有名です。
マクワウリなどが白肉のメロンにあたります。
メロンの旬はいつか知っていますか?
メロンは春~夏にかけてが旬の時期で、4月頃に九州産メロンの収穫が始まり、5月頃から関東産メロンの収穫、7月頃から東北、北海道産のメロンの収穫が始まります。
メロンの収穫が年間でもっとも多くなるのが、関東産がピークを迎える6月頃です。
メロンと言えば北海道の夕張メロンを思い浮かべる方が多いと思いますが、2020年のメロンの収穫量ランキング1位は茨城県(31600トン)で、2位が熊本県(23100トン)、3位が北海道(20100トン)と、茨城県がダントツで多いようです。
おいしいメロンの見分け方は・・・
①色づきにムラが無く左右対称のもの。
②ずっしりとした重みがあるもの。
<網目メロンの場合>網目が細かく均等でメロンのお尻に弾力があるもの。
※メロンは収穫してから追熟させるため、店頭に並んでいるものは比較的未熟なものが多い。売っている時に香りが強いものは、熟しすぎている可能性があるので避けたほうがいいと言われています。
ちなみに、青肉で名前を挙げたアンデスメロンの由来は、アンデス山脈やアンデス地方とは全く関係ないのは有名な話ですね!
病気に強く栽培しやすい「作って安心」「売って安心」「食べて安心」の「安心ですメロン」🍈
しかし、「安心ですメロン」では、長くてセンスのない名前だということで
メロンは芯(種)をとって食べることから 「安心のしん」 を取って「アンデスメロン」🍈
子どもの頃に初めて母に教えてもらった時は「絶対嘘や!お母さんに騙されている!」と疑いましたが、本当なんですね😊
現在は、赤肉のアンデスメロンも開発されており、「赤いアンデス」の賞味期間は青肉に比べ長く『食べ頃』の状態が長く続くのだそうです。そのため、従来品に比べ「贈って安心です」という新たなアピールポイントも加わっているようですね。
今回はメロンについての情報でした!
ゴールデンウィークにちょっと贅沢してみるのもいいかもしれませんね🎶
こんにちは!
管理栄養士の長井です!
今日5月2日は八十八夜ということで、先日はお茶についての食がくを載せましたが・・・
今回の食がくはメロンについて🍈
高級なイメージのあるメロン🍈
しかし、価格帯は様々でデパートの高級品からスーパーで買えるお手頃なものまであります。
種類や網目のきれいさによって価格は異なるのです。
メロンはウリ科の仲間で、香り高くジューシーで品のある甘さの果肉が特徴です。
メロンには「青肉」「赤肉」「白肉」の3種類あります。
青肉で有名なのは、マスクメロンやアンデスメロンがあり、赤肉では夕張メロンが有名です。
マクワウリなどが白肉のメロンにあたります。
メロンの旬はいつか知っていますか?
メロンは春~夏にかけてが旬の時期で、4月頃に九州産メロンの収穫が始まり、5月頃から関東産メロンの収穫、7月頃から東北、北海道産のメロンの収穫が始まります。
メロンの収穫が年間でもっとも多くなるのが、関東産がピークを迎える6月頃です。
メロンと言えば北海道の夕張メロンを思い浮かべる方が多いと思いますが、2020年のメロンの収穫量ランキング1位は茨城県(31600トン)で、2位が熊本県(23100トン)、3位が北海道(20100トン)と、茨城県がダントツで多いようです。
おいしいメロンの見分け方は・・・
①色づきにムラが無く左右対称のもの。
②ずっしりとした重みがあるもの。
<網目メロンの場合>網目が細かく均等でメロンのお尻に弾力があるもの。
※メロンは収穫してから追熟させるため、店頭に並んでいるものは比較的未熟なものが多い。売っている時に香りが強いものは、熟しすぎている可能性があるので避けたほうがいいと言われています。
ちなみに、青肉で名前を挙げたアンデスメロンの由来は、アンデス山脈やアンデス地方とは全く関係ないのは有名な話ですね!
病気に強く栽培しやすい「作って安心」「売って安心」「食べて安心」の「安心ですメロン」🍈
しかし、「安心ですメロン」では、長くてセンスのない名前だということで
メロンは芯(種)をとって食べることから 「安心のしん」 を取って「アンデスメロン」🍈
子どもの頃に初めて母に教えてもらった時は「絶対嘘や!お母さんに騙されている!」と疑いましたが、本当なんですね😊
現在は、赤肉のアンデスメロンも開発されており、「赤いアンデス」の賞味期間は青肉に比べ長く『食べ頃』の状態が長く続くのだそうです。そのため、従来品に比べ「贈って安心です」という新たなアピールポイントも加わっているようですね。
今回はメロンについての情報でした!
ゴールデンウィークにちょっと贅沢してみるのもいいかもしれませんね🎶

2022.03.28
行事食
2022.03.22
行事食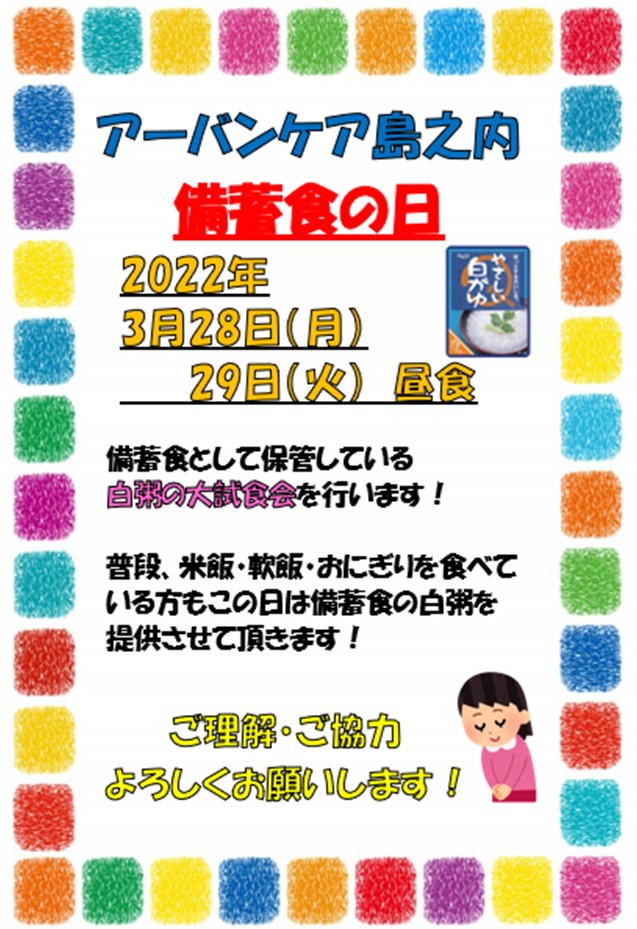
2022.03.09
行事食
2022.03.03
行事食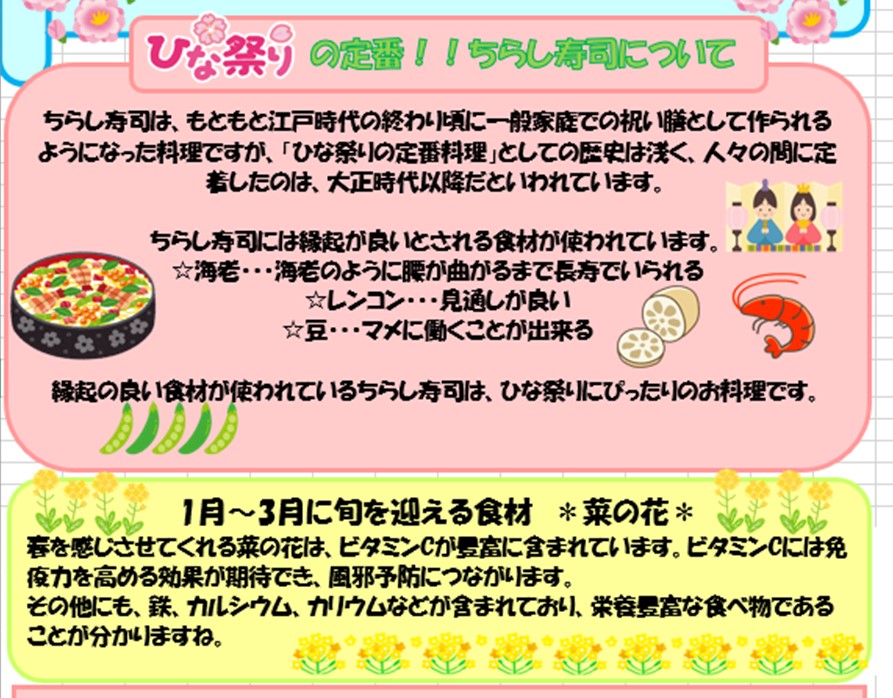
2022.02.28
行事食 こんにちは!管理栄養士の岸本です!
本日は節分ですね!
栄養課では朝から恵方巻づくりに必死でした💦
アーバンケア島之内特製『恵方巻』✨✨
海苔は口の中やのどにくっつきやすく誤嚥のしやすい食べ物です。
そのため、海苔ではなく薄焼き卵で巻きます😋
海苔より破れやすく、巻き終わりもくっつかないので巻くのは海苔より難しいのです…
しかし、そこは腕の見せ所💪
完璧な巻き寿司が完成しました✨
切るのも難しいです💦
(恵方巻は本来、包丁で切ることは「福を途切れさせる」「縁を切る」ことを意味するので切ってはいけないとされていますが、喉詰めを防ぐため、アーバンケア島之内では、切って提供させて頂いています。)
切っている途中でも巻きがくずれる恐れがあるため、うまく切る必要があるのです💧
佐藤管理栄養士が切る作業をしていました!
上手に切れるかなぁ~~??
おいしい恵方巻ができました!!
そして献立の放送では、ご利用者様が今年の恵方と節分の豆知識を放送してくださいました😊
[video width="1920" height="1080" mp4="https://yoshijukai.or.jp/urban-shimanouchi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/献立恵方巻.mp4"][/video]
[video width="1920" height="1080" mp4="https://yoshijukai.or.jp/urban-shimanouchi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/003_Trim_Trim-1.mp4"][/video]
[video width="1920" height="1080" mp4="https://yoshijukai.or.jp/urban-shimanouchi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/003_Trim_Trim-2_Trim_Trim_Trim.mp4"][/video]
[video width="1920" height="1080" mp4="https://yoshijukai.or.jp/urban-shimanouchi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/003_Trim_Trim-3_Trim_Trim.mp4"][/video]
[video width="1920" height="1080" mp4="https://yoshijukai.or.jp/urban-shimanouchi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/003_Trim_Trim-3.mp4"][/video]
今年の恵方は「北北西」!🧭
現在の豆まきは「大豆」を使うことが一般的ですが、かつては米、麦、粟、炭なども使われていたとのこと。
勉強になりました✎
「きれいなぁ~」「美味しいわぁ~」と笑顔で答えて下さいました😊
これで皆様も福を巻き込めたと思います!
今年も素敵な幸せな1年になりますように🍀
こんにちは!管理栄養士の岸本です!
本日は節分ですね!
栄養課では朝から恵方巻づくりに必死でした💦
アーバンケア島之内特製『恵方巻』✨✨
海苔は口の中やのどにくっつきやすく誤嚥のしやすい食べ物です。
そのため、海苔ではなく薄焼き卵で巻きます😋
海苔より破れやすく、巻き終わりもくっつかないので巻くのは海苔より難しいのです…
しかし、そこは腕の見せ所💪
完璧な巻き寿司が完成しました✨
切るのも難しいです💦
(恵方巻は本来、包丁で切ることは「福を途切れさせる」「縁を切る」ことを意味するので切ってはいけないとされていますが、喉詰めを防ぐため、アーバンケア島之内では、切って提供させて頂いています。)
切っている途中でも巻きがくずれる恐れがあるため、うまく切る必要があるのです💧
佐藤管理栄養士が切る作業をしていました!
上手に切れるかなぁ~~??
おいしい恵方巻ができました!!
そして献立の放送では、ご利用者様が今年の恵方と節分の豆知識を放送してくださいました😊
[video width="1920" height="1080" mp4="https://yoshijukai.or.jp/urban-shimanouchi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/献立恵方巻.mp4"][/video]
[video width="1920" height="1080" mp4="https://yoshijukai.or.jp/urban-shimanouchi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/003_Trim_Trim-1.mp4"][/video]
[video width="1920" height="1080" mp4="https://yoshijukai.or.jp/urban-shimanouchi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/003_Trim_Trim-2_Trim_Trim_Trim.mp4"][/video]
[video width="1920" height="1080" mp4="https://yoshijukai.or.jp/urban-shimanouchi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/003_Trim_Trim-3_Trim_Trim.mp4"][/video]
[video width="1920" height="1080" mp4="https://yoshijukai.or.jp/urban-shimanouchi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/003_Trim_Trim-3.mp4"][/video]
今年の恵方は「北北西」!🧭
現在の豆まきは「大豆」を使うことが一般的ですが、かつては米、麦、粟、炭なども使われていたとのこと。
勉強になりました✎
「きれいなぁ~」「美味しいわぁ~」と笑顔で答えて下さいました😊
これで皆様も福を巻き込めたと思います!
今年も素敵な幸せな1年になりますように🍀

2022.01.03
行事食
2022.01.01
行事食