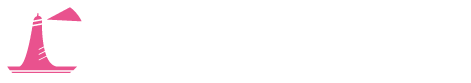「食品」で記事を検索しました。
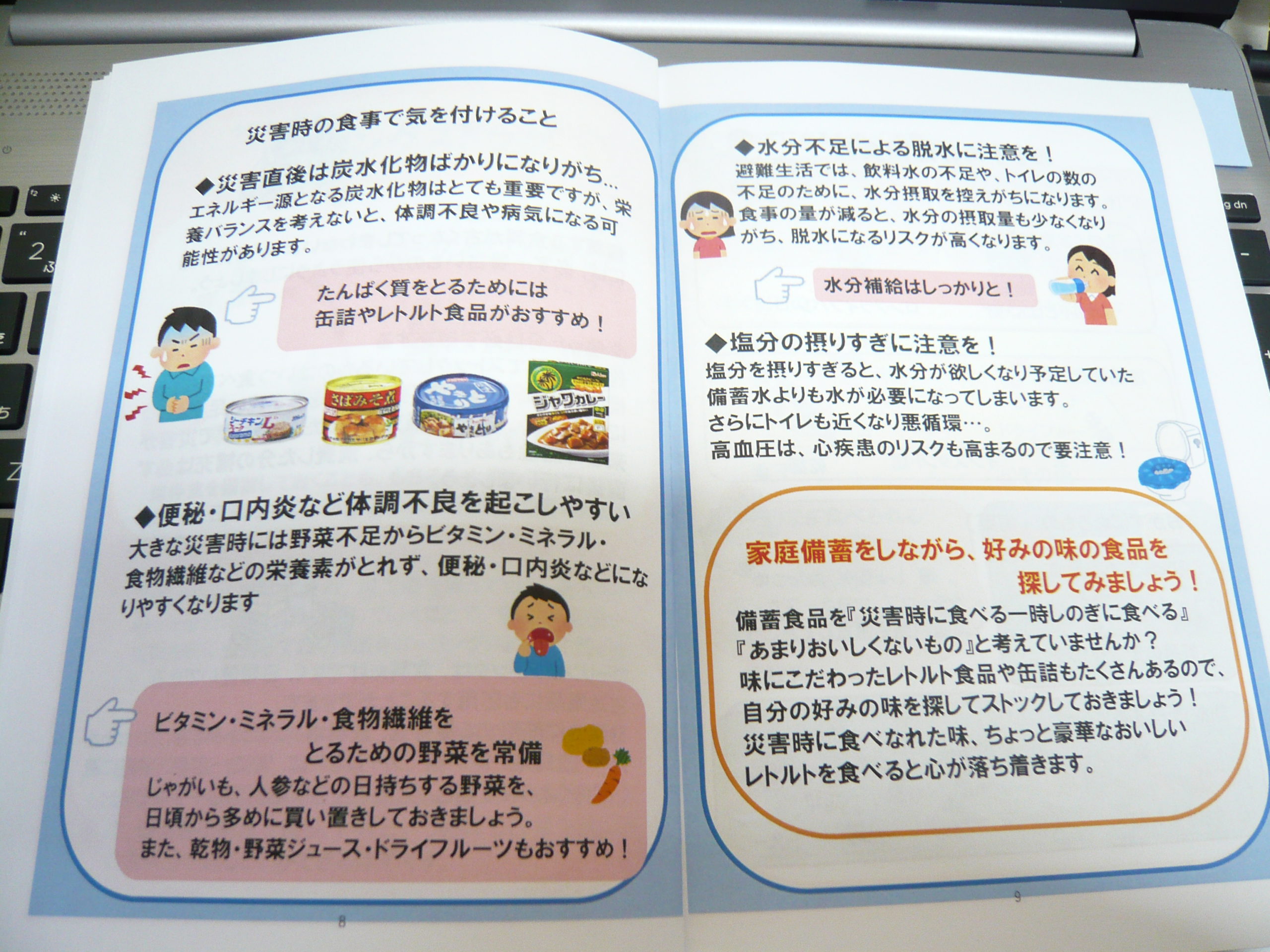
2022.09.03
食品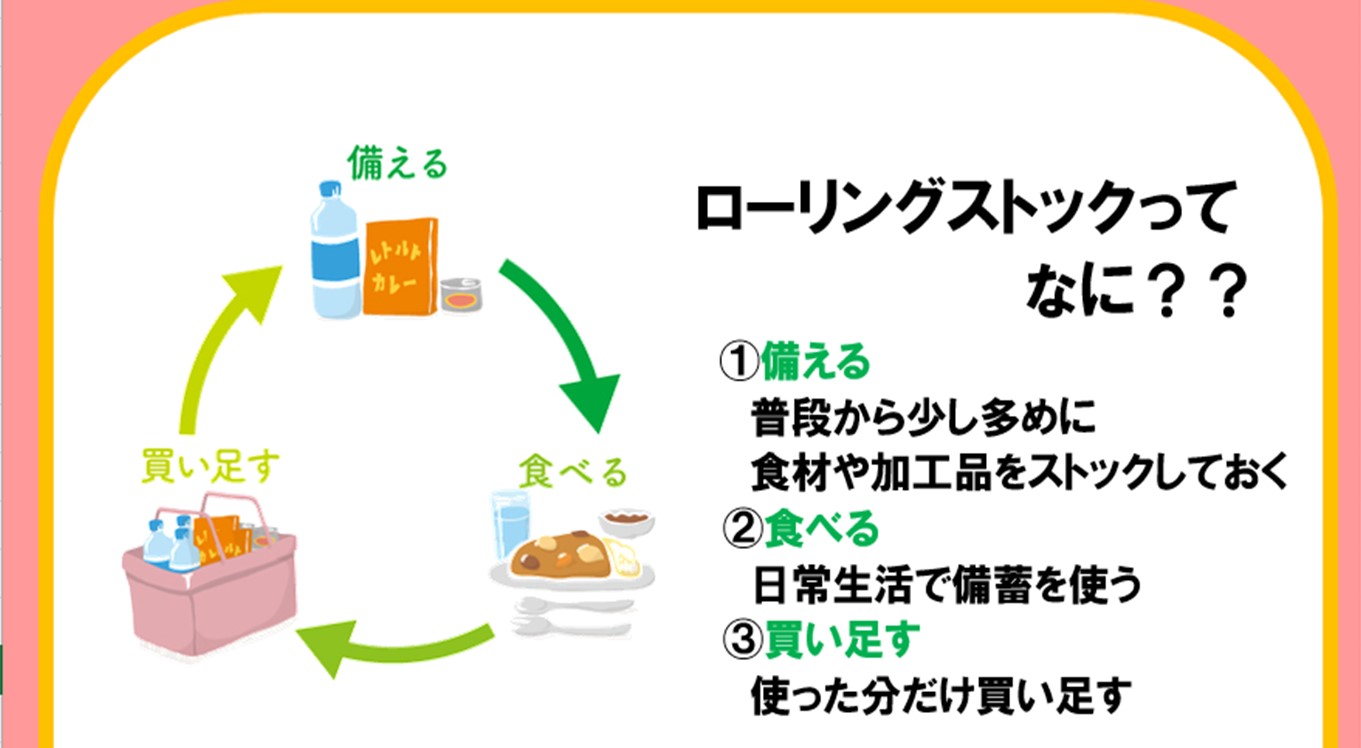
2022.09.02
食品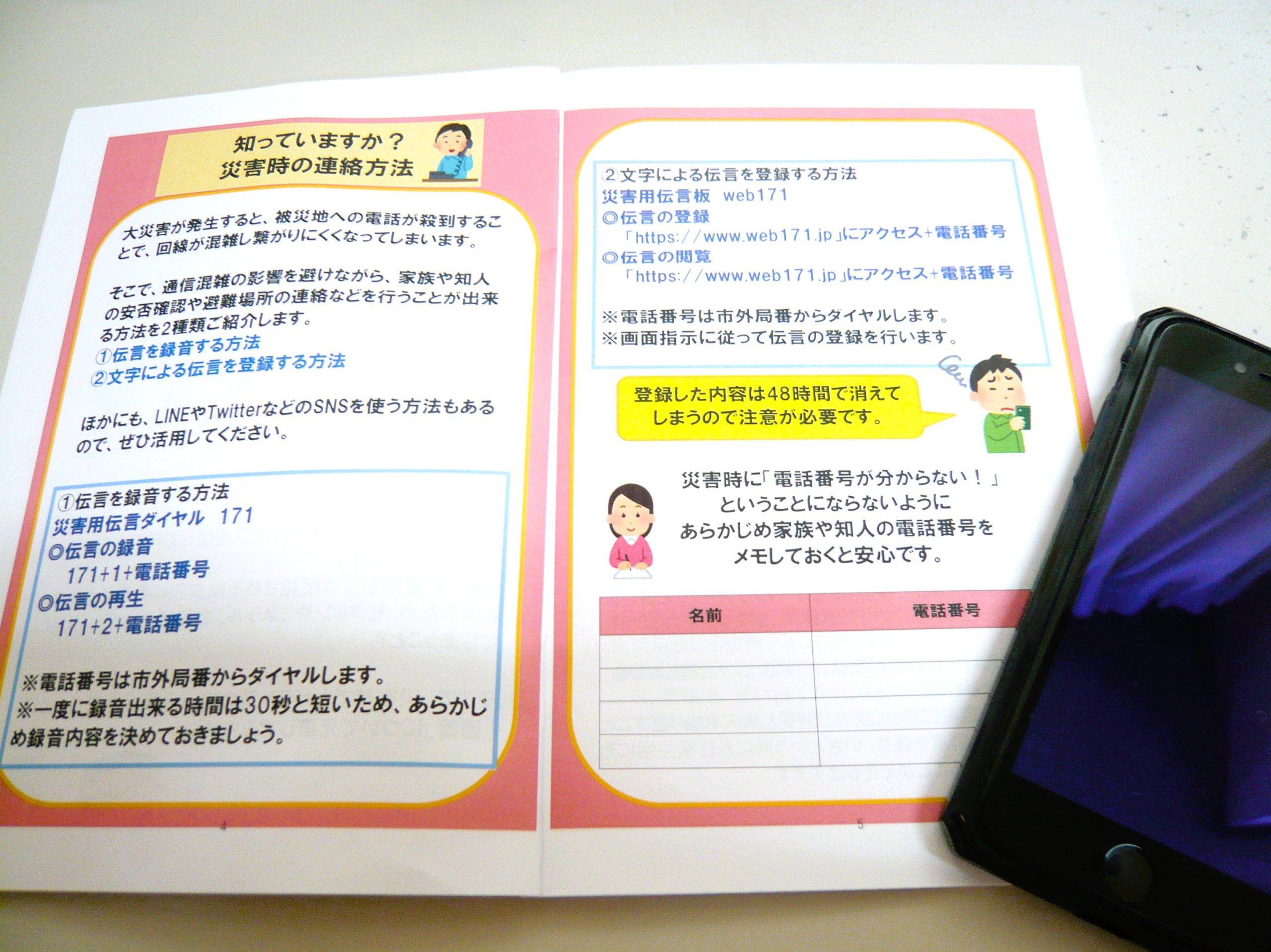
2022.08.31
食品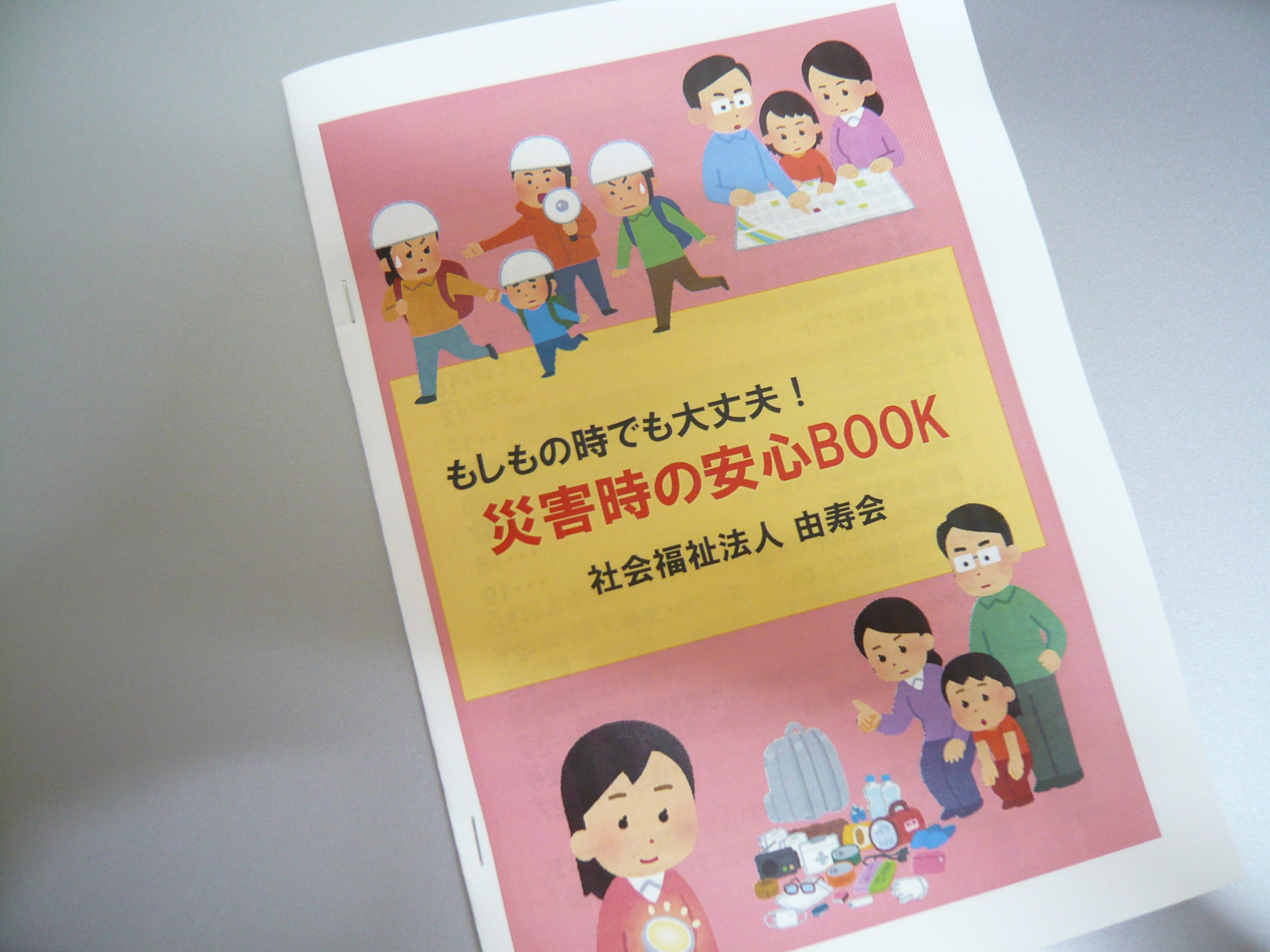
2022.08.28
食品
2022.08.11
食品
2022.08.07
食品
2022.07.23
食品
2022.07.07
食品
2022.07.01
食品
2022.06.19
食品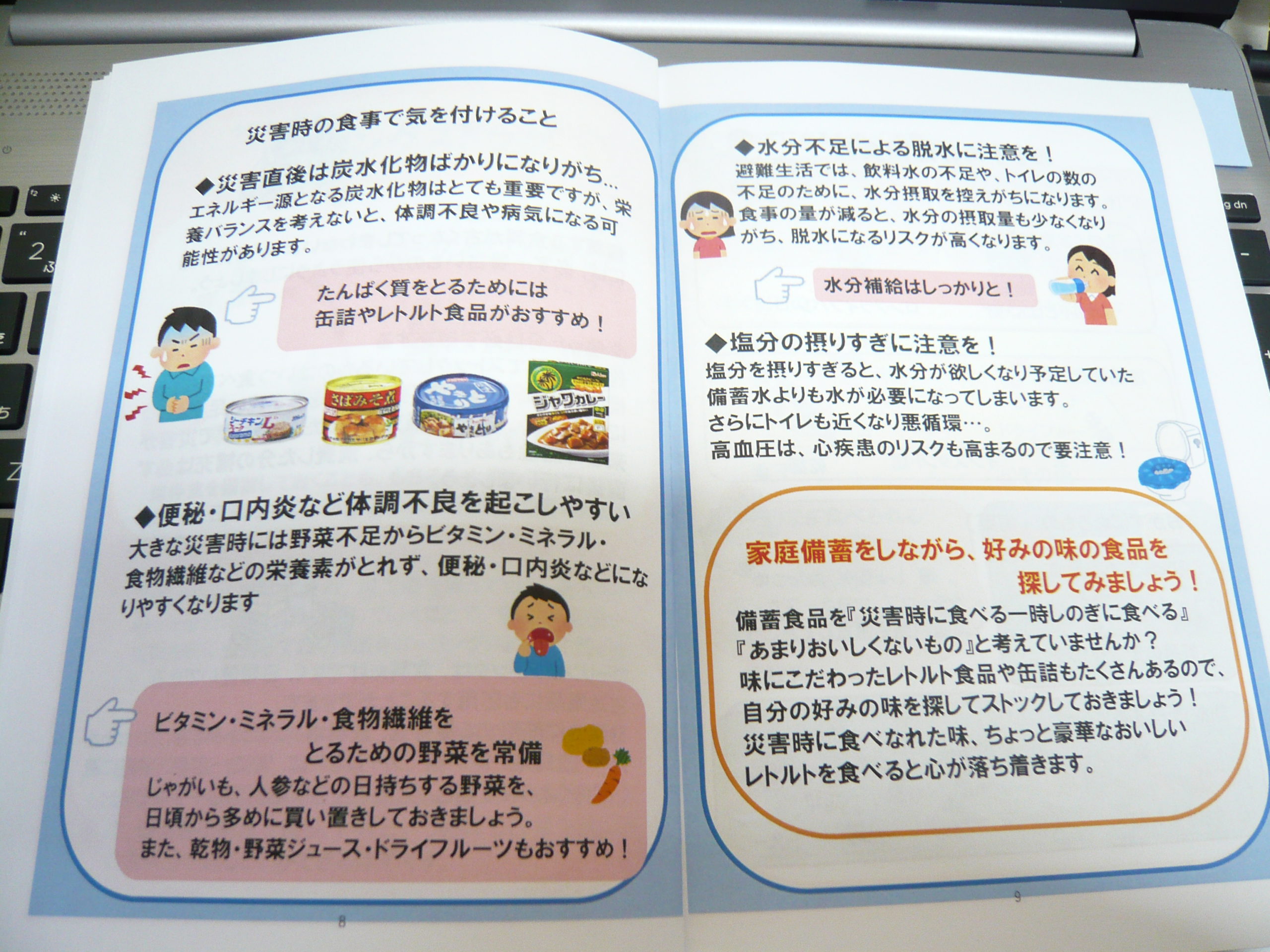
2022.09.03
食品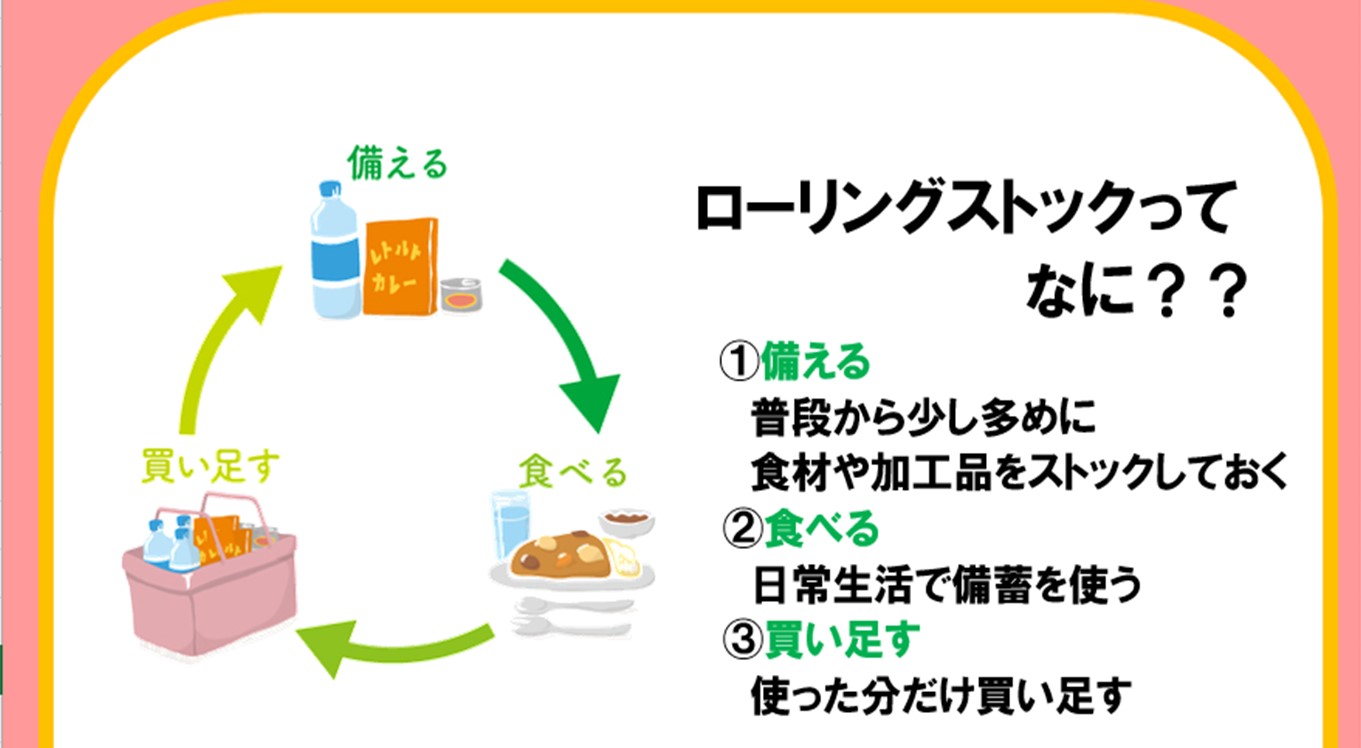
2022.09.02
食品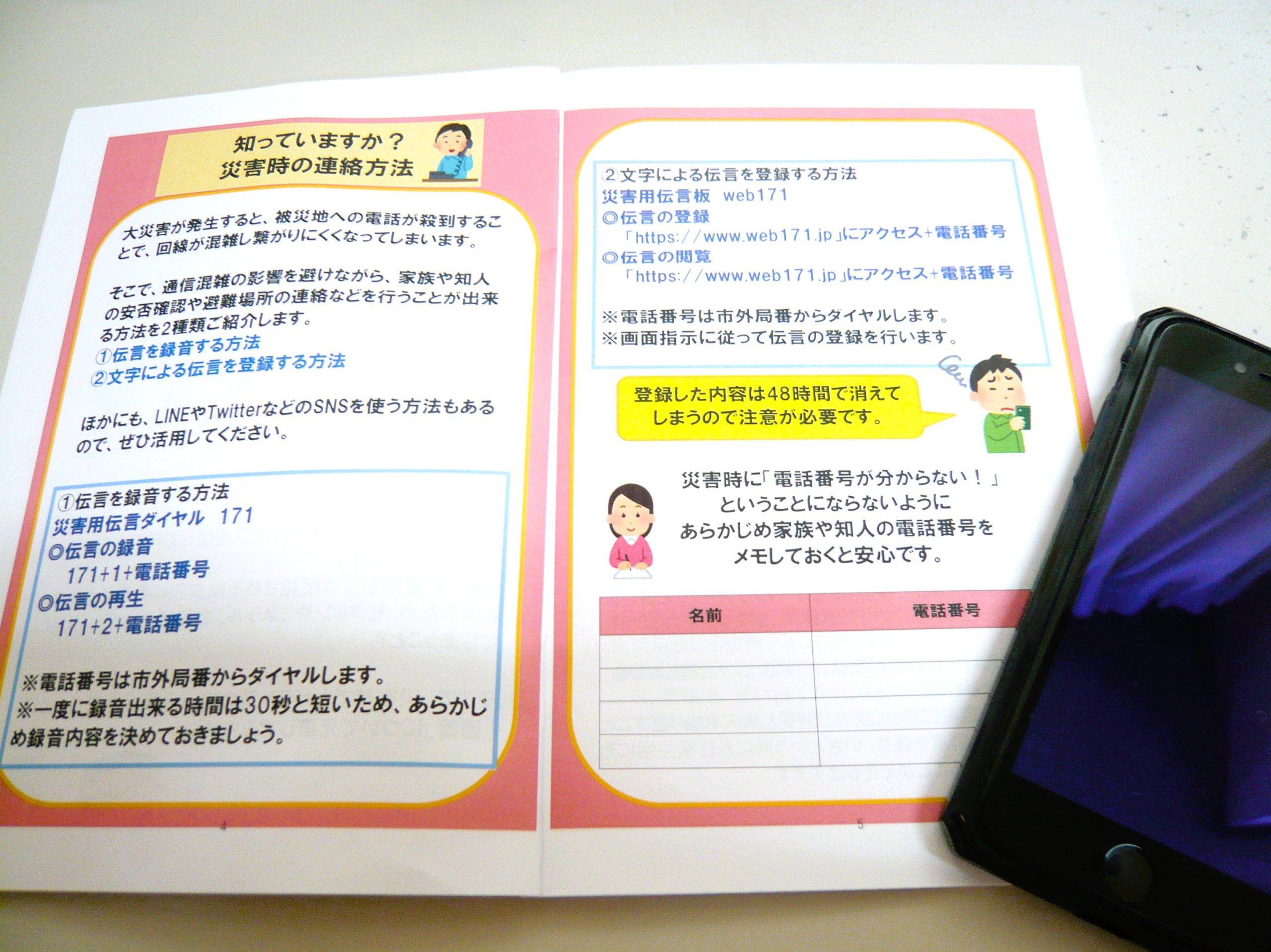
2022.08.31
食品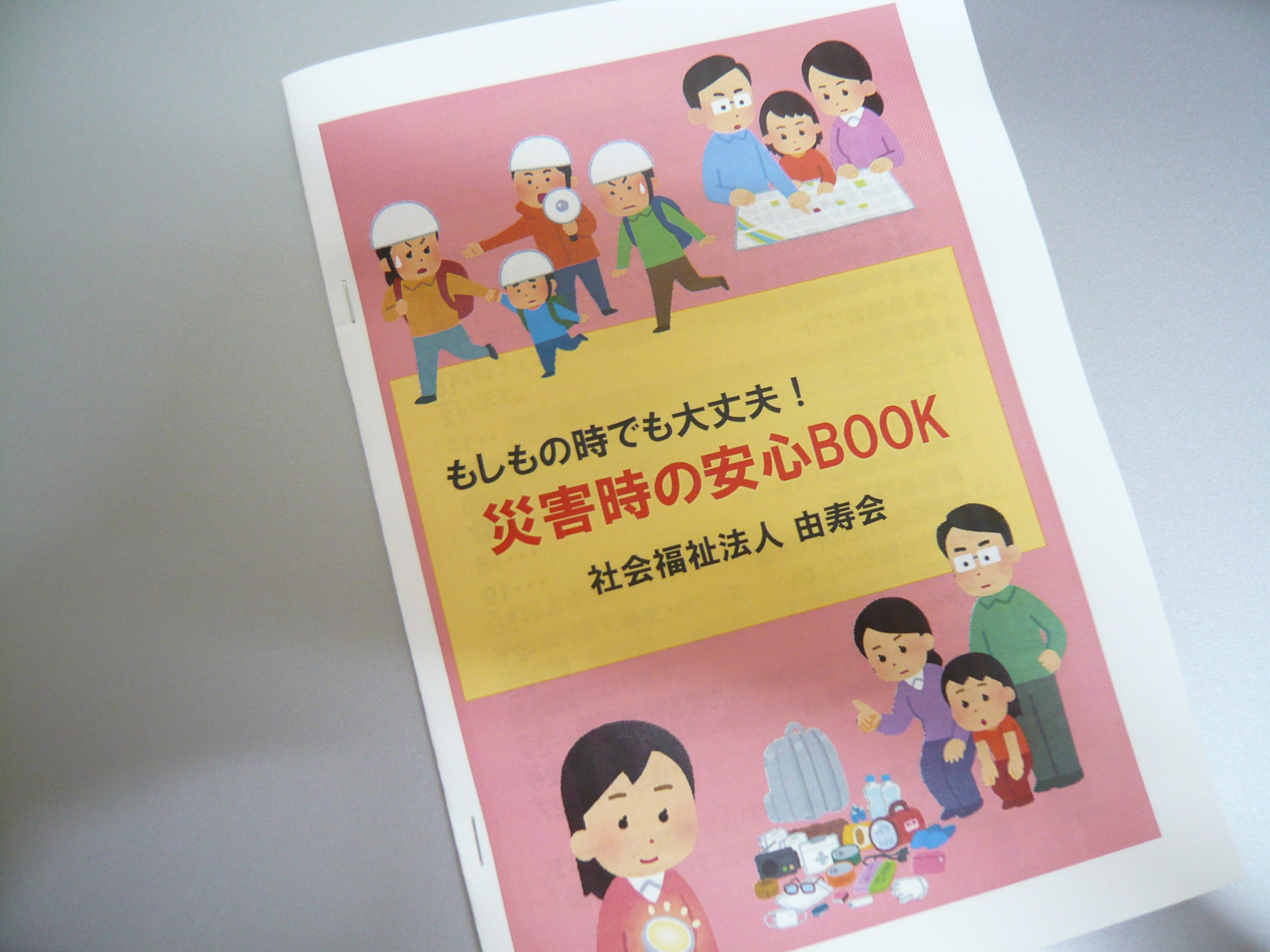
2022.08.28
食品
2022.08.11
食品 こんにちは!
管理栄養士の長井です!
今月の食がくは、「バナナ」についてです!
今日8月7日はなんと「バナナの日」なんです🍌
理由は「バ(8)ナナ(7)」と読む語呂合わせから。果物で一番の輸入量を誇り、健康にも良いバナナを食べて暑い夏を元気に乗り切ってもらいたいとの思いから制定されたそうです🍌
バナナは南国の食べ物で、バナナを生産できる場所は熱帯から亜熱帯地域に限られており、その地域を『バナナベルト』と呼びます。
この地域では季節に影響されることなくバナナを収穫、栽培することができます。
そのため、年中美味しいバナナが収穫され、日本国内でも旬を気にせず安定した味わいを楽しむことができます。
国産の島バナナは7~9月が旬の時期になります(*^-^*)
国産のバナナはとても高く1本800円以上する物が多く、1200円以上する物もあるようです!
バナナの栄養は??
エネルギーは1本(120g)約110kcal
食物繊維:便秘の予防・解消
ビタミン類:エネルギー代謝促進
カリウム:血圧調節
マグネシウム:骨代謝促進、血圧調節
トリプトファン:精神状態の安静、睡眠の促進
といった効果が期待できます。
アーバンケア島之内では週に2~3回程度朝食にバナナを提供しています。
(バナナの準備中の様子です。バナナも消毒して提供します。)
バナナは人気で楽しみにされている方もいらっしゃいます🍌
おいしいバナナの選び方は??
① すぐ食べる場合は…皮表面に黒い斑点が出ていれば完熟!
② 数日かけて食べる場合は…斑点が出る直前!目安は軸が薄い緑色~黄色のもの!
③ より長持ちさせたい場合は…付け根と先端が濃い緑色のものは日持ちよし!
ちなみに、早く熟させる方法は、りんご🍎と一緒に紙袋などにいれておくと早く熟しますよ。
バナナはエチレンという植物ホルモンに反応し熟成します。
りんごはそのエチレンを多く放出するため、より早くバナナが熟すというわけです。
熟したバナナが食べたいけれど、青いバナナしか売っていない😢という時は、ぜひりんごを活用してくださいね😊
先日テレビで、日本で初めてバナナを食べたのは「織田信長」だという話が紹介されていました。
イエズス会の宣教師ルイス・フロイスが織田信長に初めて謁見した際、バナナを献上したと言われているそうです。召し上がったかどうかの記録はないようですが。
諸説あるようで、本当かどうかは定かではありません。信じるか信じないかはあなた次第です👉
ただ、それにあやかって岐阜県では国産バナナ「信長バナナ」が栽培されているようです🍌
これは本当です🍌
とっても高い「信長バナナ」ですが、最高に美味しいそうです。食べてみたいなぁ・・・🤤
「信長バナナ」はなかなか手に入りませんが、バナナを食べて暑さを乗り切りましょう!!
暦の上では今日から立秋ですが…秋はまだまだ遠そうです🌞
熱中症と夏バテ、豪雨雷雨にご注意ください。
こんにちは!
管理栄養士の長井です!
今月の食がくは、「バナナ」についてです!
今日8月7日はなんと「バナナの日」なんです🍌
理由は「バ(8)ナナ(7)」と読む語呂合わせから。果物で一番の輸入量を誇り、健康にも良いバナナを食べて暑い夏を元気に乗り切ってもらいたいとの思いから制定されたそうです🍌
バナナは南国の食べ物で、バナナを生産できる場所は熱帯から亜熱帯地域に限られており、その地域を『バナナベルト』と呼びます。
この地域では季節に影響されることなくバナナを収穫、栽培することができます。
そのため、年中美味しいバナナが収穫され、日本国内でも旬を気にせず安定した味わいを楽しむことができます。
国産の島バナナは7~9月が旬の時期になります(*^-^*)
国産のバナナはとても高く1本800円以上する物が多く、1200円以上する物もあるようです!
バナナの栄養は??
エネルギーは1本(120g)約110kcal
食物繊維:便秘の予防・解消
ビタミン類:エネルギー代謝促進
カリウム:血圧調節
マグネシウム:骨代謝促進、血圧調節
トリプトファン:精神状態の安静、睡眠の促進
といった効果が期待できます。
アーバンケア島之内では週に2~3回程度朝食にバナナを提供しています。
(バナナの準備中の様子です。バナナも消毒して提供します。)
バナナは人気で楽しみにされている方もいらっしゃいます🍌
おいしいバナナの選び方は??
① すぐ食べる場合は…皮表面に黒い斑点が出ていれば完熟!
② 数日かけて食べる場合は…斑点が出る直前!目安は軸が薄い緑色~黄色のもの!
③ より長持ちさせたい場合は…付け根と先端が濃い緑色のものは日持ちよし!
ちなみに、早く熟させる方法は、りんご🍎と一緒に紙袋などにいれておくと早く熟しますよ。
バナナはエチレンという植物ホルモンに反応し熟成します。
りんごはそのエチレンを多く放出するため、より早くバナナが熟すというわけです。
熟したバナナが食べたいけれど、青いバナナしか売っていない😢という時は、ぜひりんごを活用してくださいね😊
先日テレビで、日本で初めてバナナを食べたのは「織田信長」だという話が紹介されていました。
イエズス会の宣教師ルイス・フロイスが織田信長に初めて謁見した際、バナナを献上したと言われているそうです。召し上がったかどうかの記録はないようですが。
諸説あるようで、本当かどうかは定かではありません。信じるか信じないかはあなた次第です👉
ただ、それにあやかって岐阜県では国産バナナ「信長バナナ」が栽培されているようです🍌
これは本当です🍌
とっても高い「信長バナナ」ですが、最高に美味しいそうです。食べてみたいなぁ・・・🤤
「信長バナナ」はなかなか手に入りませんが、バナナを食べて暑さを乗り切りましょう!!
暦の上では今日から立秋ですが…秋はまだまだ遠そうです🌞
熱中症と夏バテ、豪雨雷雨にご注意ください。

2022.07.23
食品
2022.07.07
食品
2022.07.01
食品
2022.06.19
食品