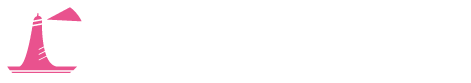「スタッフ日記」で記事を検索しました。

2022.03.27
スタッフ日記
2022.03.19
スタッフ日記
2022.03.19
スタッフ日記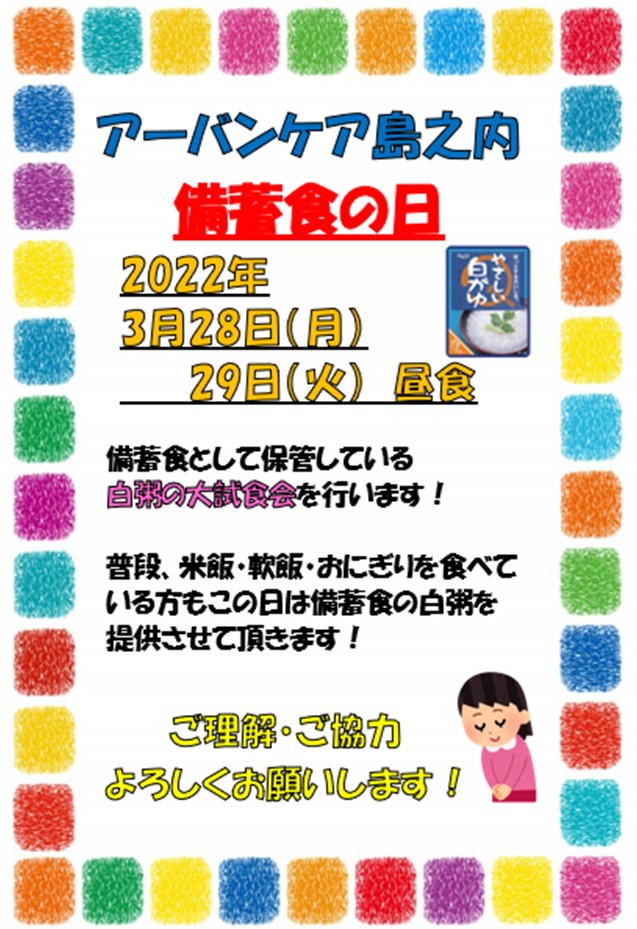
2022.03.09
スタッフ日記
2022.03.03
スタッフ日記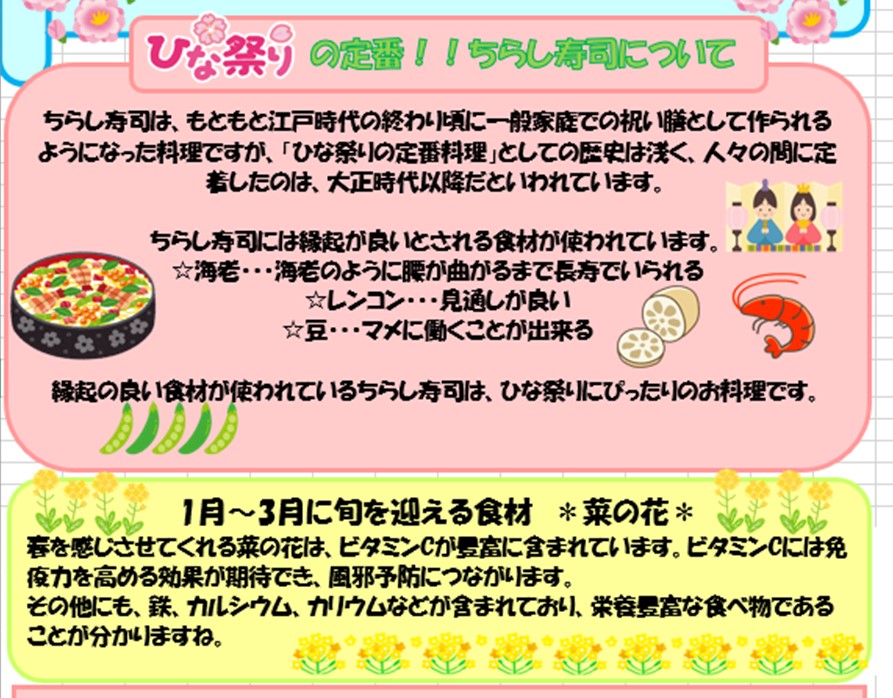
2022.02.28
スタッフ日記
2022.02.13
スタッフ日記
2022.02.03
スタッフ日記
2022.02.03
スタッフ日記
2022.03.27
スタッフ日記
2022.03.19
スタッフ日記 みなさんこんにちは!アーバンケア島之内生活介護課の
小寺です!
前回の更新から、日にちがたってしまい
申し訳ございません( ノД`)シクシク…
もう三月も終わってしまう😓
さて!三月と言えば⁉
そうです!ひな祭りです!
特養のご利用者様と一緒に準備しました!
ご覧ください(^_^)
色塗りをしていますね(*^^*)
すごくきれいな色使いですね!!完成が気になります😎
おっと⁉これは何をしているのでしょうか❔
何をちぎっているのやら…
折り紙をちぎって花びらにしていたんですね!
なるほど!
張り付けの作業中ですね!
職員も参戦です!
そしてついに⁉
完成しました!!作品は次の時に紹介しますね!
ひな祭りということでお内裏様とお雛様と
記念撮影もしました✨
5階のご利用者様♪
3階のご利用者様♪
みなさんこんにちは!アーバンケア島之内生活介護課の
小寺です!
前回の更新から、日にちがたってしまい
申し訳ございません( ノД`)シクシク…
もう三月も終わってしまう😓
さて!三月と言えば⁉
そうです!ひな祭りです!
特養のご利用者様と一緒に準備しました!
ご覧ください(^_^)
色塗りをしていますね(*^^*)
すごくきれいな色使いですね!!完成が気になります😎
おっと⁉これは何をしているのでしょうか❔
何をちぎっているのやら…
折り紙をちぎって花びらにしていたんですね!
なるほど!
張り付けの作業中ですね!
職員も参戦です!
そしてついに⁉
完成しました!!作品は次の時に紹介しますね!
ひな祭りということでお内裏様とお雛様と
記念撮影もしました✨
5階のご利用者様♪
3階のご利用者様♪
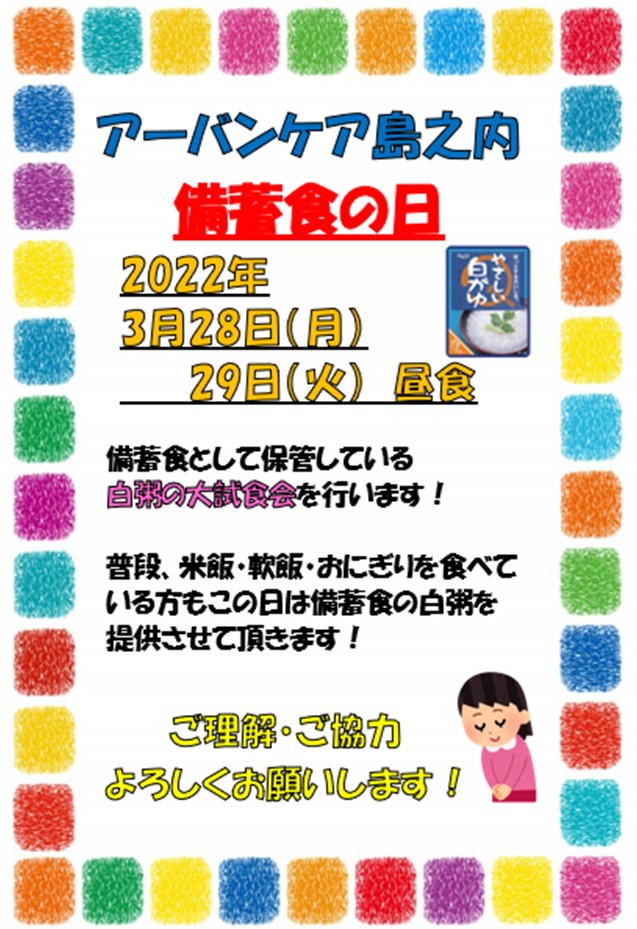
2022.03.09
スタッフ日記
2022.03.03
スタッフ日記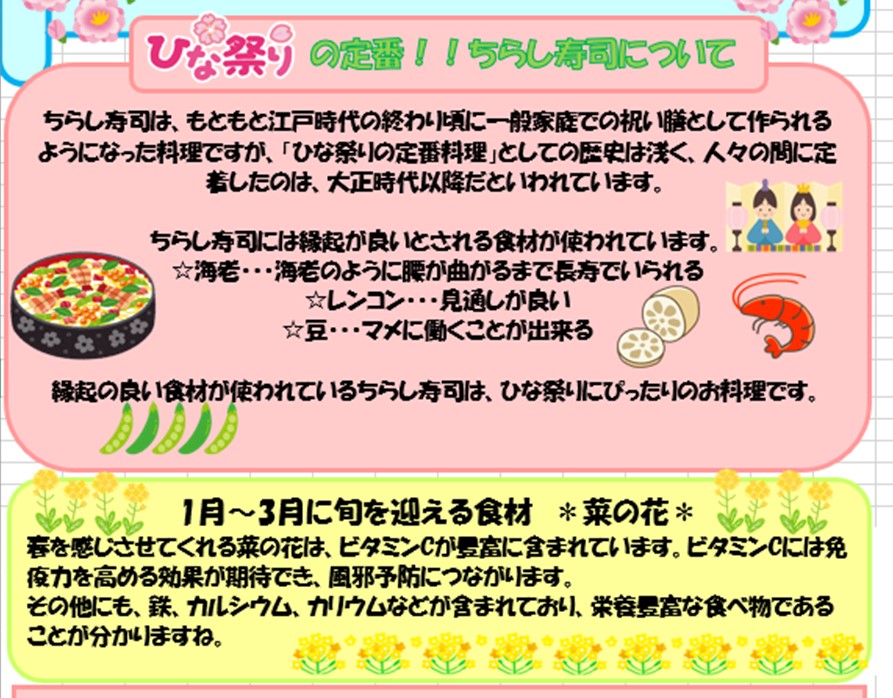
2022.02.28
スタッフ日記
2022.02.13
スタッフ日記 こんにちは!
管理栄養士の岸本です!
昨日、節分の鬼退治の様子を載せましたが、5階では鬼のブロックでも鬼退治を行ったようです👹!!
おにはそと~~!!
やった!やっつけました!!!
昨日の内容も合わせてご覧ください💖
節分~恵方巻!~
節分、鬼退治!
こんにちは!
管理栄養士の岸本です!
昨日、節分の鬼退治の様子を載せましたが、5階では鬼のブロックでも鬼退治を行ったようです👹!!
おにはそと~~!!
やった!やっつけました!!!
昨日の内容も合わせてご覧ください💖
節分~恵方巻!~
節分、鬼退治!
 こんにちは!管理栄養士の岸本です!
特養では、職員が鬼の格好になって、豆まきをしました!
もじゃもじゃの頭には角が2本!トラ柄のパンツに金棒を持ったこわーい鬼です👹
豆の代わりにボールを使いました🔴🔵🥎
「うぉ~~~!」
「わぁ~おには外~~~!!」
皆さん必死に投げてやっつけようとしてくださいました😊
「うわ!!それ!!」
「ああぁ~~!!やられた~~!」
やっつけたら鬼は改心。
仲直り😊✨
鬼さんは「やられたので帰ります👹」とのことでした🌟
これで1年間は平和に元気に過ごせますね✨
「また来年👹」と言い残していきました😅
優しく改心したままの鬼さんでまた来てほしいものですね!
[video width="1920" height="1440" mp4="https://yoshijukai.or.jp/urban-shimanouchi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/156_Trim.mp4"][/video]
こんにちは!管理栄養士の岸本です!
特養では、職員が鬼の格好になって、豆まきをしました!
もじゃもじゃの頭には角が2本!トラ柄のパンツに金棒を持ったこわーい鬼です👹
豆の代わりにボールを使いました🔴🔵🥎
「うぉ~~~!」
「わぁ~おには外~~~!!」
皆さん必死に投げてやっつけようとしてくださいました😊
「うわ!!それ!!」
「ああぁ~~!!やられた~~!」
やっつけたら鬼は改心。
仲直り😊✨
鬼さんは「やられたので帰ります👹」とのことでした🌟
これで1年間は平和に元気に過ごせますね✨
「また来年👹」と言い残していきました😅
優しく改心したままの鬼さんでまた来てほしいものですね!
[video width="1920" height="1440" mp4="https://yoshijukai.or.jp/urban-shimanouchi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/156_Trim.mp4"][/video]
 こんにちは!管理栄養士の岸本です!
本日は節分ですね!
栄養課では朝から恵方巻づくりに必死でした💦
アーバンケア島之内特製『恵方巻』✨✨
海苔は口の中やのどにくっつきやすく誤嚥のしやすい食べ物です。
そのため、海苔ではなく薄焼き卵で巻きます😋
海苔より破れやすく、巻き終わりもくっつかないので巻くのは海苔より難しいのです…
しかし、そこは腕の見せ所💪
完璧な巻き寿司が完成しました✨
切るのも難しいです💦
(恵方巻は本来、包丁で切ることは「福を途切れさせる」「縁を切る」ことを意味するので切ってはいけないとされていますが、喉詰めを防ぐため、アーバンケア島之内では、切って提供させて頂いています。)
切っている途中でも巻きがくずれる恐れがあるため、うまく切る必要があるのです💧
佐藤管理栄養士が切る作業をしていました!
上手に切れるかなぁ~~??
おいしい恵方巻ができました!!
そして献立の放送では、ご利用者様が今年の恵方と節分の豆知識を放送してくださいました😊
[video width="1920" height="1080" mp4="https://yoshijukai.or.jp/urban-shimanouchi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/献立恵方巻.mp4"][/video]
[video width="1920" height="1080" mp4="https://yoshijukai.or.jp/urban-shimanouchi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/003_Trim_Trim-1.mp4"][/video]
[video width="1920" height="1080" mp4="https://yoshijukai.or.jp/urban-shimanouchi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/003_Trim_Trim-2_Trim_Trim_Trim.mp4"][/video]
[video width="1920" height="1080" mp4="https://yoshijukai.or.jp/urban-shimanouchi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/003_Trim_Trim-3_Trim_Trim.mp4"][/video]
[video width="1920" height="1080" mp4="https://yoshijukai.or.jp/urban-shimanouchi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/003_Trim_Trim-3.mp4"][/video]
今年の恵方は「北北西」!🧭
現在の豆まきは「大豆」を使うことが一般的ですが、かつては米、麦、粟、炭なども使われていたとのこと。
勉強になりました✎
「きれいなぁ~」「美味しいわぁ~」と笑顔で答えて下さいました😊
これで皆様も福を巻き込めたと思います!
今年も素敵な幸せな1年になりますように🍀
こんにちは!管理栄養士の岸本です!
本日は節分ですね!
栄養課では朝から恵方巻づくりに必死でした💦
アーバンケア島之内特製『恵方巻』✨✨
海苔は口の中やのどにくっつきやすく誤嚥のしやすい食べ物です。
そのため、海苔ではなく薄焼き卵で巻きます😋
海苔より破れやすく、巻き終わりもくっつかないので巻くのは海苔より難しいのです…
しかし、そこは腕の見せ所💪
完璧な巻き寿司が完成しました✨
切るのも難しいです💦
(恵方巻は本来、包丁で切ることは「福を途切れさせる」「縁を切る」ことを意味するので切ってはいけないとされていますが、喉詰めを防ぐため、アーバンケア島之内では、切って提供させて頂いています。)
切っている途中でも巻きがくずれる恐れがあるため、うまく切る必要があるのです💧
佐藤管理栄養士が切る作業をしていました!
上手に切れるかなぁ~~??
おいしい恵方巻ができました!!
そして献立の放送では、ご利用者様が今年の恵方と節分の豆知識を放送してくださいました😊
[video width="1920" height="1080" mp4="https://yoshijukai.or.jp/urban-shimanouchi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/献立恵方巻.mp4"][/video]
[video width="1920" height="1080" mp4="https://yoshijukai.or.jp/urban-shimanouchi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/003_Trim_Trim-1.mp4"][/video]
[video width="1920" height="1080" mp4="https://yoshijukai.or.jp/urban-shimanouchi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/003_Trim_Trim-2_Trim_Trim_Trim.mp4"][/video]
[video width="1920" height="1080" mp4="https://yoshijukai.or.jp/urban-shimanouchi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/003_Trim_Trim-3_Trim_Trim.mp4"][/video]
[video width="1920" height="1080" mp4="https://yoshijukai.or.jp/urban-shimanouchi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/003_Trim_Trim-3.mp4"][/video]
今年の恵方は「北北西」!🧭
現在の豆まきは「大豆」を使うことが一般的ですが、かつては米、麦、粟、炭なども使われていたとのこと。
勉強になりました✎
「きれいなぁ~」「美味しいわぁ~」と笑顔で答えて下さいました😊
これで皆様も福を巻き込めたと思います!
今年も素敵な幸せな1年になりますように🍀