「ほんわか写真館」で記事を検索しました。

2021.11.15
ほんわか写真館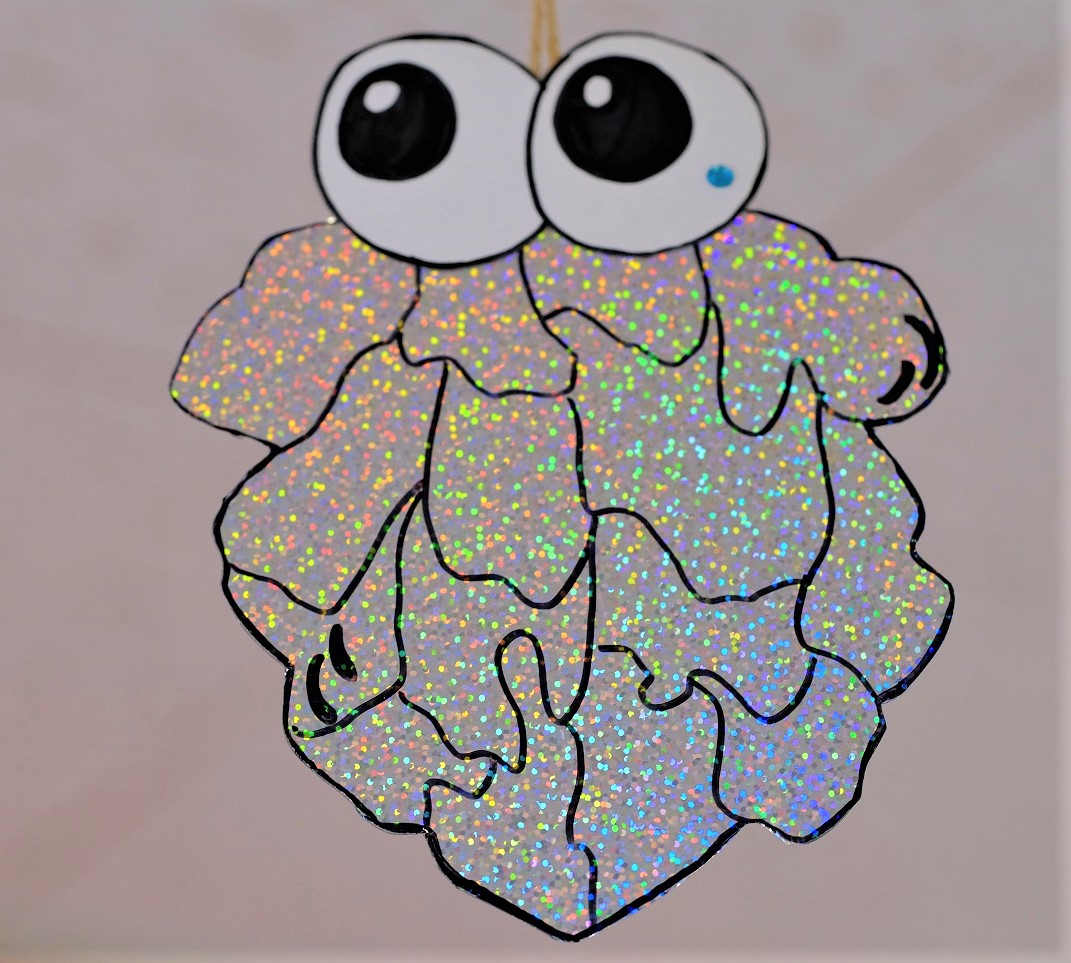
2021.11.12
ほんわか写真館
2021.11.09
ほんわか写真館
2021.10.13
ほんわか写真館
2021.09.29
ほんわか写真館
2021.09.11
ほんわか写真館
2021.09.10
ほんわか写真館
2021.08.21
ほんわか写真館
2021.08.13
ほんわか写真館
2021.11.15
ほんわか写真館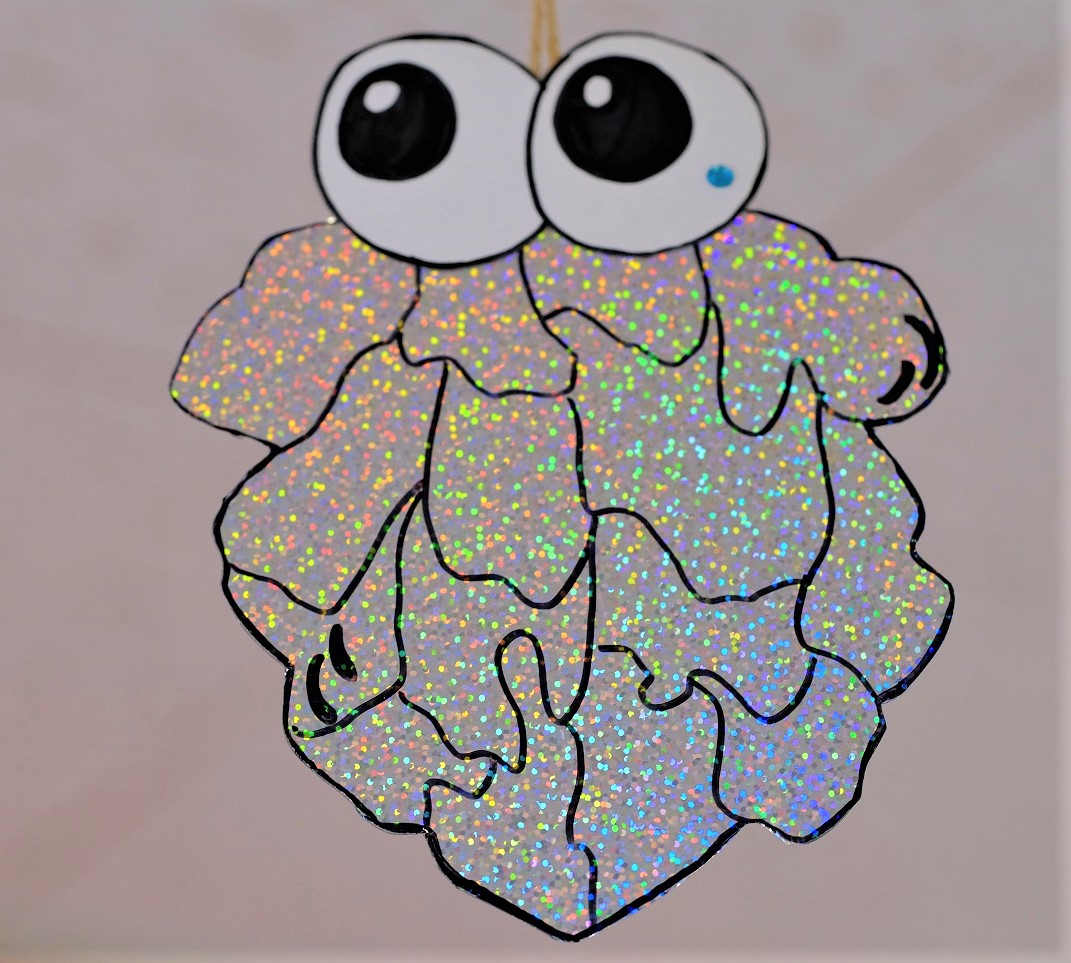 「相手の気持ちになって考えよう」と、
ケアの現場ではよく言われます。
しかし人間は、自分の心の中には自分の考えが一杯詰まっているので
本来、相手の気持ちを考え、さらに受容すると言うのはとても苦手なのです。
SNSで平気でいじめをしてしまうのも、
相手の気持ちなど全く考えないからです。
しかし私たちの仕事は、「相手の気持ちを考えたり、受け止めたりすること」
それが出来なければ、専門職としての魅力は半減します。
この仕事に就いたからには、ケアの実践者として「自分はどうありたいのか」と
問いかけなければならないでしょう。
「相手の気持ちを考える」
そのため普段から柔らかい思考を持たなければなりません。
日頃から相手はどう思っているのだろうか?と考える姿勢が必要です。
ちょっとでいいのです。
ほんの少し立ち止まり、相手の気持ちを考える時間を持ちます。
そのトレーニングのひとつとして、どんなものにも声を掛け、
何を思っているのか想像するという、擬人化トレーニングをすることです。
それを普段からちょくちょく行うことです。
以下の3枚のお猿の写真は、私が撮影したものですが、
1枚1枚の写真に、「お猿の気持ち(思っていること)」を考えてみて、
書いてみてください。
ちょっとしたショートストーリーが出来るかもしれませんよ。
どうでしょうか。一枚一枚にお猿の気持ちを想像して書いてみる。
この瞬間に、あなたは「お猿の立場」で考えています。
どんなものでもいいので、ちょっと立ち止って、考えてみる。
そんなトレーニングをやってみてください。
今は電車に乗っていても何が起きるかわからない時代です。
スマホばっかりやってないで、周辺に目をやり、いろいろ想像してみることですね。
それだけでも心の柔軟性は養われます。
スマホの狭い画面ばかり見ていては得られない、心の世界を広げる情報がそこにあります。
「相手の気持ちになって考えよう」と、
ケアの現場ではよく言われます。
しかし人間は、自分の心の中には自分の考えが一杯詰まっているので
本来、相手の気持ちを考え、さらに受容すると言うのはとても苦手なのです。
SNSで平気でいじめをしてしまうのも、
相手の気持ちなど全く考えないからです。
しかし私たちの仕事は、「相手の気持ちを考えたり、受け止めたりすること」
それが出来なければ、専門職としての魅力は半減します。
この仕事に就いたからには、ケアの実践者として「自分はどうありたいのか」と
問いかけなければならないでしょう。
「相手の気持ちを考える」
そのため普段から柔らかい思考を持たなければなりません。
日頃から相手はどう思っているのだろうか?と考える姿勢が必要です。
ちょっとでいいのです。
ほんの少し立ち止まり、相手の気持ちを考える時間を持ちます。
そのトレーニングのひとつとして、どんなものにも声を掛け、
何を思っているのか想像するという、擬人化トレーニングをすることです。
それを普段からちょくちょく行うことです。
以下の3枚のお猿の写真は、私が撮影したものですが、
1枚1枚の写真に、「お猿の気持ち(思っていること)」を考えてみて、
書いてみてください。
ちょっとしたショートストーリーが出来るかもしれませんよ。
どうでしょうか。一枚一枚にお猿の気持ちを想像して書いてみる。
この瞬間に、あなたは「お猿の立場」で考えています。
どんなものでもいいので、ちょっと立ち止って、考えてみる。
そんなトレーニングをやってみてください。
今は電車に乗っていても何が起きるかわからない時代です。
スマホばっかりやってないで、周辺に目をやり、いろいろ想像してみることですね。
それだけでも心の柔軟性は養われます。
スマホの狭い画面ばかり見ていては得られない、心の世界を広げる情報がそこにあります。

2021.11.09
ほんわか写真館
2021.11.09
ほんわか写真館
2021.10.13
ほんわか写真館
2021.09.29
ほんわか写真館 センター長の石川です。
ふと窓を開けると
「なんだあの雲は?」
まるで、ゲゲゲの鬼太郎に出てくる「いったんもめん」のような雲でした。
雲は普通、モクモクした形なのに、まるで切ったような長方形になっていました。
おそらくは、2本の飛行機雲が滲んで交わって長方形の雲が出来たと思うのですが、
それにしても、まるで切ったかのような形は摩訶不思議です。
雲って瞬間瞬間に形を変える自然が織りなす芸術作品ですね。
心が疲れた時、何も考えずに空を見上げ、雲を見るだけで
少しは余裕のない心に空き地が出来るかもしれません。
でも雨の日に見上げたら、顔がびしょ濡れになるだけですけど(笑)
センター長の石川です。
ふと窓を開けると
「なんだあの雲は?」
まるで、ゲゲゲの鬼太郎に出てくる「いったんもめん」のような雲でした。
雲は普通、モクモクした形なのに、まるで切ったような長方形になっていました。
おそらくは、2本の飛行機雲が滲んで交わって長方形の雲が出来たと思うのですが、
それにしても、まるで切ったかのような形は摩訶不思議です。
雲って瞬間瞬間に形を変える自然が織りなす芸術作品ですね。
心が疲れた時、何も考えずに空を見上げ、雲を見るだけで
少しは余裕のない心に空き地が出来るかもしれません。
でも雨の日に見上げたら、顔がびしょ濡れになるだけですけど(笑)

2021.09.10
ほんわか写真館 センター長の石川です。
雨模様の天気は、まだ数日続くみたいですね。
コロナと言い、お天気だけでなく、心も晴れない日が続きます。
さて次回からはいよいよ認知症の人をどう理解し、
私たちはどのように関わればよいのかと言うことについて、話を再スタートさせます。
その前に、私は「天狗」になっていないか
つまり、高慢ちきで、思い上がりがあるのではないかと、
振り返る必要があります。
ですから、一度、鼻をつまんでみることにします。
人間誰しも「天狗になる」ことがあります。
これは年齢関係ありません。
若い人でも天狗になる、つまり「いい気になる」ことは多々あるのです。
もちろんベテランにも。
[caption id="attachment_2891" align="alignnone" width="1560"] 天狗岩 自然のものですよ。[/caption]
この仕事では、ケア側は、ある意味「優位的立場」にいます。
それが利用者に対して「いい気になる」ことに繋がってしまうことがあります。
逆を言えば、それをわかることができる職場でもあるのです。
自分自身を振り返り、人間的成長に繋げられる仕事でもあるのですよね。
私も時に自分の鼻をつまみ、いい気になっていないか確かめることにします。
人間誰でも天狗になってしまうことがあります。
でもそのことに気づくかどうかが大切なのですね。
センター長の石川です。
雨模様の天気は、まだ数日続くみたいですね。
コロナと言い、お天気だけでなく、心も晴れない日が続きます。
さて次回からはいよいよ認知症の人をどう理解し、
私たちはどのように関わればよいのかと言うことについて、話を再スタートさせます。
その前に、私は「天狗」になっていないか
つまり、高慢ちきで、思い上がりがあるのではないかと、
振り返る必要があります。
ですから、一度、鼻をつまんでみることにします。
人間誰しも「天狗になる」ことがあります。
これは年齢関係ありません。
若い人でも天狗になる、つまり「いい気になる」ことは多々あるのです。
もちろんベテランにも。
[caption id="attachment_2891" align="alignnone" width="1560"] 天狗岩 自然のものですよ。[/caption]
この仕事では、ケア側は、ある意味「優位的立場」にいます。
それが利用者に対して「いい気になる」ことに繋がってしまうことがあります。
逆を言えば、それをわかることができる職場でもあるのです。
自分自身を振り返り、人間的成長に繋げられる仕事でもあるのですよね。
私も時に自分の鼻をつまみ、いい気になっていないか確かめることにします。
人間誰でも天狗になってしまうことがあります。
でもそのことに気づくかどうかが大切なのですね。

2021.08.13
ほんわか写真館