「心の荷物預かり所」で記事を検索しました。
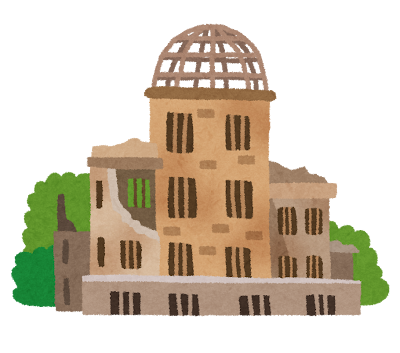
2025.08.14
心の荷物預かり所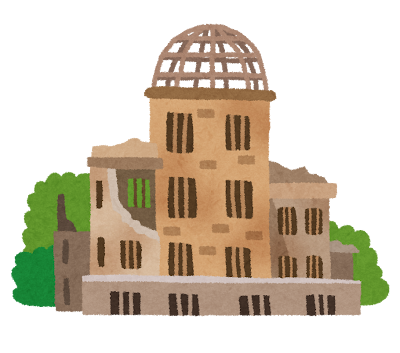
2025.08.07
心の荷物預かり所
2025.07.26
心の荷物預かり所
2025.07.23
心の荷物預かり所
2025.04.25
心の荷物預かり所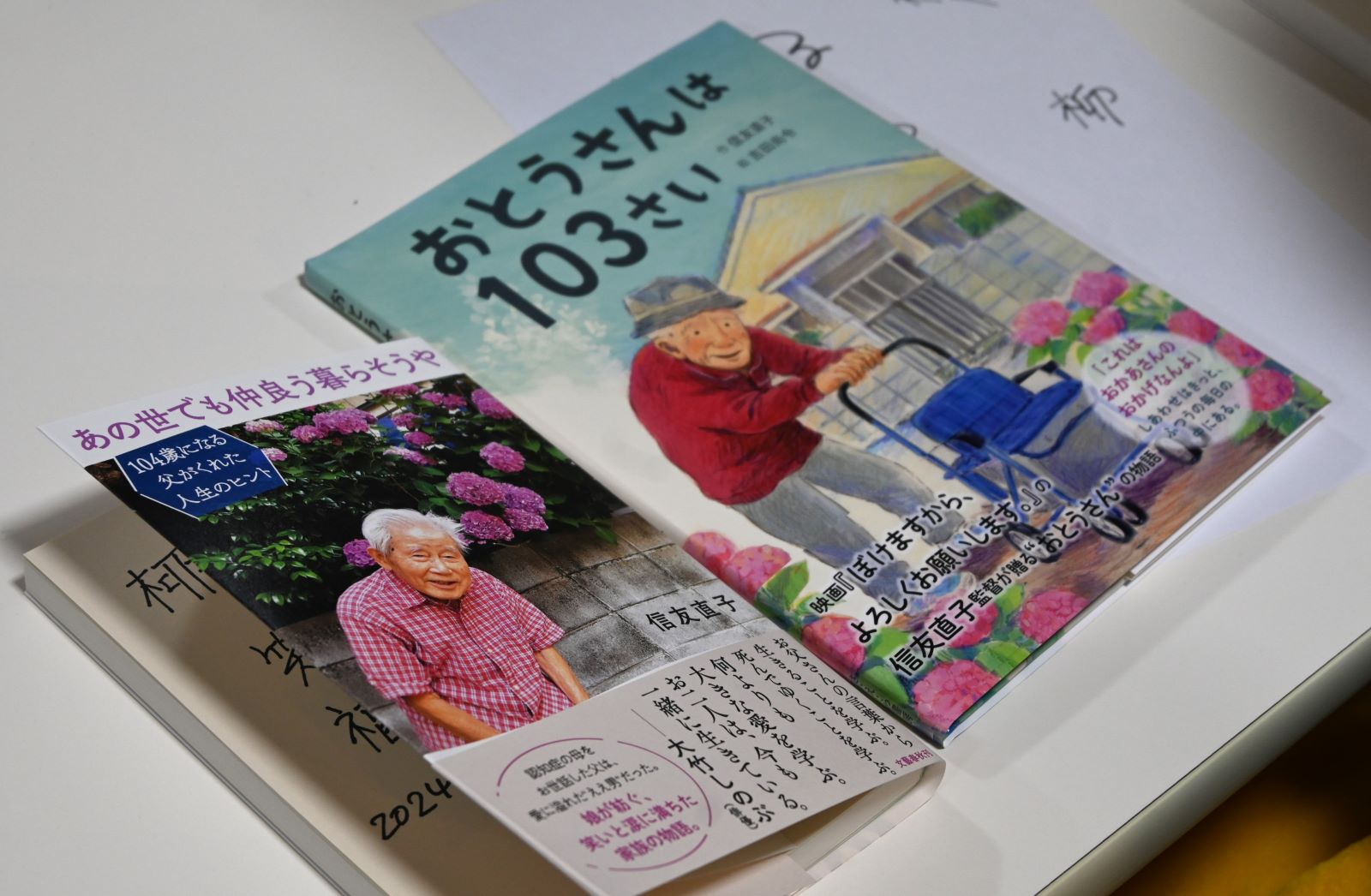
2025.03.17
心の荷物預かり所
2025.03.04
心の荷物預かり所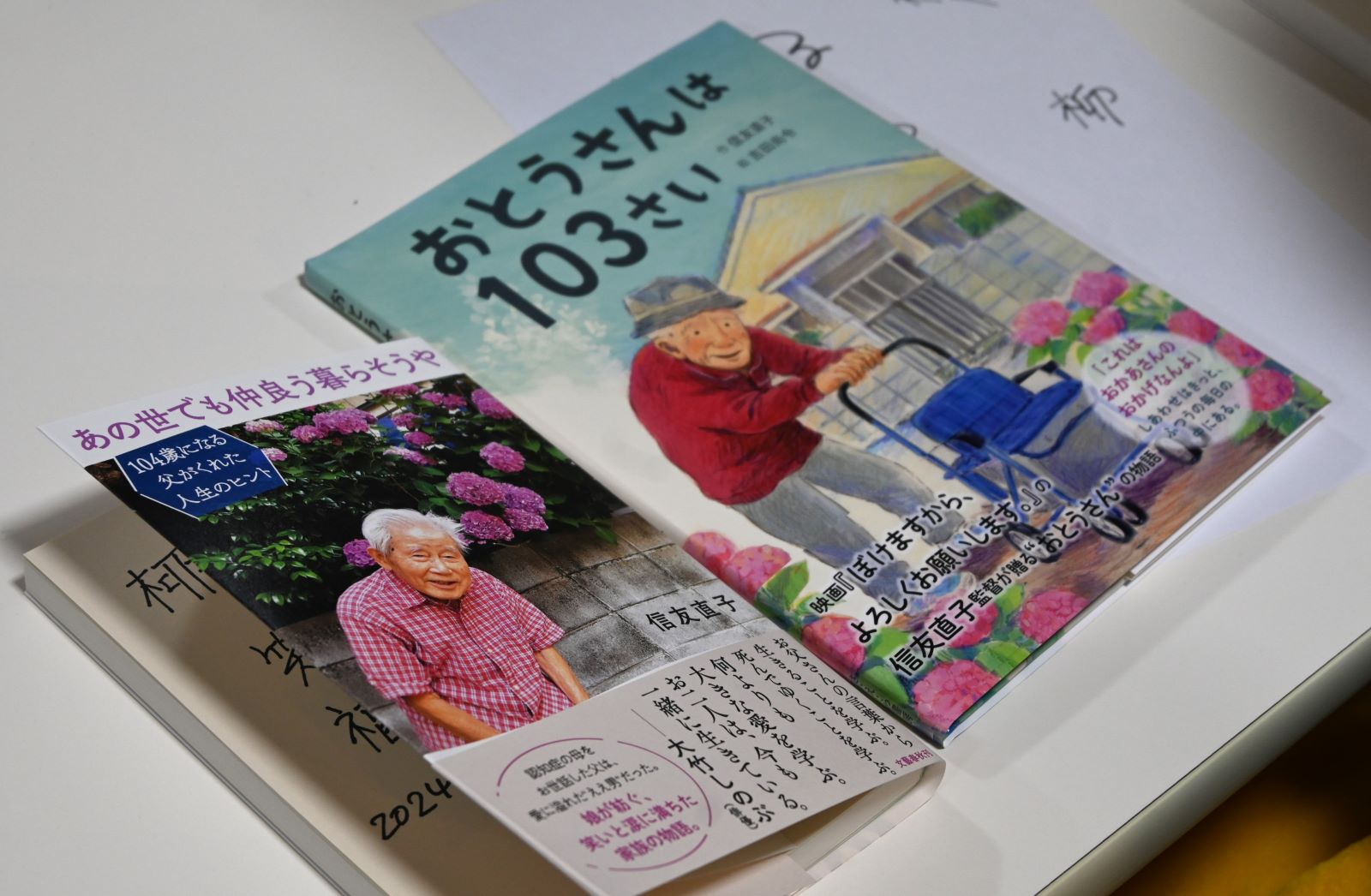
2025.02.05
心の荷物預かり所
2025.01.09
心の荷物預かり所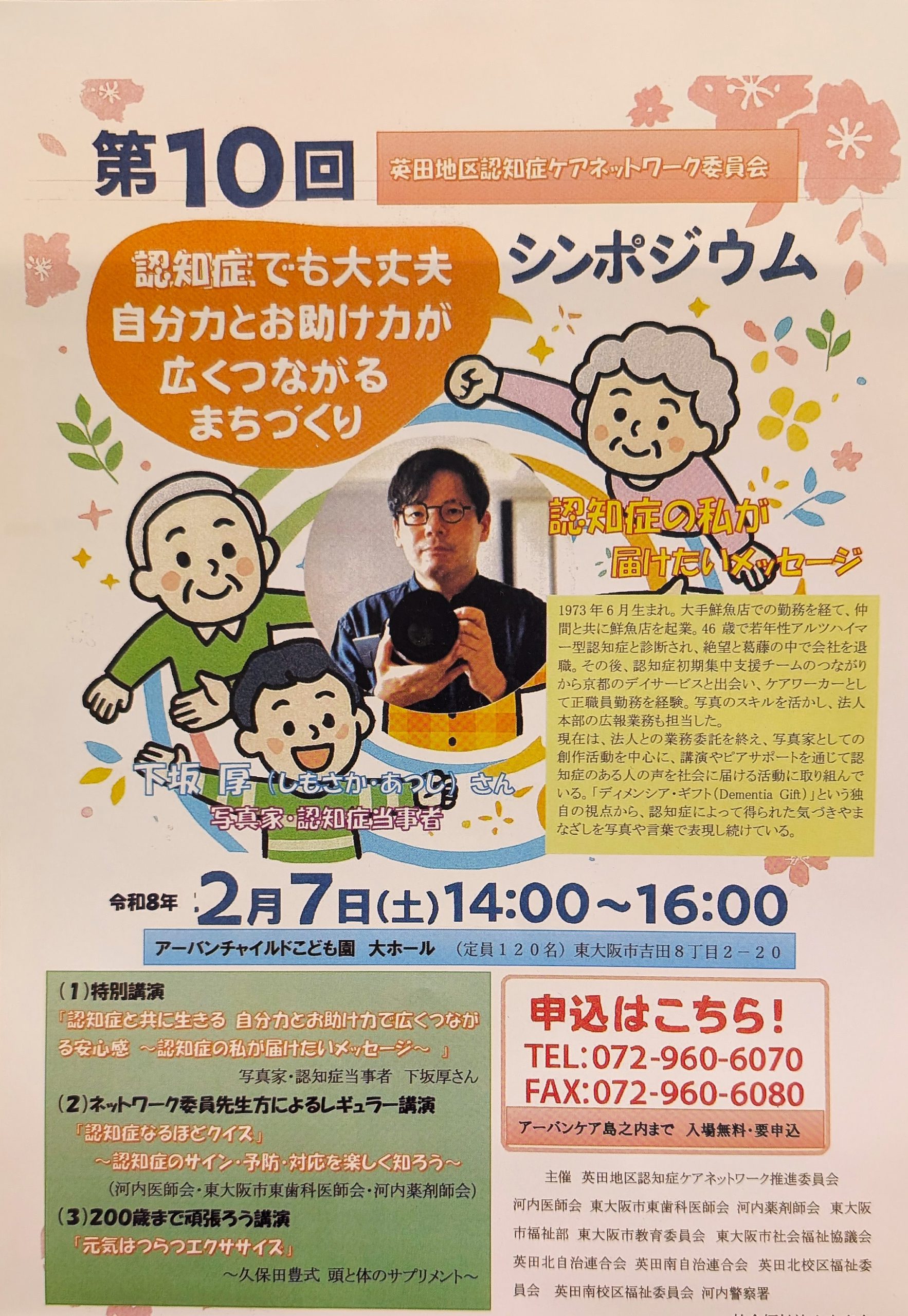
2025.12.24
心の荷物預かり所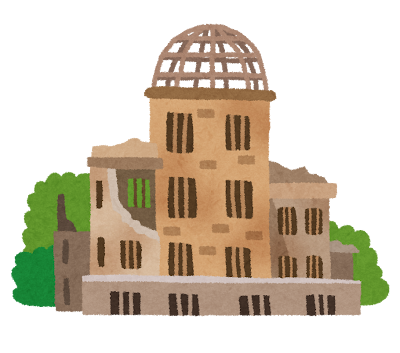 8月は、特に前半は、なんか心が沈みます。
6日のヒロシマ 9日のナガサキ 12日の日航機墜落 そして15日の終戦の日
ずっと亡き方々の慰霊の日という感じですね。
12日の日航機事故は、その原因がいまだに謎を生んでいる事故ですが、
当時私はある法人の老人ホームに勤めていました。
この年の7月末、長野県の老人ホームで裏山が崩れ、多くの入居者が亡くなる災害がありました。
同業者でもあり、この災害のことはよく覚えています。
当時私が勤めていた法人の理事長は、全国老人施設協議会の会長であり、
たびたび東京へ出張していました。
そしていつも日航123便のあの時間の飛行機で帰って来るのでした。
8月12日もこの飛行機に乗る予定で、予約もしていたそうです。
しかし長野で起きた特養の土砂災害では20名以上の利用者が亡くなっており、
その後の対応も含めて長野の現場に行くことになり、123便の搭乗をキャンセルしたのです。
理事長はこうして事なきを得たのですが、代わりに乗った人がいたのですね。
毎年8月12日になると、このことを思い出します。
なんと表現していいのかわからない人生の運命の行方ですね。
地滑りで老人ホームが埋まるというような災害がなければ、理事長はいつものように
123便に乗っていたかもしれません。
広島、長崎も、人数ではなく、一人一人にそれぞれの人生ドラマがあったこと
そのことを忘れないでいたいですね。
8月は、特に前半は、なんか心が沈みます。
6日のヒロシマ 9日のナガサキ 12日の日航機墜落 そして15日の終戦の日
ずっと亡き方々の慰霊の日という感じですね。
12日の日航機事故は、その原因がいまだに謎を生んでいる事故ですが、
当時私はある法人の老人ホームに勤めていました。
この年の7月末、長野県の老人ホームで裏山が崩れ、多くの入居者が亡くなる災害がありました。
同業者でもあり、この災害のことはよく覚えています。
当時私が勤めていた法人の理事長は、全国老人施設協議会の会長であり、
たびたび東京へ出張していました。
そしていつも日航123便のあの時間の飛行機で帰って来るのでした。
8月12日もこの飛行機に乗る予定で、予約もしていたそうです。
しかし長野で起きた特養の土砂災害では20名以上の利用者が亡くなっており、
その後の対応も含めて長野の現場に行くことになり、123便の搭乗をキャンセルしたのです。
理事長はこうして事なきを得たのですが、代わりに乗った人がいたのですね。
毎年8月12日になると、このことを思い出します。
なんと表現していいのかわからない人生の運命の行方ですね。
地滑りで老人ホームが埋まるというような災害がなければ、理事長はいつものように
123便に乗っていたかもしれません。
広島、長崎も、人数ではなく、一人一人にそれぞれの人生ドラマがあったこと
そのことを忘れないでいたいですね。
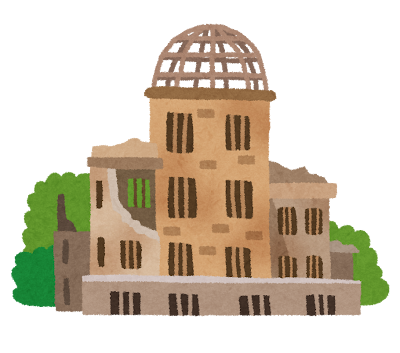 ヒロシマ、ナガサキの原爆投下から80年ですね。
昨日の広島県知事の平和宣言は、心に響くものがありました。
洋上でもなく、軍事施設でもない、ただただ普通に暮らしていた市民を虐殺したのが原爆です。
赤ん坊から幼子、高齢者など弱者も含んだ、両市合わせて21~22万人の命を
瞬間的に奪ったもの。それが核兵器です。(被ばく戦没者数は50万人を上回る)
つい最近まで知らなかったのですが、長崎市出身の福山雅治が、
廃墟となり、焼かれた被爆クスノキが、今は大きな樹木になっているのですが
そのことを題材にした歌を唄っていたのですね。
今は多くの子どもたちも唄っているようです。
静かに、力強く、平和を訴える歌ですね。
福山雅治のオリジナル映像と
生き続けている被爆樹木の映像と
二つを貼り付けておきます。
是非とも聞いて、見てくださいね。
https://www.youtube.com/watch?v=vuxCfIijgIc&list=RDvuxCfIijgIc&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=JumRmUwmOgs&list=RDJumRmUwmOgs&start_radio=1
ヒロシマ、ナガサキの原爆投下から80年ですね。
昨日の広島県知事の平和宣言は、心に響くものがありました。
洋上でもなく、軍事施設でもない、ただただ普通に暮らしていた市民を虐殺したのが原爆です。
赤ん坊から幼子、高齢者など弱者も含んだ、両市合わせて21~22万人の命を
瞬間的に奪ったもの。それが核兵器です。(被ばく戦没者数は50万人を上回る)
つい最近まで知らなかったのですが、長崎市出身の福山雅治が、
廃墟となり、焼かれた被爆クスノキが、今は大きな樹木になっているのですが
そのことを題材にした歌を唄っていたのですね。
今は多くの子どもたちも唄っているようです。
静かに、力強く、平和を訴える歌ですね。
福山雅治のオリジナル映像と
生き続けている被爆樹木の映像と
二つを貼り付けておきます。
是非とも聞いて、見てくださいね。
https://www.youtube.com/watch?v=vuxCfIijgIc&list=RDvuxCfIijgIc&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=JumRmUwmOgs&list=RDJumRmUwmOgs&start_radio=1

2025.07.26
心の荷物預かり所
2025.07.23
心の荷物預かり所
2025.04.25
心の荷物預かり所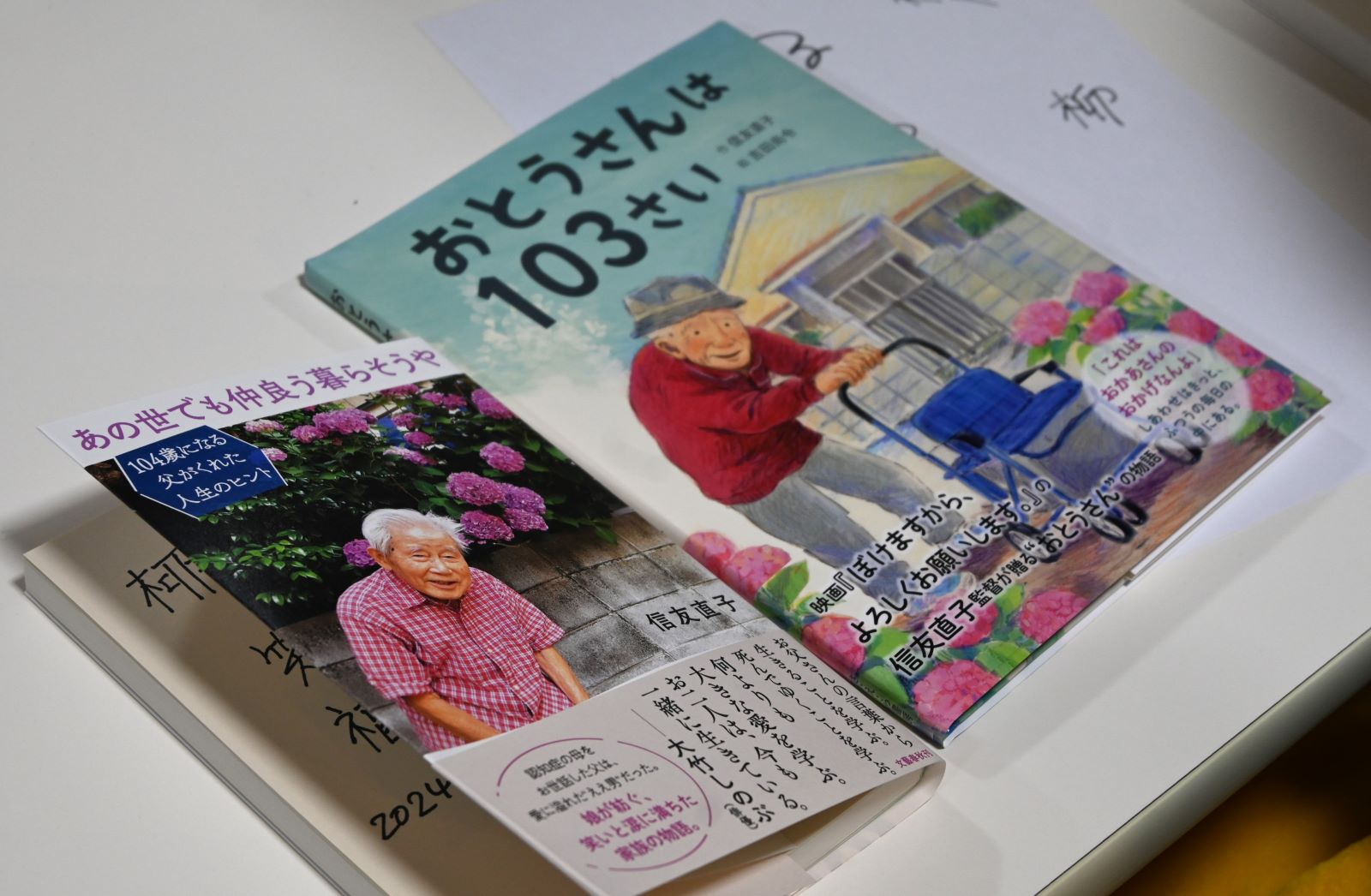
2025.03.17
心の荷物預かり所
2025.03.04
心の荷物預かり所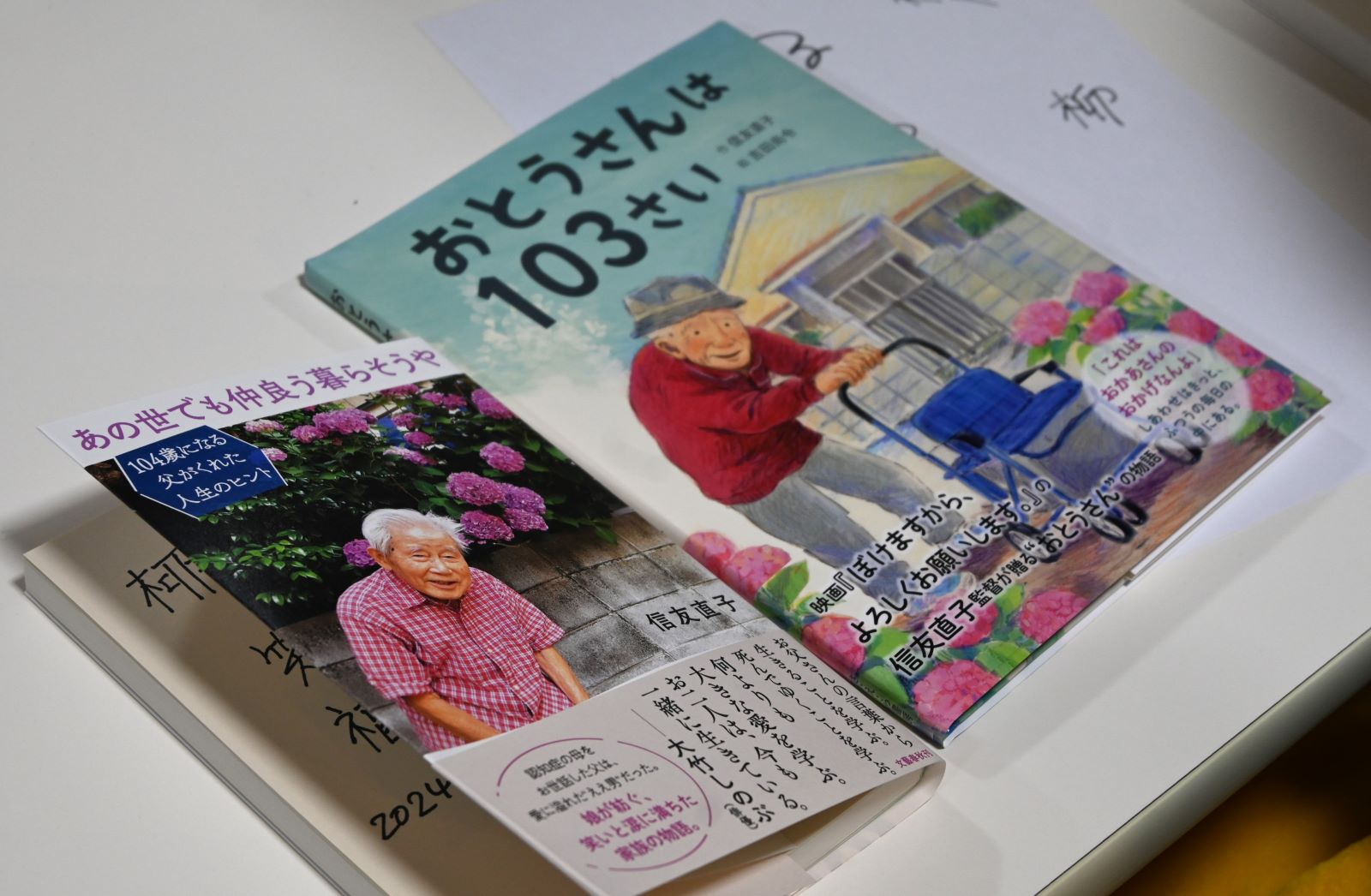
2025.02.05
心の荷物預かり所
2025.01.09
心の荷物預かり所