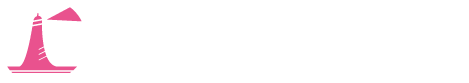2021.03.19
イベント
2021.03.04
イベント
2021.02.25
イベント
2021.02.15
イベント
2021.02.11
その他お知らせ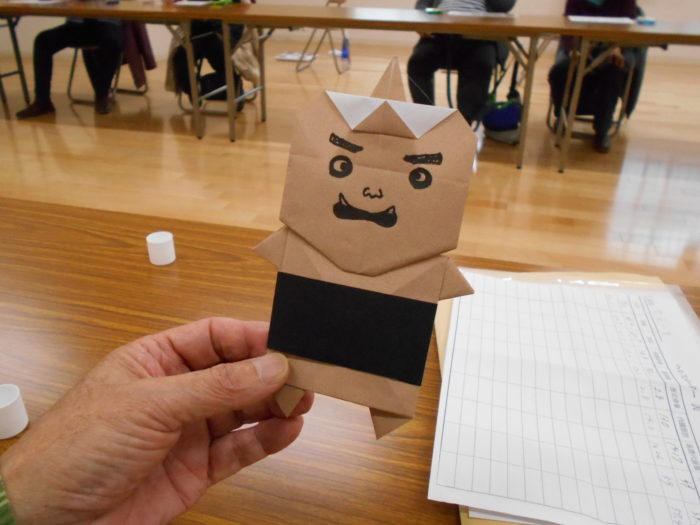
2021.01.18
イベント
2021.01.09
イベント
2021.01.04
イベント
2020.12.30
ネットワーク
2020.12.22
イベント
2021.03.19
イベント
2021.03.04
イベント
2021.02.25
イベント
2021.02.15
イベント
2021.02.11
その他お知らせ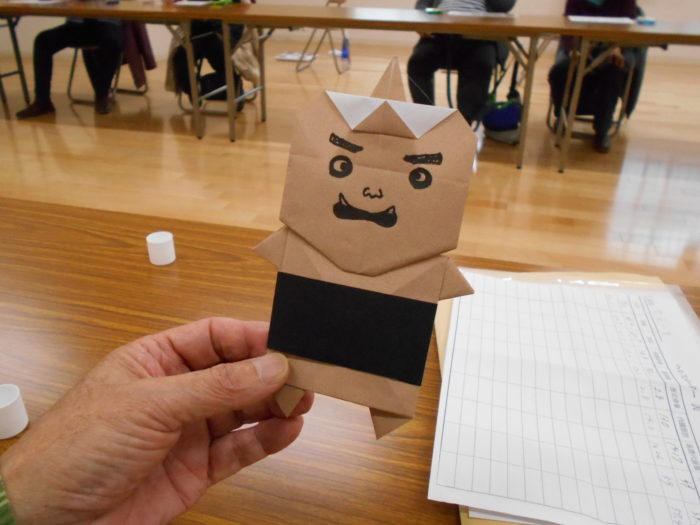
2021.01.18
イベント
2021.01.09
イベント
2021.01.04
イベント
2020.12.30
ネットワーク
2020.12.22
イベント