「心の荷物預かり所」で記事を検索しました。
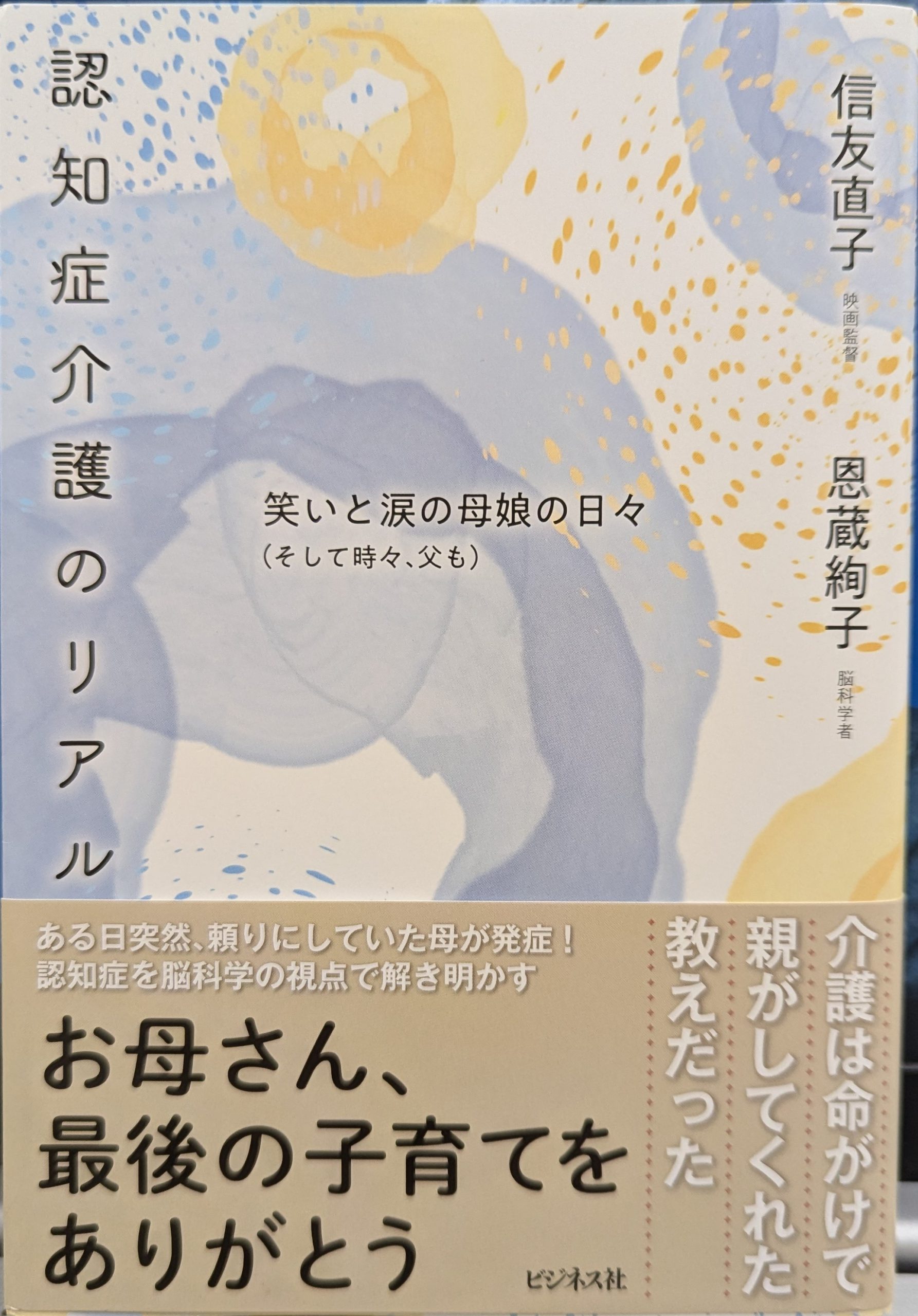
2024.08.06
心の荷物預かり所
2024.07.25
心の荷物預かり所
2024.07.12
心の荷物預かり所
2024.06.13
心の荷物預かり所
2024.06.10
心の荷物預かり所
2024.06.03
心の荷物預かり所
2024.05.08
心の荷物預かり所
2024.04.25
心の荷物預かり所
2024.04.03
心の荷物預かり所
2024.02.14
心の荷物預かり所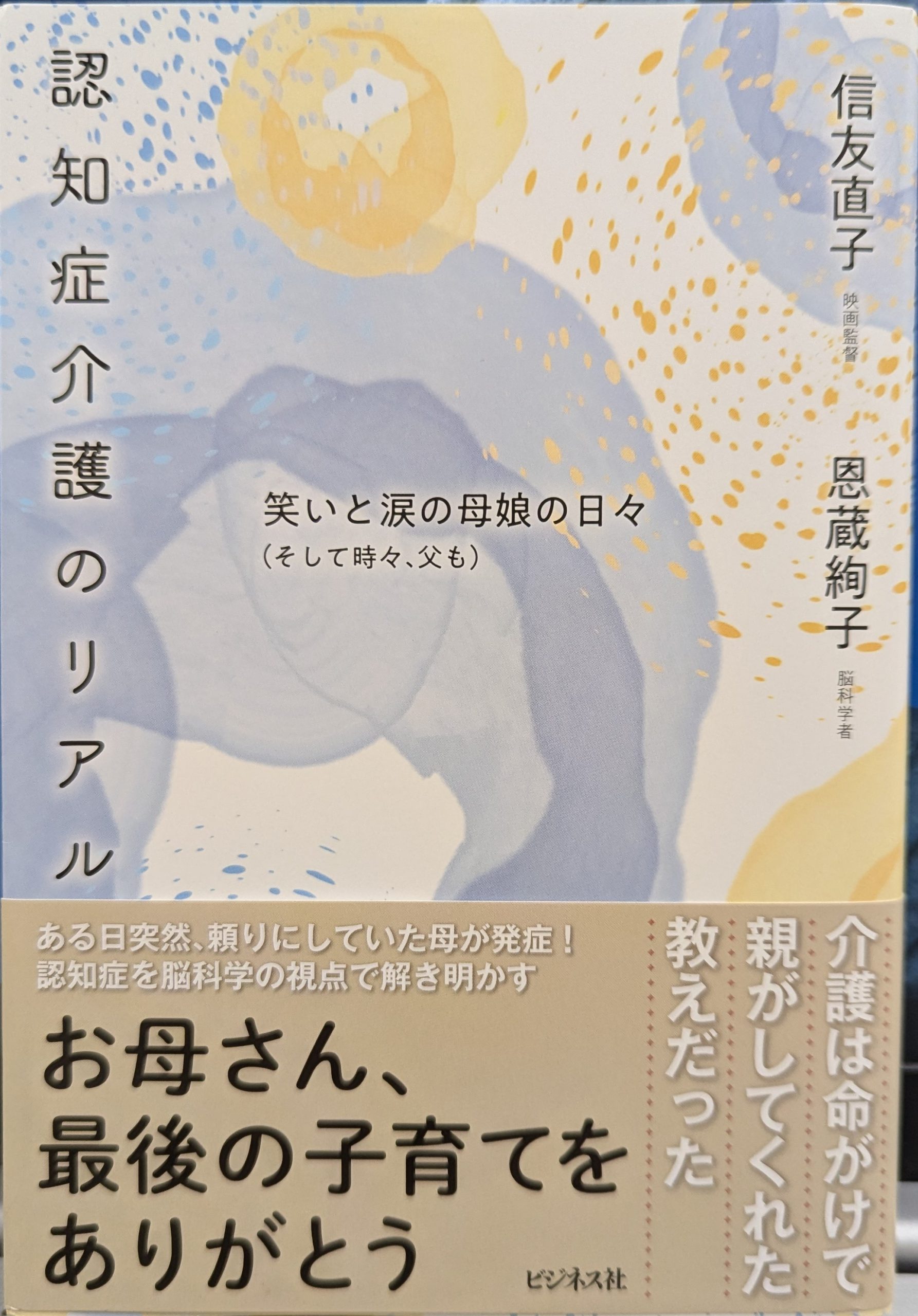
2024.08.06
心の荷物預かり所
2024.07.25
心の荷物預かり所
2024.07.12
心の荷物預かり所 英田南校区の安心声掛け訓練、
いよいよ来週の土曜日です。
全国津々浦々、どこにお住まいの方でも参加できます。
但し、交通費の支給はありません(笑)
但し但し、お昼ごはんのカレーは、無料でたっぷり食べれますよ!
それはともかく、声掛け訓練自体は
認知症の人を地域で温かく見守っていくためのもの。
自分力とお助け力で繋がっていきましょう!
もう一つは、映画「ぼけますから、よろしくお願いします」の
映画監督、信友直子さんの講演会です。
介護者としての信友さんの話は、必聴ですね!
因みに、後半のパネルディスカッションでは
私が司会を務めさせていただきます。
場所が神戸なので、少し遠いですが、
美味しいものを食べに、観光も兼ねて、来られたらどうでしょうか。
英田南校区の安心声掛け訓練、
いよいよ来週の土曜日です。
全国津々浦々、どこにお住まいの方でも参加できます。
但し、交通費の支給はありません(笑)
但し但し、お昼ごはんのカレーは、無料でたっぷり食べれますよ!
それはともかく、声掛け訓練自体は
認知症の人を地域で温かく見守っていくためのもの。
自分力とお助け力で繋がっていきましょう!
もう一つは、映画「ぼけますから、よろしくお願いします」の
映画監督、信友直子さんの講演会です。
介護者としての信友さんの話は、必聴ですね!
因みに、後半のパネルディスカッションでは
私が司会を務めさせていただきます。
場所が神戸なので、少し遠いですが、
美味しいものを食べに、観光も兼ねて、来られたらどうでしょうか。

2024.06.10
心の荷物預かり所
2024.06.03
心の荷物預かり所
2024.05.08
心の荷物預かり所
2024.04.25
心の荷物預かり所
2024.04.03
心の荷物預かり所 朝の通勤時は色々なゲストの話をラジオで聞いています。
多様な職種の人の話を聞けるのは、知らない世界の話が一杯聞けて楽しいですね。
ラジオなので想像力をも働かせます。
今朝は、阪神タイガースの木浪選手のインタビューでした。
まぁ野球という、比較的皆さんが知っている世界の話ですが、
おもしろかったのは、8番バッターとしての木浪選手の心意気でした。
8番バッターというのは、野球の世界では、
レギュラー選手でも一番期待されていない打順の選手というイメージがあります。
しかし昨年の阪神タイガースで、最恐の8番バッターとして、
その存在の大きさを示した選手でした。
最強ではなく、最も恐れられる8番バッターとして君臨したのです。
その木浪選手、今年も8番バッターを希望したそうです。
普通なら昨年の活躍から、もっと早い打順も希望できるのにかかわらず。
木浪選手自体も最初は「8番バッターかぁ…」という残念な気持ちは当初あったそうです。
しかし8番バッターが何かと頑張る中で、得点や勝利に繋がっているということが見えてきて、
8番バッターの大切さがわかってきたとのことでした。
今は、「8番バッターのイメージを変えたい。8番バッターの存在感を示したい」と、
進んで希望しているとのこと。
さらに数値目標は?と聞かれたことに対して、
「日々の努力があれば、結果として数字がついてくるので、数値を目標にしているわけではない」とのこと。
まさしくその通りで、数字を気にしすぎると、その数字に縛られ、
毎日をプレッシャーの中で過ごすことになりかねないのです。
「8番バッターのこれまでのイメージを変えたい」 かっこいいですね!
決して3番や4番の選手のような主役ではないけれど、
このような8番バッターがいるからこそ、チームは強くなると、言えます。
誰もが4番バッターになるわけではないし、4番バッターだけで勝てるものではない。
でも誰かが8番バッターを頑張ることで、最強のチームとなる。
ケアの現場も同じかもですね。
リーダーだけが頑張っても強いチームにはなれないのです。
朝の通勤時は色々なゲストの話をラジオで聞いています。
多様な職種の人の話を聞けるのは、知らない世界の話が一杯聞けて楽しいですね。
ラジオなので想像力をも働かせます。
今朝は、阪神タイガースの木浪選手のインタビューでした。
まぁ野球という、比較的皆さんが知っている世界の話ですが、
おもしろかったのは、8番バッターとしての木浪選手の心意気でした。
8番バッターというのは、野球の世界では、
レギュラー選手でも一番期待されていない打順の選手というイメージがあります。
しかし昨年の阪神タイガースで、最恐の8番バッターとして、
その存在の大きさを示した選手でした。
最強ではなく、最も恐れられる8番バッターとして君臨したのです。
その木浪選手、今年も8番バッターを希望したそうです。
普通なら昨年の活躍から、もっと早い打順も希望できるのにかかわらず。
木浪選手自体も最初は「8番バッターかぁ…」という残念な気持ちは当初あったそうです。
しかし8番バッターが何かと頑張る中で、得点や勝利に繋がっているということが見えてきて、
8番バッターの大切さがわかってきたとのことでした。
今は、「8番バッターのイメージを変えたい。8番バッターの存在感を示したい」と、
進んで希望しているとのこと。
さらに数値目標は?と聞かれたことに対して、
「日々の努力があれば、結果として数字がついてくるので、数値を目標にしているわけではない」とのこと。
まさしくその通りで、数字を気にしすぎると、その数字に縛られ、
毎日をプレッシャーの中で過ごすことになりかねないのです。
「8番バッターのこれまでのイメージを変えたい」 かっこいいですね!
決して3番や4番の選手のような主役ではないけれど、
このような8番バッターがいるからこそ、チームは強くなると、言えます。
誰もが4番バッターになるわけではないし、4番バッターだけで勝てるものではない。
でも誰かが8番バッターを頑張ることで、最強のチームとなる。
ケアの現場も同じかもですね。
リーダーだけが頑張っても強いチームにはなれないのです。
