「心の荷物預かり所」で記事を検索しました。
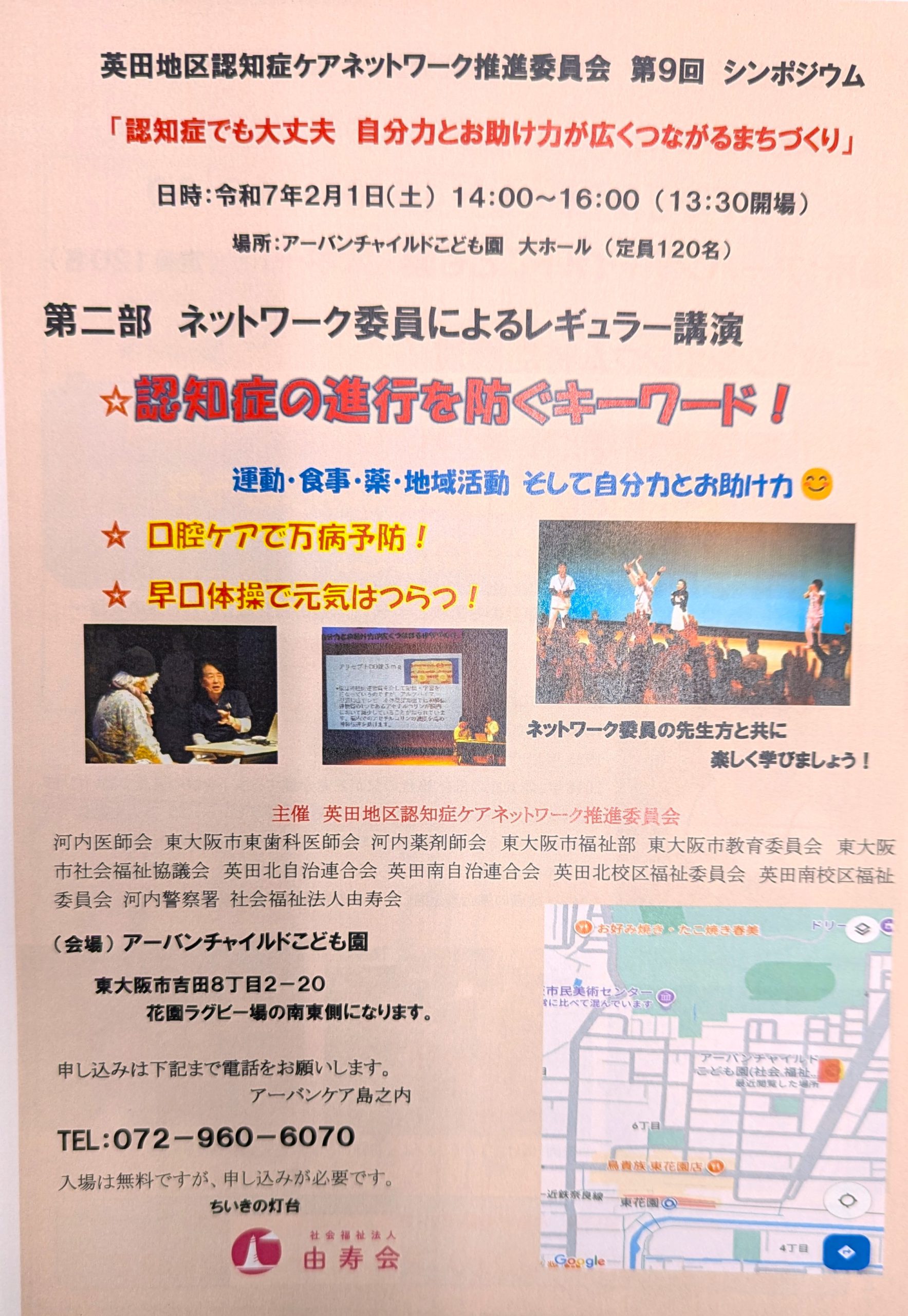
2025.01.06
心の荷物預かり所
2024.12.30
心の荷物預かり所
2024.12.24
心の荷物預かり所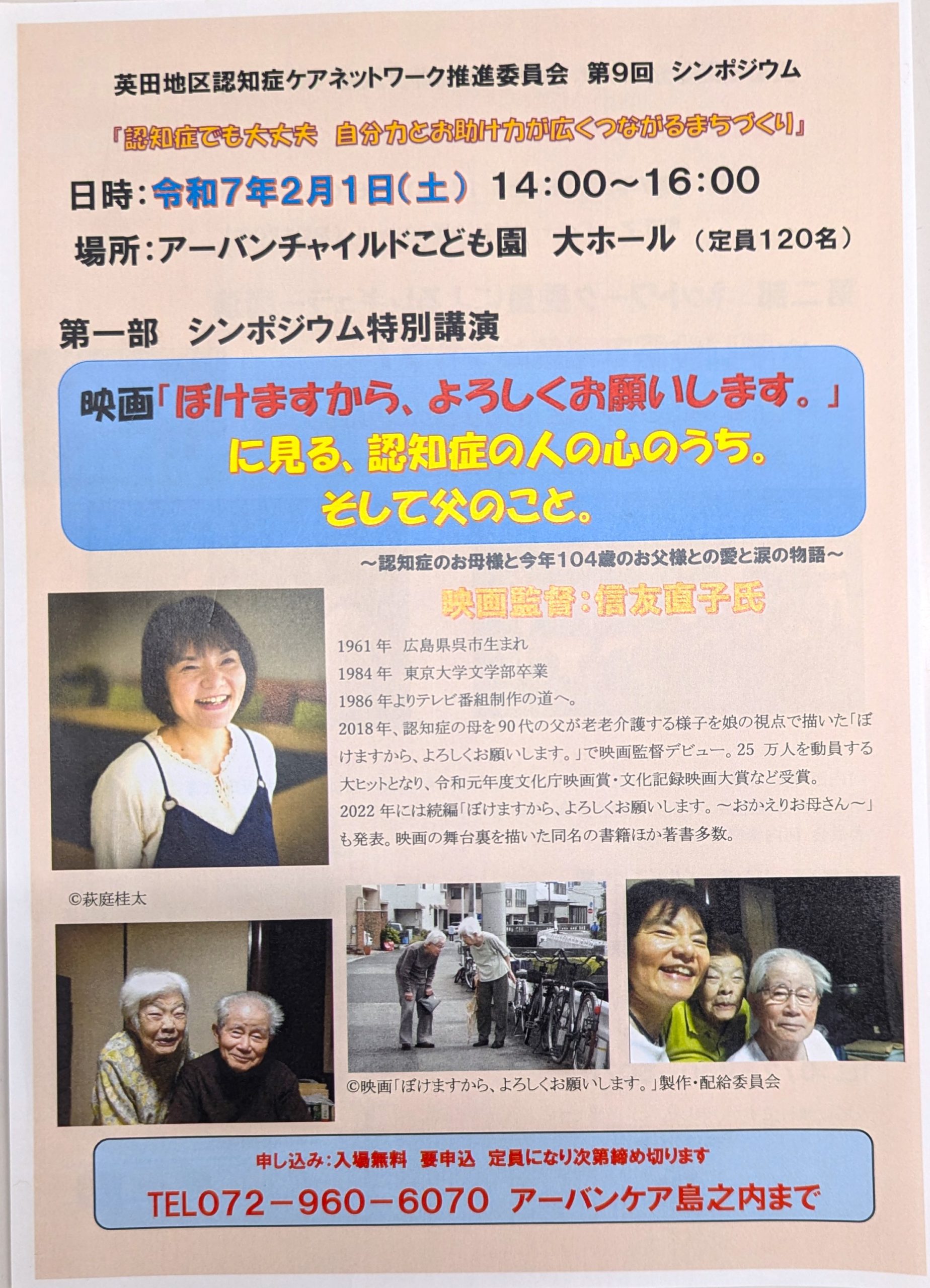
2024.12.23
心の荷物預かり所
2024.10.16
心の荷物預かり所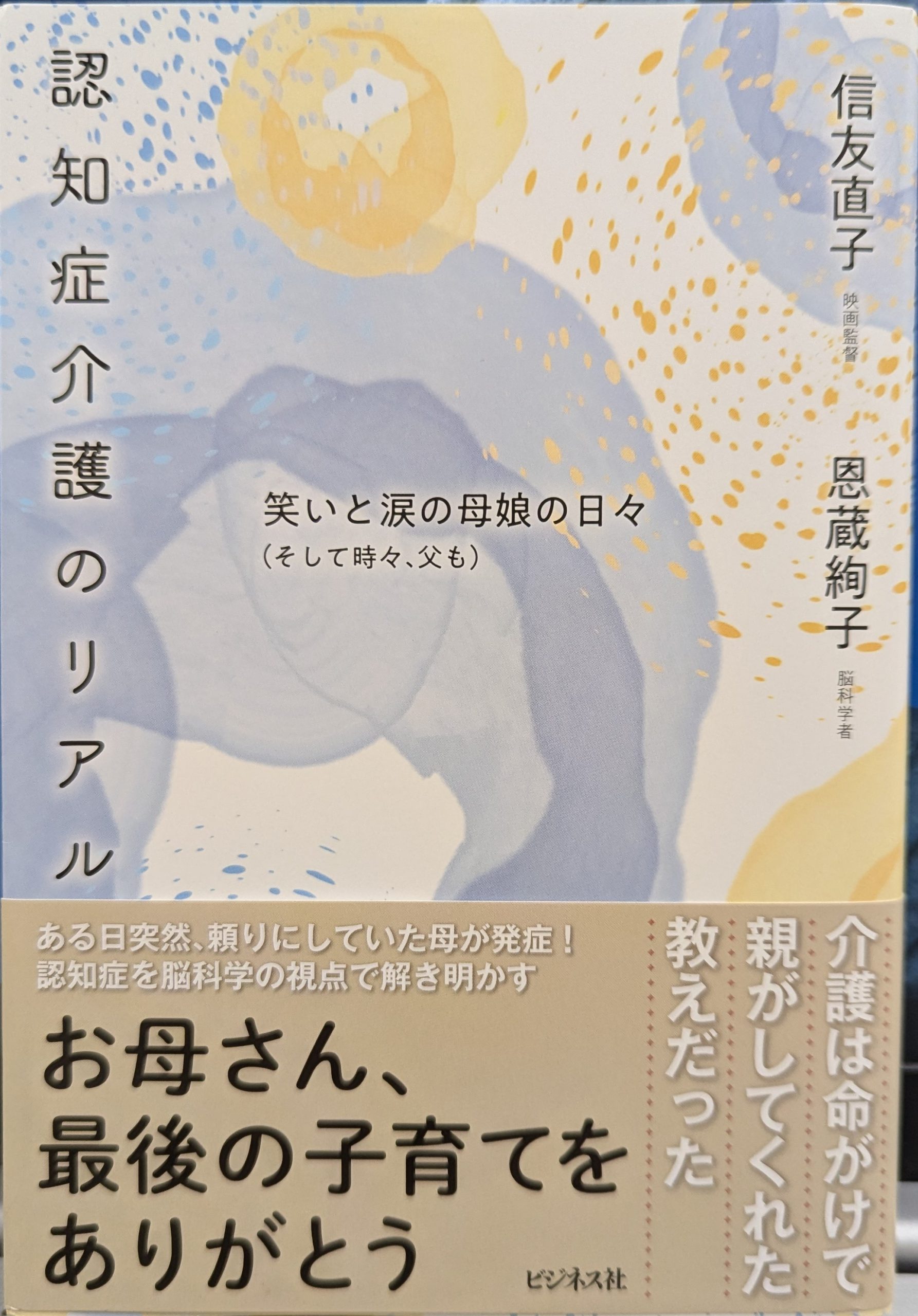
2024.09.24
心の荷物預かり所
2024.09.12
心の荷物預かり所
2024.09.04
心の荷物預かり所
2024.08.24
心の荷物預かり所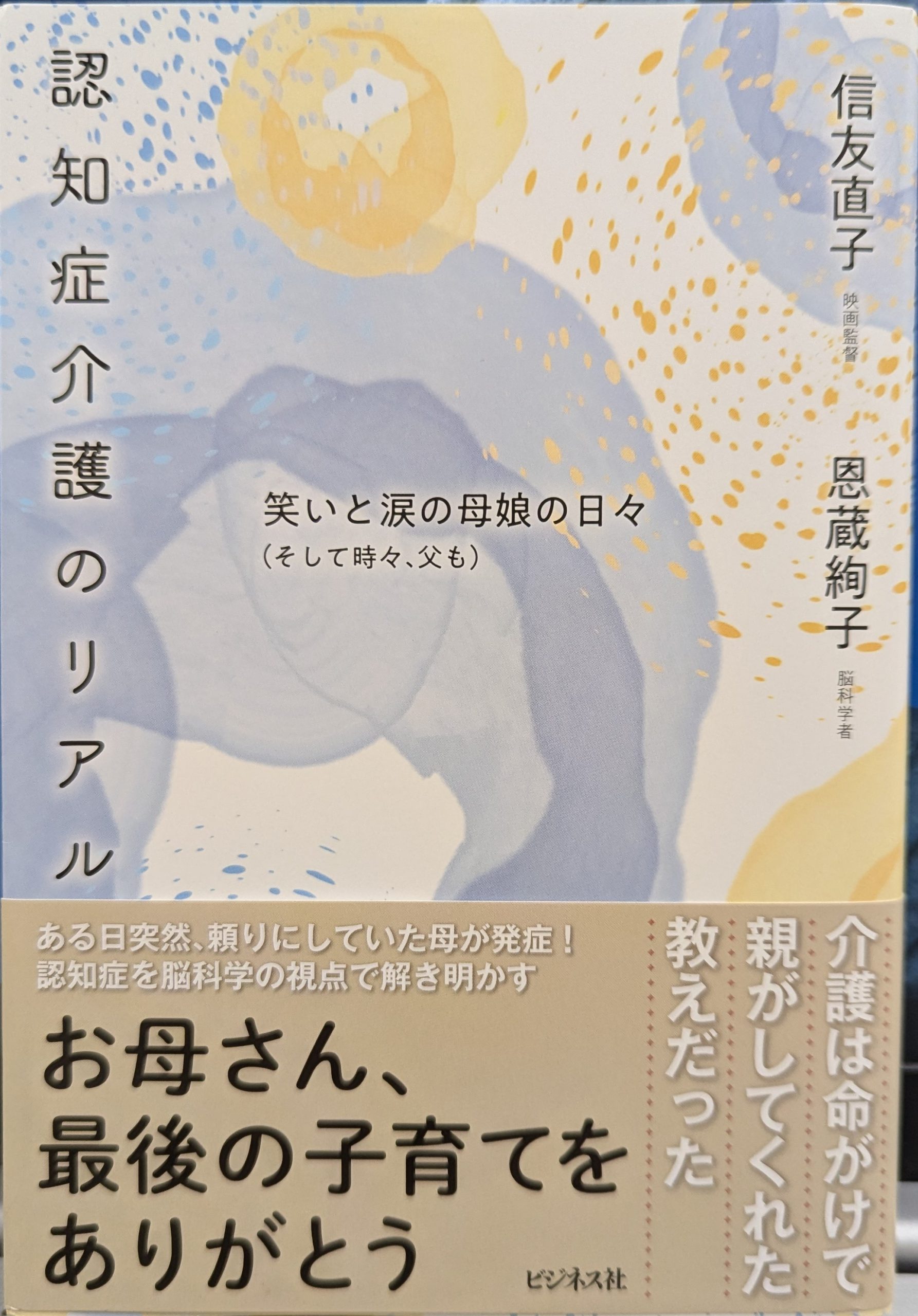
2024.08.16
心の荷物預かり所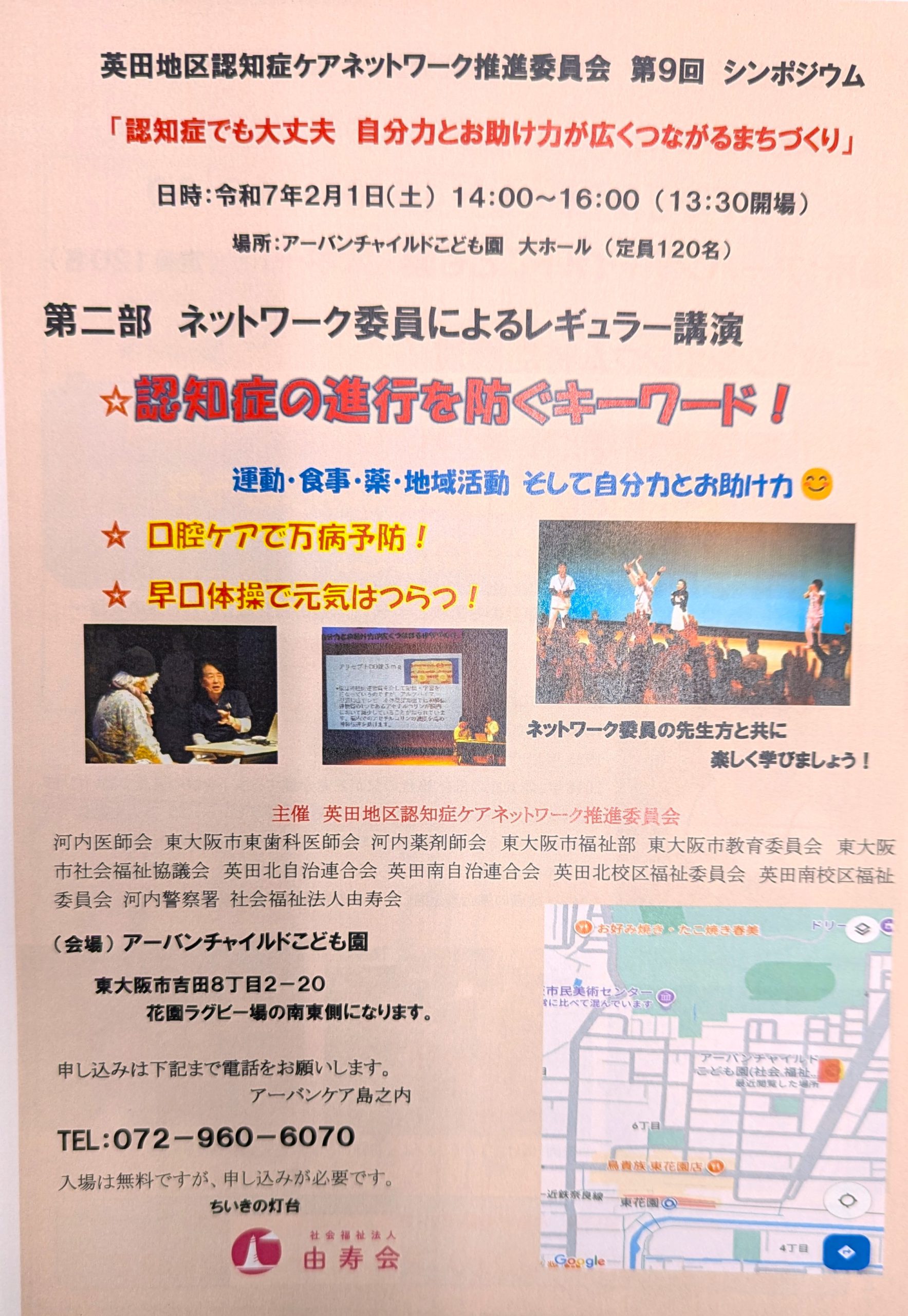
2025.01.06
心の荷物預かり所
2024.12.30
心の荷物預かり所
2024.12.24
心の荷物預かり所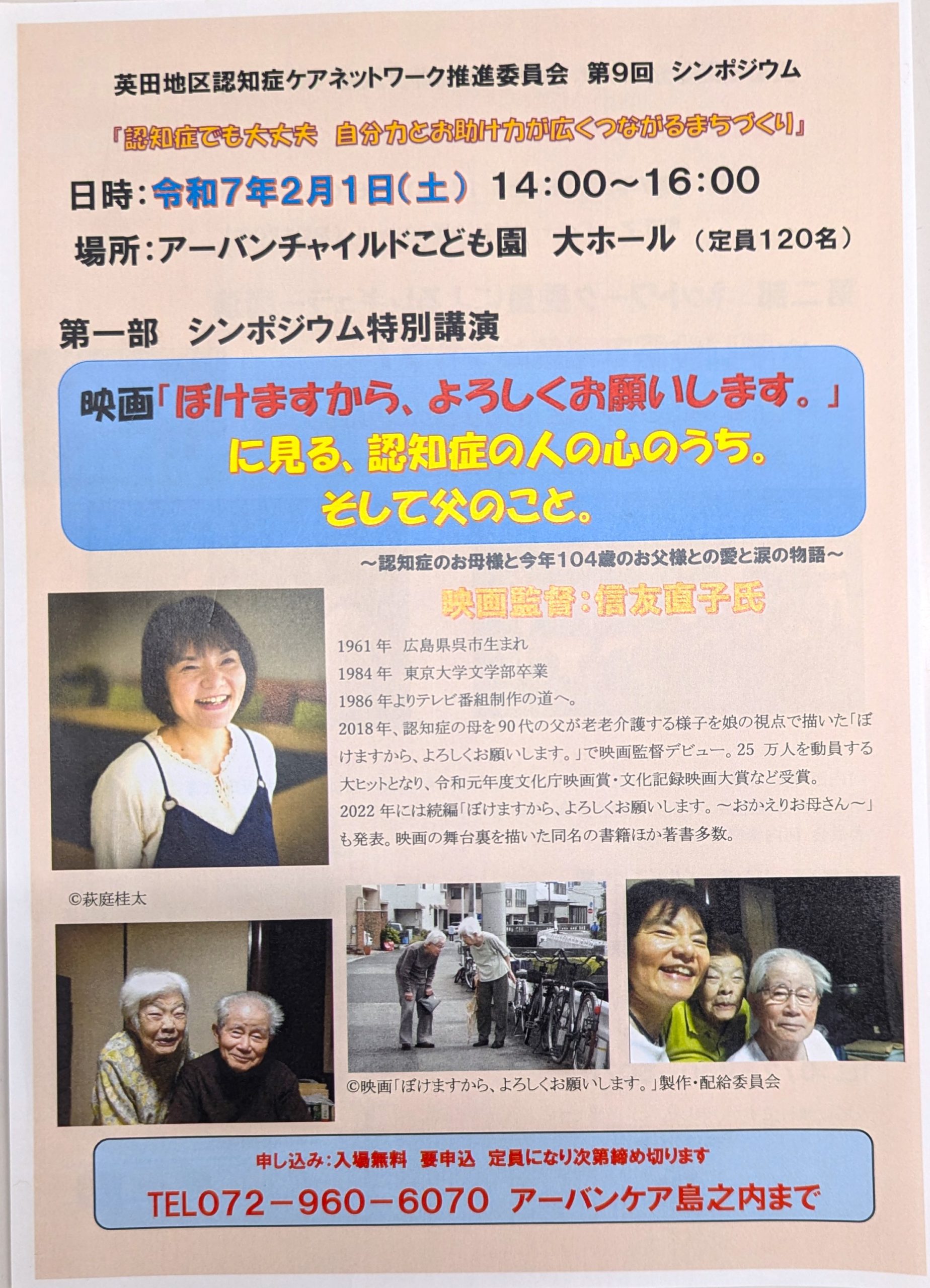
2024.12.23
心の荷物預かり所
2024.10.16
心の荷物預かり所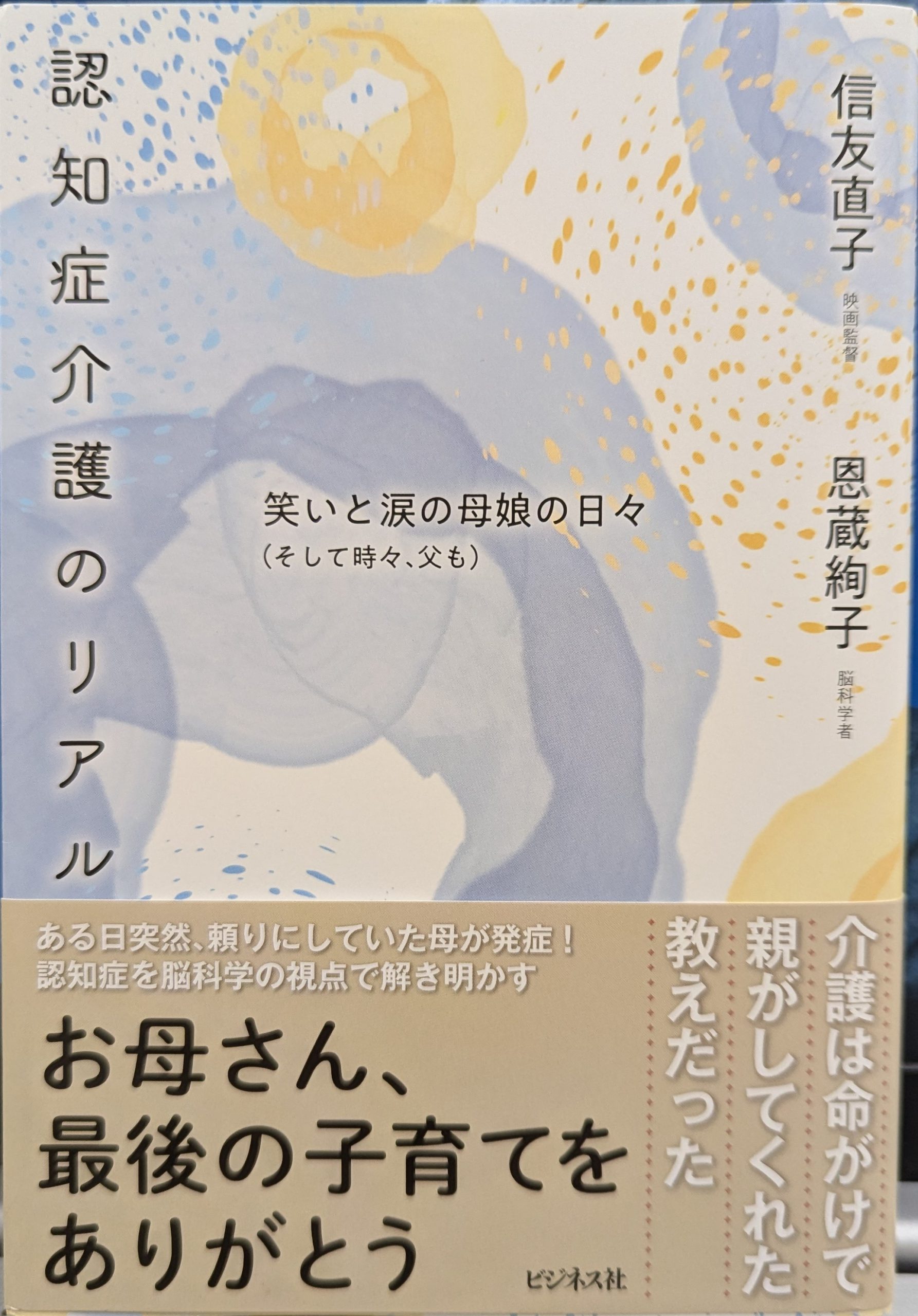
2024.09.24
心の荷物預かり所
2024.09.12
心の荷物預かり所
2024.09.04
心の荷物預かり所
2024.08.24
心の荷物預かり所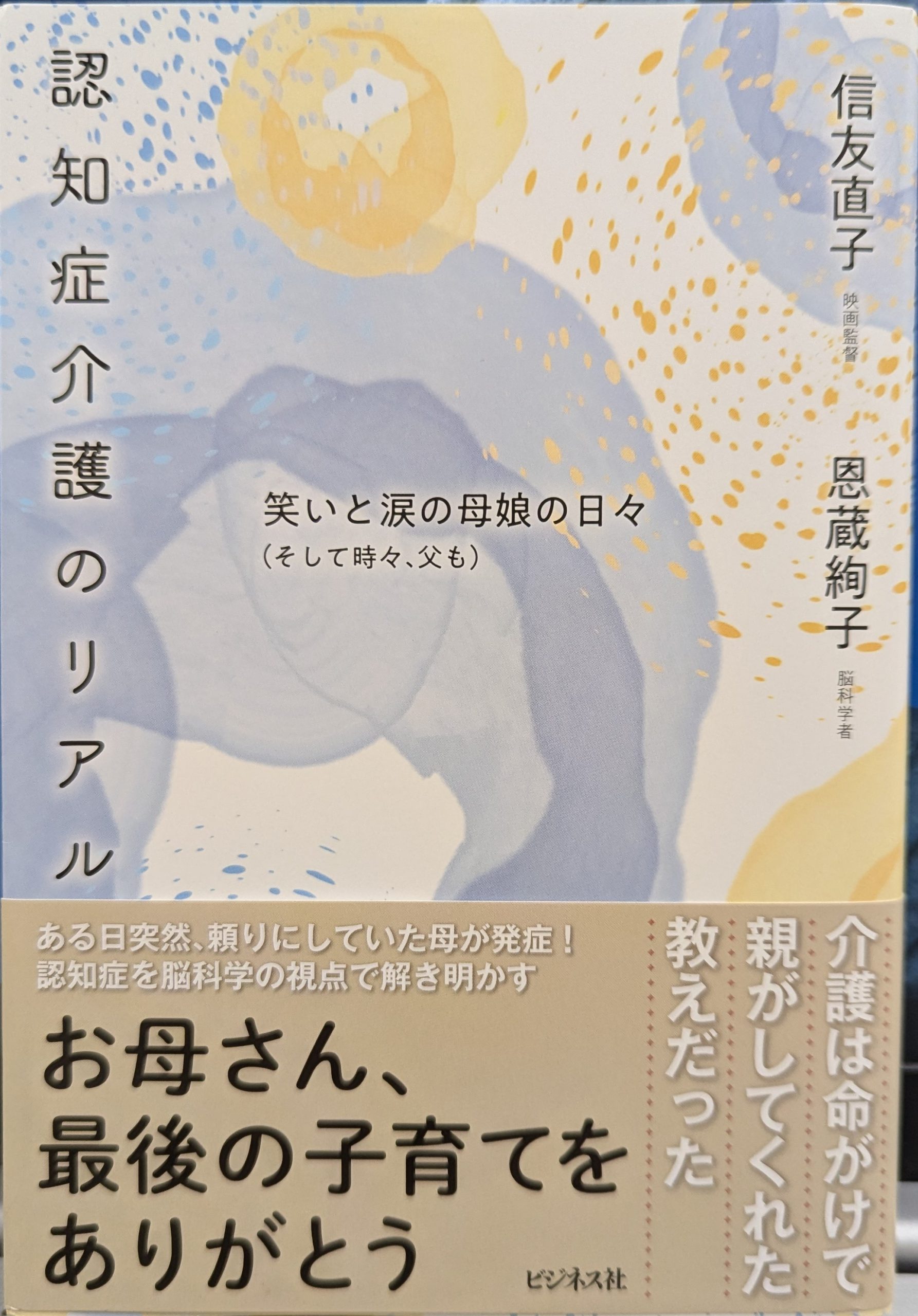
2024.08.16
心の荷物預かり所