「トピックス」で記事を検索しました。

2020.12.22
トピックス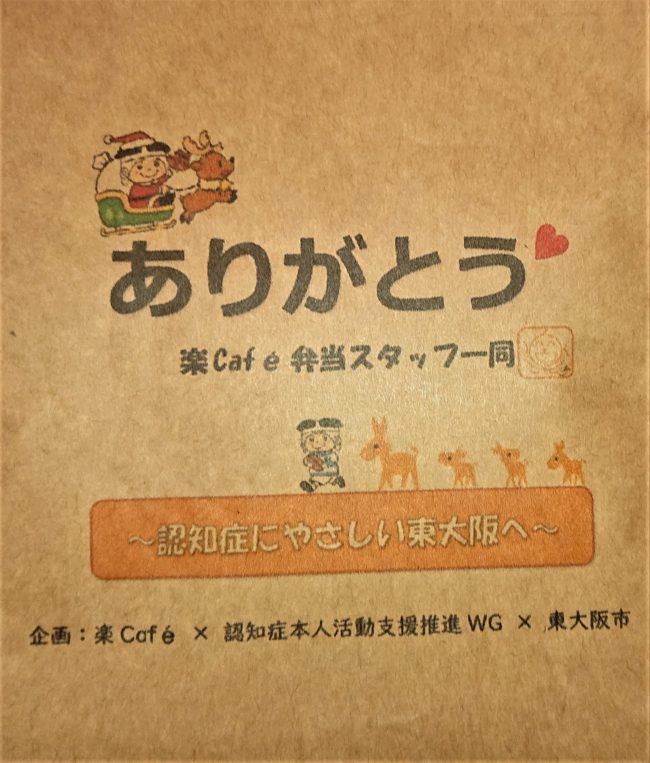
2020.12.21
トピックス
2020.12.18
トピックス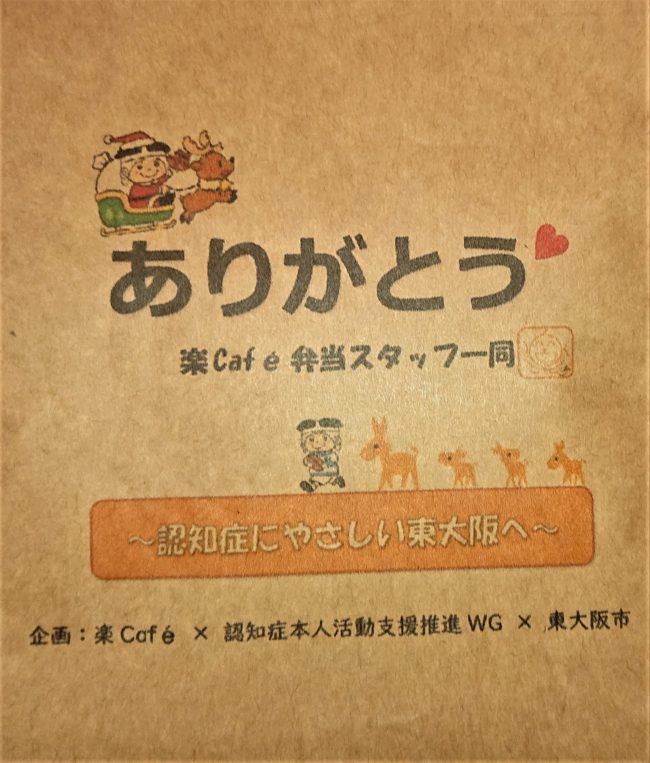
2020.12.17
トピックス
2020.12.15
トピックス
2020.12.12
トピックス
2020.12.11
トピックス
2020.12.09
トピックス
2020.12.08
トピックス
2020.12.07
トピックス
2020.12.22
トピックス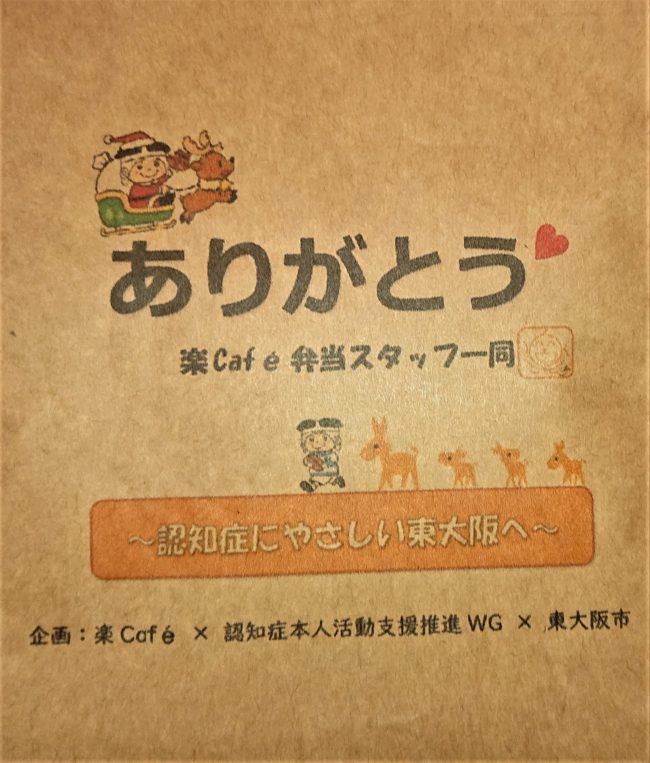 センター長の石川です。
「一生に一度」
昨年のラグビーワールドカップでのキャッチフレーズでした。
しかしその一生に一度のことが(そうありたい)世界的に起こってしまいましたね。
心が暗くなる一生に一度はいらないです。
もっとも生も死も一生に一度のことですが。
でも、だからこそその、一生に一度しかないその人(私たちのケアの対象の方)の人生の
エンディングを支える私たち介護職員は、凄く素晴らしい仕事に就いているのです。
自らの振り返りは大切ですが、この仕事に就いていることに
誇りを持つべきでしょう。
[caption id="attachment_2227" align="aligncenter" width="650"] 木星の衛星、木星側からエウロパ、イオ、ガニメデ、カリスト。土星の近くに土星の衛星タイタンが写っています。[/caption]
さて、宇宙規模で見ると、「一生に一度の出来事」と言うのは、ほとんどがそのような出来事と言えるでしょう。
今夕、木星と土星が超接近して見えます。
ふたつの惑星が近づくという訳ではなく、見た目の超接近になるのですが、
何とこれだけの接近は397年ぶりになるそうです。
徳川将軍家光の時代以来と言うことになります。
次回は60年後とのことですから、まさしく「一生に一度」ですね。
肉眼で見ると、一つの星に見えるかもしれませんし、二つ見えるかもしれません。
それは今夕のお楽しみ。
でも、6時過ぎにはかなり低い位置になるので、日没後すぐに見るのがいいでしょう。
[caption id="attachment_2226" align="aligncenter" width="650"] 昨夕の撮影です。土星は輪っかがあるので、少し楕円に写っています。[/caption]
さて、話題が変わり、
先日の楽Cafeメンバーの活躍が産経新聞に掲載されました。
下記をクリックすれば読めますのでご確認ください。
20201218産経(河内版)朝刊(楽Cafe弁当)
センター長の石川です。
「一生に一度」
昨年のラグビーワールドカップでのキャッチフレーズでした。
しかしその一生に一度のことが(そうありたい)世界的に起こってしまいましたね。
心が暗くなる一生に一度はいらないです。
もっとも生も死も一生に一度のことですが。
でも、だからこそその、一生に一度しかないその人(私たちのケアの対象の方)の人生の
エンディングを支える私たち介護職員は、凄く素晴らしい仕事に就いているのです。
自らの振り返りは大切ですが、この仕事に就いていることに
誇りを持つべきでしょう。
[caption id="attachment_2227" align="aligncenter" width="650"] 木星の衛星、木星側からエウロパ、イオ、ガニメデ、カリスト。土星の近くに土星の衛星タイタンが写っています。[/caption]
さて、宇宙規模で見ると、「一生に一度の出来事」と言うのは、ほとんどがそのような出来事と言えるでしょう。
今夕、木星と土星が超接近して見えます。
ふたつの惑星が近づくという訳ではなく、見た目の超接近になるのですが、
何とこれだけの接近は397年ぶりになるそうです。
徳川将軍家光の時代以来と言うことになります。
次回は60年後とのことですから、まさしく「一生に一度」ですね。
肉眼で見ると、一つの星に見えるかもしれませんし、二つ見えるかもしれません。
それは今夕のお楽しみ。
でも、6時過ぎにはかなり低い位置になるので、日没後すぐに見るのがいいでしょう。
[caption id="attachment_2226" align="aligncenter" width="650"] 昨夕の撮影です。土星は輪っかがあるので、少し楕円に写っています。[/caption]
さて、話題が変わり、
先日の楽Cafeメンバーの活躍が産経新聞に掲載されました。
下記をクリックすれば読めますのでご確認ください。
20201218産経(河内版)朝刊(楽Cafe弁当)

2020.12.18
トピックス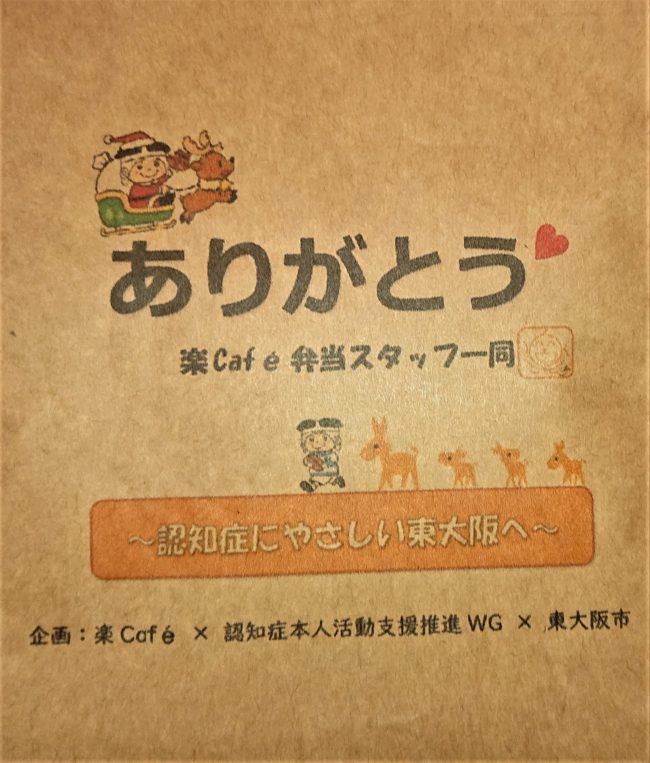
2020.12.17
トピックス
2020.12.15
トピックス
2020.12.12
トピックス
2020.12.11
トピックス
2020.12.09
トピックス
2020.12.08
トピックス
2020.12.07
トピックス