「トピックス」で記事を検索しました。

2021.02.26
トピックス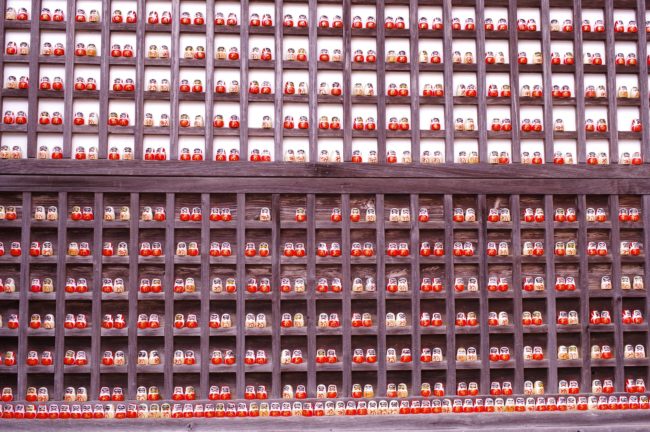
2021.02.22
トピックス
2021.02.20
トピックス
2021.02.17
トピックス
2021.02.15
トピックス
2021.02.11
トピックス
2021.02.08
トピックス
2021.02.05
トピックス
2021.02.04
トピックス
2021.02.02
トピックス センター長の石川です。
昨日のことですが、3月22日に英田北小学校4年生向け「キッズサポーター講座」の打ち合わせに行った時のことです。
何と5年生担当の先生方全員が出てきてくれて、
1月29日に5年生向けに行った「キッズサポーター講座」の御礼とともに
5年生全員が書いてくれた感想文をいただきました。
分厚い冊子には、一人ひとりの児童たちが感じたことが一杯書かれて綴られていました。
何と嬉しいことでしょうか!
相談するなら地域包括支援センター、デイサービスはアーバンケアと書いてくれた児童も複数いて、
地域に根差し、世代を越えて繋がっていくことの大切さを痛感しました。
また今回からは、認知症は高齢者だけでなく、
児童たちのお父さんやお母さんの年齢からもなってしまう人がいることを伝えたところ、
そのこともしっかりと書かれ、児童たちの関心の高さに驚きました。
全ての文章を載せることはできませんが、いくつか紹介させていただいてます。
裏表紙の「つなごう、オレンジリング」という言葉での締めくくりもいいですね。先生方にも感謝です。
ありがとうございました!
センター長の石川です。
昨日のことですが、3月22日に英田北小学校4年生向け「キッズサポーター講座」の打ち合わせに行った時のことです。
何と5年生担当の先生方全員が出てきてくれて、
1月29日に5年生向けに行った「キッズサポーター講座」の御礼とともに
5年生全員が書いてくれた感想文をいただきました。
分厚い冊子には、一人ひとりの児童たちが感じたことが一杯書かれて綴られていました。
何と嬉しいことでしょうか!
相談するなら地域包括支援センター、デイサービスはアーバンケアと書いてくれた児童も複数いて、
地域に根差し、世代を越えて繋がっていくことの大切さを痛感しました。
また今回からは、認知症は高齢者だけでなく、
児童たちのお父さんやお母さんの年齢からもなってしまう人がいることを伝えたところ、
そのこともしっかりと書かれ、児童たちの関心の高さに驚きました。
全ての文章を載せることはできませんが、いくつか紹介させていただいてます。
裏表紙の「つなごう、オレンジリング」という言葉での締めくくりもいいですね。先生方にも感謝です。
ありがとうございました!
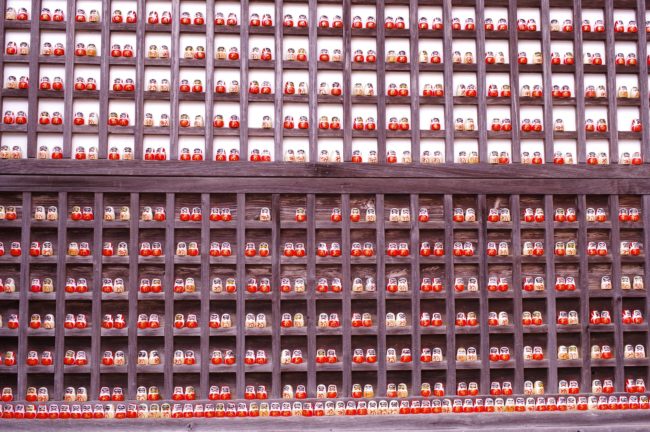
2021.02.22
トピックス センター長の石川です。
昨年の2月20日は、藤川幸之助氏の講演会があった日です。
未知のコロナウイルスの恐怖に怯え、世間が大騒ぎになり始めた時でした。
[caption id="attachment_2386" align="aligncenter" width="650"] 藤川幸之助氏講演会「支える側が支えられるとき」[/caption]
講演会自体実施の有無が問われるほどの、ぎりぎりの状況での開催でした。
消毒、そして参加者は全員マスク。
今なら当たり前の景色も、当時はみんながマスクをしているのが異様に思えた時期でした。
[caption id="attachment_2384" align="aligncenter" width="650"] まだおおらかな日でした[/caption]
そして心に残る藤川先生の講演は、
これからもあの日を境に… と、印象に残る講演会となりました。
思えば、たくさんの人が集まって心が和む話を聞けるのは、
今日時点において、この日が最後となりました。
[caption id="attachment_2387" align="aligncenter" width="650"] 和やかな雰囲気もこの日以降途絶えています[/caption]
翌21日から、行事と言う行事は一斉に禁止。
そして面会もできない、鎖国状態と施設はなったのです。
まさかこんな状況が一年も続くとは、この時は誰も思わなかったでしょう。
それどころか、この時よりもはるかに感染者を多く出す第3波に襲われたのですから。
丸々一年間、面会できていないご家族の方も多くおられます。
本当に切ない、もどかしい日々だと思います。
職員も、つらく、長く、耐えることと、感染の恐怖に不安になる日々
「でした」と書きたいところですが、まだまだその日々は続きます。
[caption id="attachment_1584" align="aligncenter" width="297"] ベランダ面会。話は携帯電話で行いました。[/caption]
ワクチンも恐らくはかなり遅れるのではないでしょうか。
少なくても、あと半年、試練の日々が続くかもしれません。
今は耐え抜いていきましょう!
トンネルの先の光は見えてきました。
まだ遠くにですが、でも着実にその光は大きくなっていきます。
センター長の石川です。
昨年の2月20日は、藤川幸之助氏の講演会があった日です。
未知のコロナウイルスの恐怖に怯え、世間が大騒ぎになり始めた時でした。
[caption id="attachment_2386" align="aligncenter" width="650"] 藤川幸之助氏講演会「支える側が支えられるとき」[/caption]
講演会自体実施の有無が問われるほどの、ぎりぎりの状況での開催でした。
消毒、そして参加者は全員マスク。
今なら当たり前の景色も、当時はみんながマスクをしているのが異様に思えた時期でした。
[caption id="attachment_2384" align="aligncenter" width="650"] まだおおらかな日でした[/caption]
そして心に残る藤川先生の講演は、
これからもあの日を境に… と、印象に残る講演会となりました。
思えば、たくさんの人が集まって心が和む話を聞けるのは、
今日時点において、この日が最後となりました。
[caption id="attachment_2387" align="aligncenter" width="650"] 和やかな雰囲気もこの日以降途絶えています[/caption]
翌21日から、行事と言う行事は一斉に禁止。
そして面会もできない、鎖国状態と施設はなったのです。
まさかこんな状況が一年も続くとは、この時は誰も思わなかったでしょう。
それどころか、この時よりもはるかに感染者を多く出す第3波に襲われたのですから。
丸々一年間、面会できていないご家族の方も多くおられます。
本当に切ない、もどかしい日々だと思います。
職員も、つらく、長く、耐えることと、感染の恐怖に不安になる日々
「でした」と書きたいところですが、まだまだその日々は続きます。
[caption id="attachment_1584" align="aligncenter" width="297"] ベランダ面会。話は携帯電話で行いました。[/caption]
ワクチンも恐らくはかなり遅れるのではないでしょうか。
少なくても、あと半年、試練の日々が続くかもしれません。
今は耐え抜いていきましょう!
トンネルの先の光は見えてきました。
まだ遠くにですが、でも着実にその光は大きくなっていきます。

2021.02.17
トピックス
2021.02.15
トピックス
2021.02.11
トピックス
2021.02.08
トピックス
2021.02.05
トピックス
2021.02.04
トピックス
2021.02.02
トピックス