「必見!最新情報」で記事を検索しました。

2021.06.16
必見!最新情報
2021.06.12
必見!最新情報
2021.06.10
必見!最新情報
2021.06.08
必見!最新情報
2021.05.27
必見!最新情報
2021.05.20
必見!最新情報
2021.05.08
必見!最新情報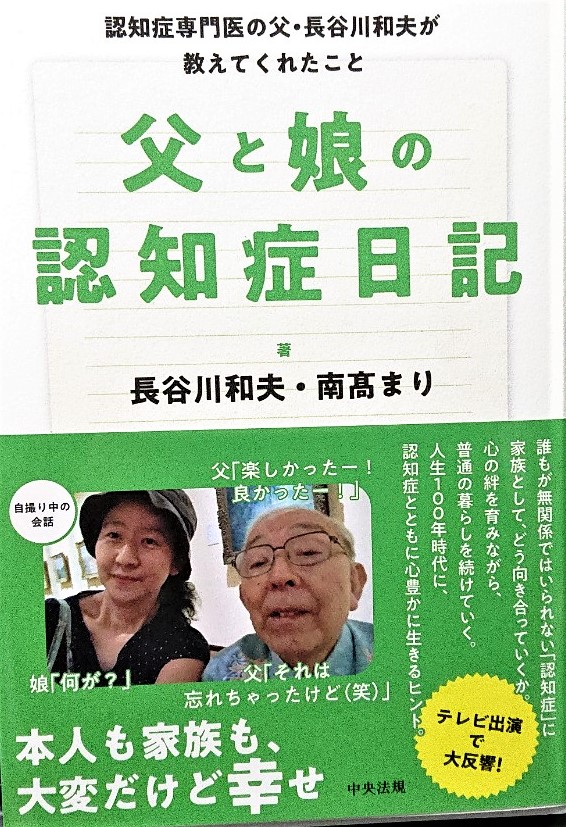
2021.05.06
必見!最新情報
2021.05.04
必見!最新情報
2021.06.16
必見!最新情報 センター長の石川です。
グーグルにタイムラインと言う機能があり、
毎月の訪問先を振り返られるようになっています。
それを見ると私の行動範囲がわかるのですが、
仕事で東大阪に来ている以外、見事に4月5月ともに北摂から出ることはありませんでした。
アウトドアや遠征が大好きなのに、大阪市内にも一歩も入らず、
北摂でじっと我慢していたことになります。
星空撮影に最適な奈良の山奥(鹿しかいない)に行くのも我慢してました。
行先で挙げられていたのも、池田市文化会館(ワクチン接種のため)と、
箕面のお酒のディスカウント店だけでした。
さて、そんな北摂でも、能勢に行くと、ここは大阪なのか?と思うほどめっちゃ田舎になります。
そして、乱舞まではいかない、蛍街まではいかないけれど、
蛍村ほどのホタルたちには出会うことが出来ました。
「大阪でも」こんなに蛍がいるところがあるんやと思うと、なんか凄いなと思いますね。
星空撮影に行けない分、蛍の光撮影を楽しませてもらいました。
残念ながら大阪は田舎であっても、奈良のような鹿しかいないほどの山奥ではないので、
蛍は撮影出来ても星空は撮影できません。
しかし、田舎はいいですね。蛍はいても、人はいない。(休日前や休日は人が多いかも)
でも鹿や蛇には気を付けないと。
何かと制限の多い時期ですが、少し工夫して田舎の風景を見に行くのも
いいかもしれません。
センター長の石川です。
グーグルにタイムラインと言う機能があり、
毎月の訪問先を振り返られるようになっています。
それを見ると私の行動範囲がわかるのですが、
仕事で東大阪に来ている以外、見事に4月5月ともに北摂から出ることはありませんでした。
アウトドアや遠征が大好きなのに、大阪市内にも一歩も入らず、
北摂でじっと我慢していたことになります。
星空撮影に最適な奈良の山奥(鹿しかいない)に行くのも我慢してました。
行先で挙げられていたのも、池田市文化会館(ワクチン接種のため)と、
箕面のお酒のディスカウント店だけでした。
さて、そんな北摂でも、能勢に行くと、ここは大阪なのか?と思うほどめっちゃ田舎になります。
そして、乱舞まではいかない、蛍街まではいかないけれど、
蛍村ほどのホタルたちには出会うことが出来ました。
「大阪でも」こんなに蛍がいるところがあるんやと思うと、なんか凄いなと思いますね。
星空撮影に行けない分、蛍の光撮影を楽しませてもらいました。
残念ながら大阪は田舎であっても、奈良のような鹿しかいないほどの山奥ではないので、
蛍は撮影出来ても星空は撮影できません。
しかし、田舎はいいですね。蛍はいても、人はいない。(休日前や休日は人が多いかも)
でも鹿や蛇には気を付けないと。
何かと制限の多い時期ですが、少し工夫して田舎の風景を見に行くのも
いいかもしれません。

2021.06.10
必見!最新情報
2021.06.08
必見!最新情報
2021.06.05
必見!最新情報
2021.05.27
必見!最新情報
2021.05.20
必見!最新情報
2021.05.08
必見!最新情報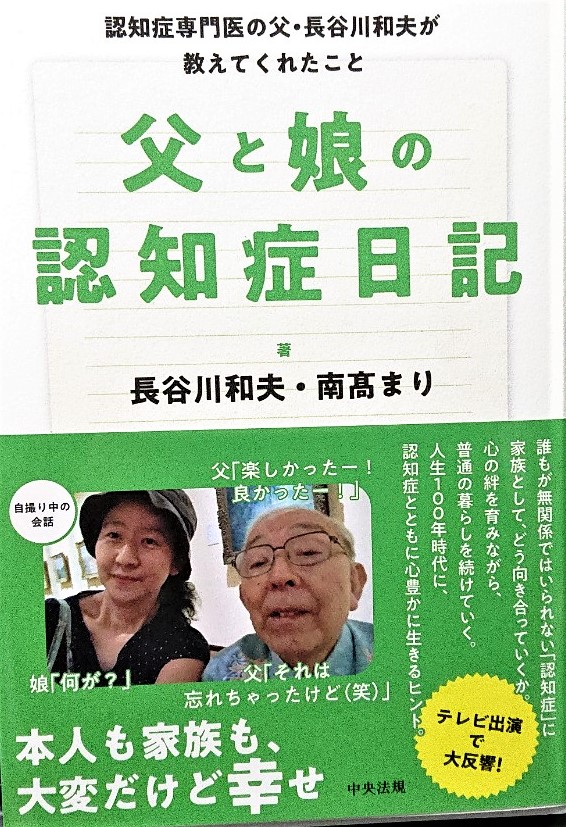
2021.05.06
必見!最新情報
2021.05.04
必見!最新情報