「認知症の教室(専門職用)」で記事を検索しました。
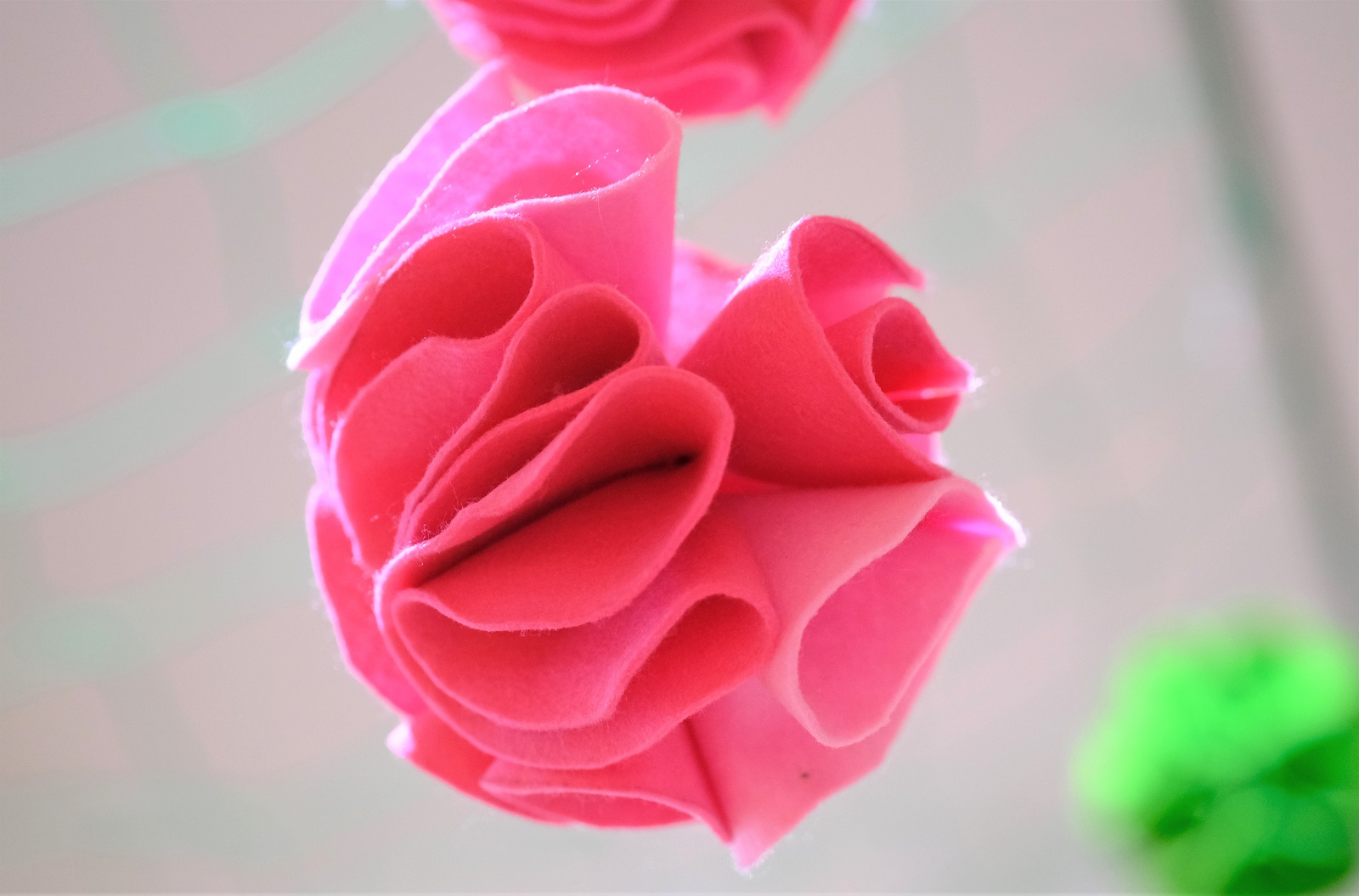
2021.12.22
認知症の教室(専門職用)
2021.12.17
認知症の教室(専門職用)
2021.12.16
認知症の教室(専門職用)
2021.12.11
認知症の教室(専門職用)
2021.12.09
認知症の教室(専門職用)
2021.12.04
認知症の教室(専門職用)
2021.12.01
認知症の教室(専門職用)
2021.11.30
認知症の教室(専門職用)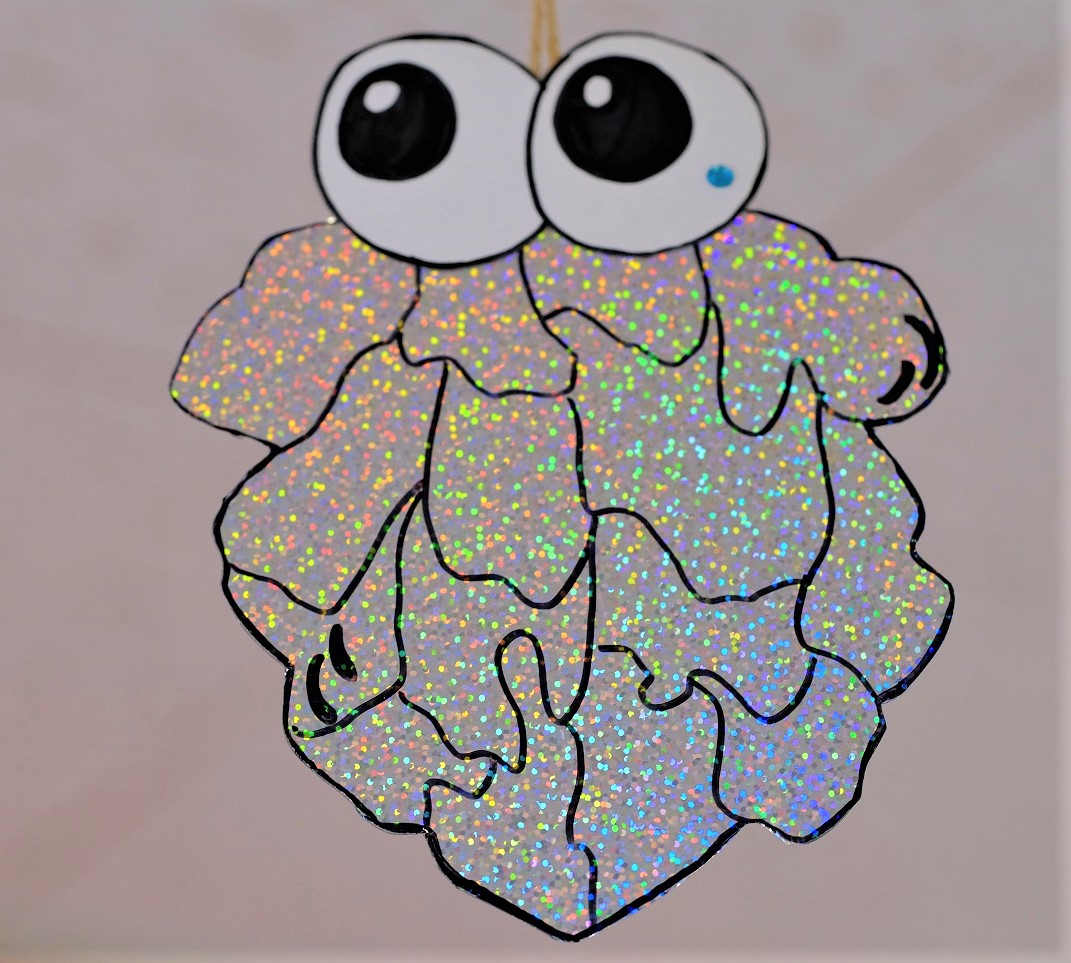
2021.11.27
認知症の教室(専門職用)
2021.11.25
認知症の教室(専門職用)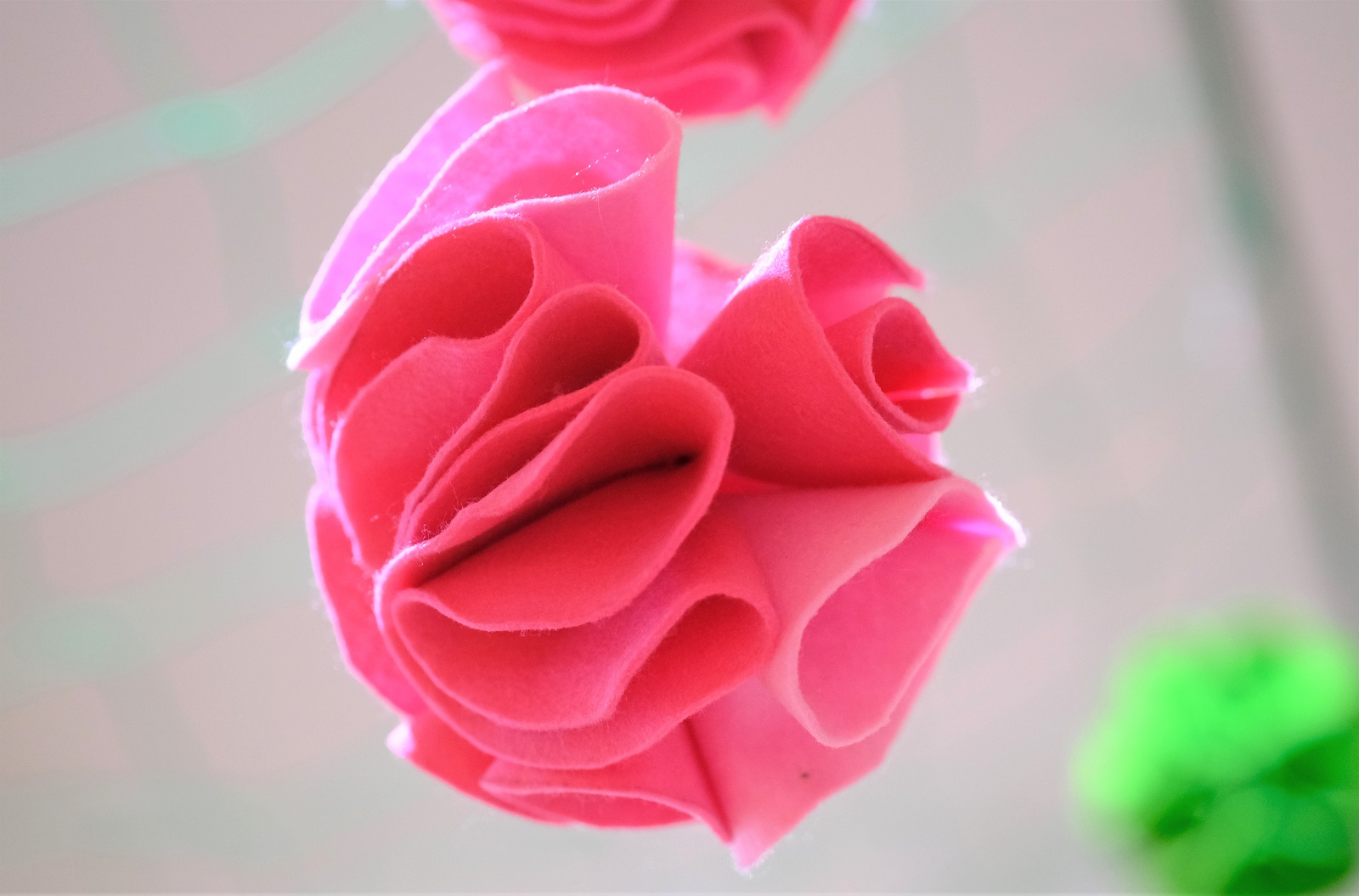
2021.12.22
認知症の教室(専門職用)
2021.12.17
認知症の教室(専門職用)
2021.12.16
認知症の教室(専門職用)
2021.12.11
認知症の教室(専門職用)
2021.12.09
認知症の教室(専門職用)
2021.12.04
認知症の教室(専門職用)
2021.12.01
認知症の教室(専門職用)
2021.11.30
認知症の教室(専門職用)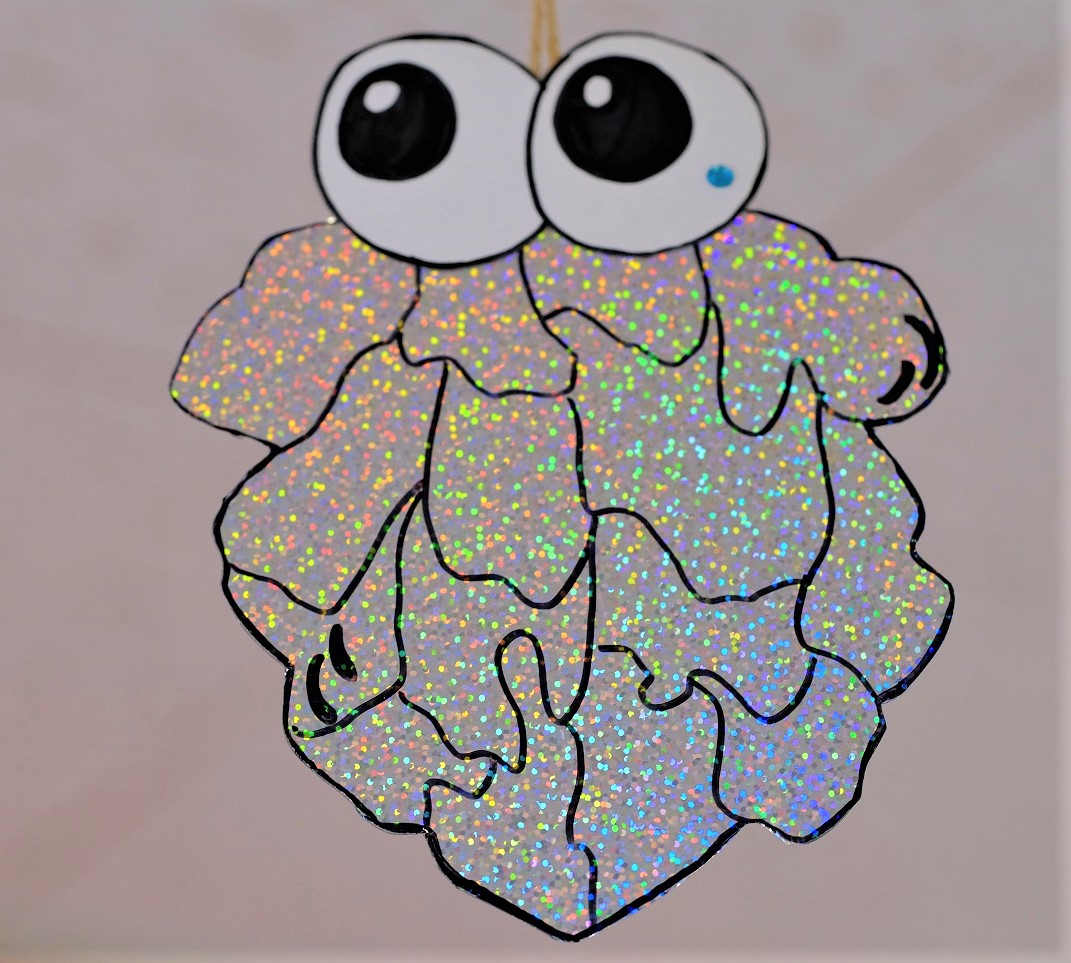
2021.11.27
認知症の教室(専門職用)
2021.11.25
認知症の教室(専門職用)