「認知症の教室(専門職用)」で記事を検索しました。

2020.11.25
認知症の教室(専門職用)
2020.11.20
認知症の教室(専門職用)
2020.11.09
認知症の教室(専門職用)
2020.10.28
認知症の教室(専門職用)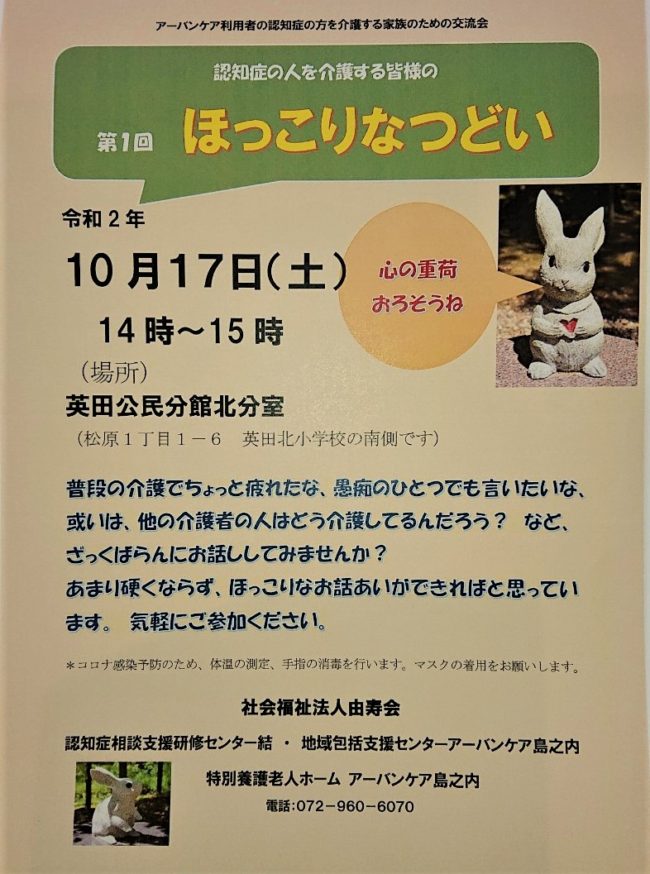
2020.10.17
認知症の教室(専門職用)
2020.10.13
認知症の教室(専門職用)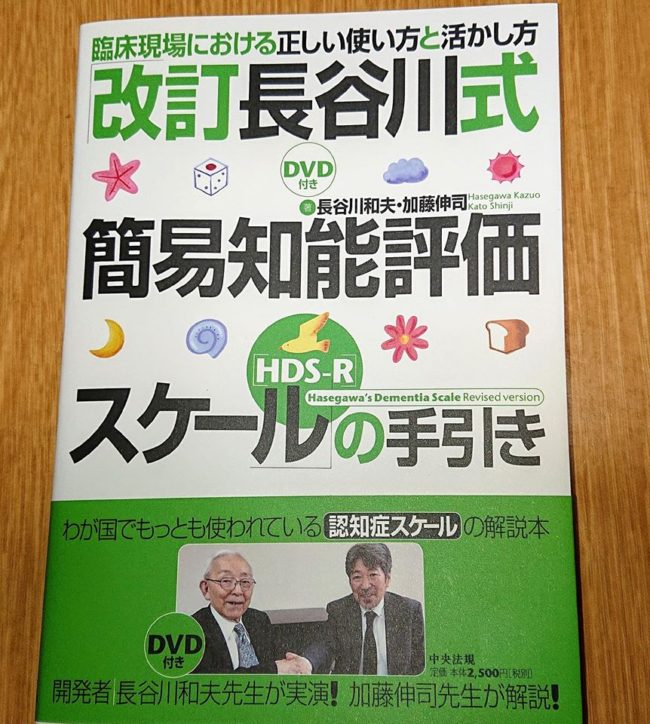
2020.10.08
認知症の教室(専門職用)
2020.09.30
認知症の教室(専門職用)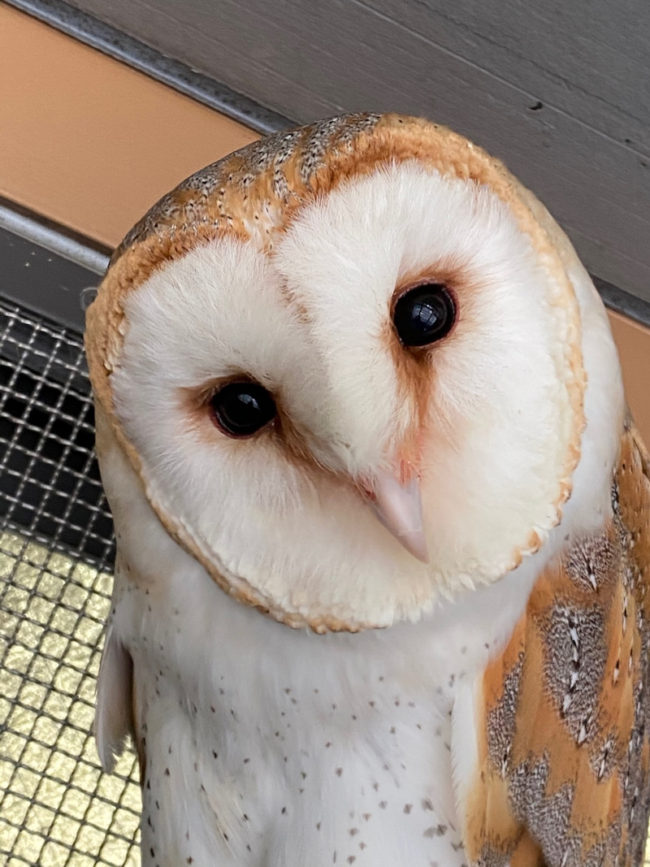
2020.09.24
認知症の教室(専門職用)
2020.11.25
認知症の教室(専門職用)
2020.11.20
認知症の教室(専門職用)
2020.11.09
認知症の教室(専門職用)
2020.10.28
認知症の教室(専門職用)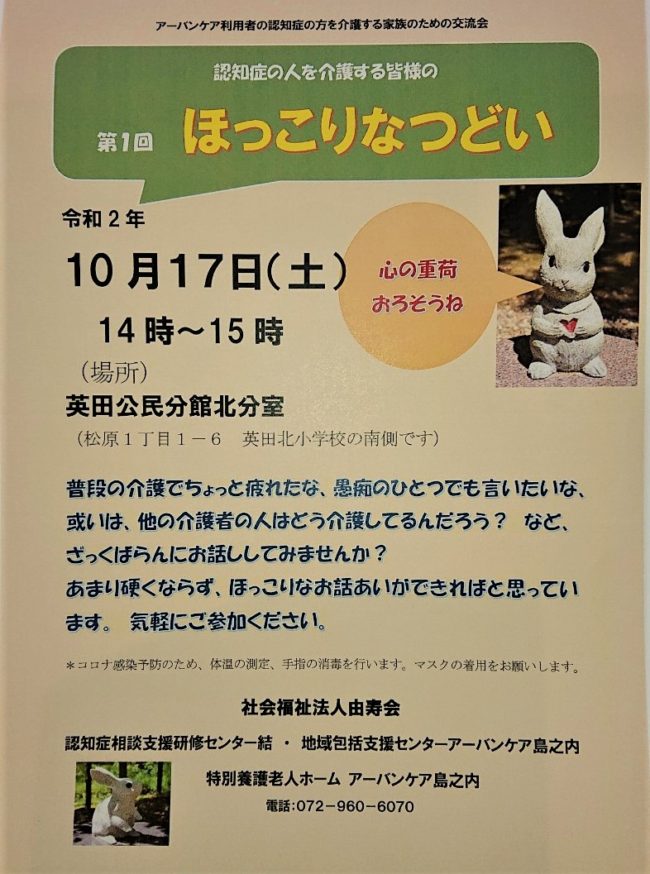
2020.10.17
認知症の教室(専門職用)
2020.10.13
認知症の教室(専門職用)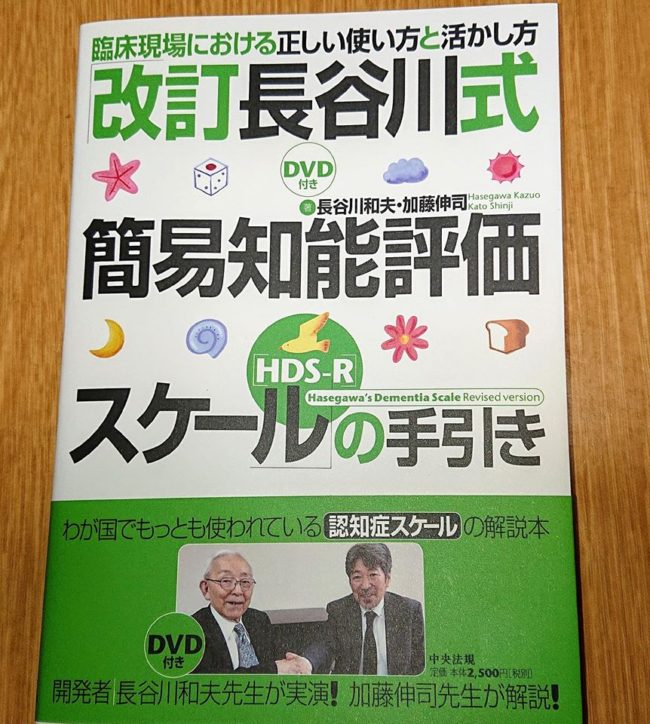
2020.10.08
認知症の教室(専門職用)
2020.09.30
認知症の教室(専門職用)
2020.09.26
認知症の教室(専門職用)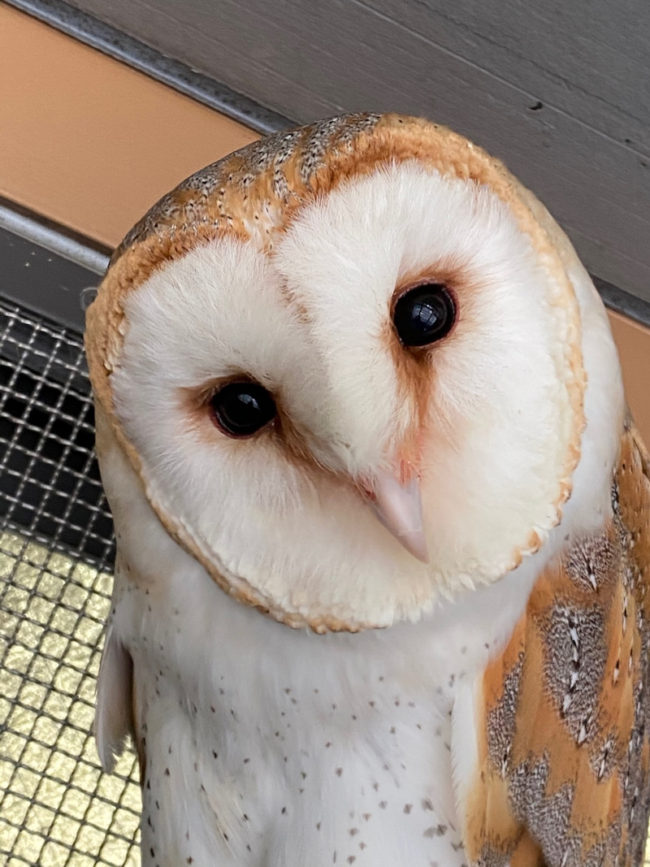
2020.09.24
認知症の教室(専門職用)