「ほんわか写真館」で記事を検索しました。

2024.08.24
ほんわか写真館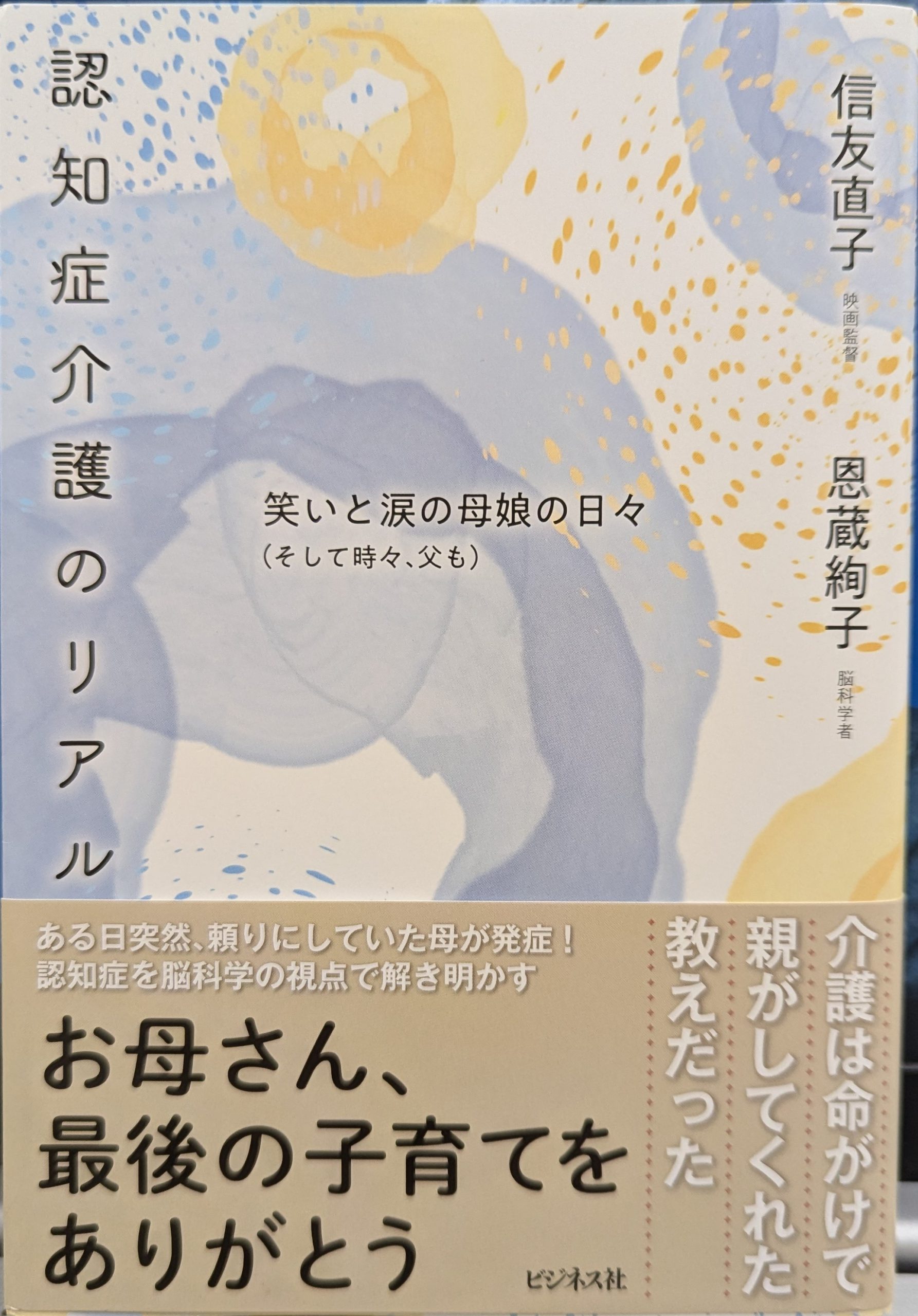
2024.08.16
ほんわか写真館
2024.08.01
ほんわか写真館
2024.07.01
ほんわか写真館
2024.06.12
ほんわか写真館
2024.04.22
ほんわか写真館
2024.04.19
ほんわか写真館
2024.04.15
ほんわか写真館
2024.04.10
ほんわか写真館
2024.08.24
ほんわか写真館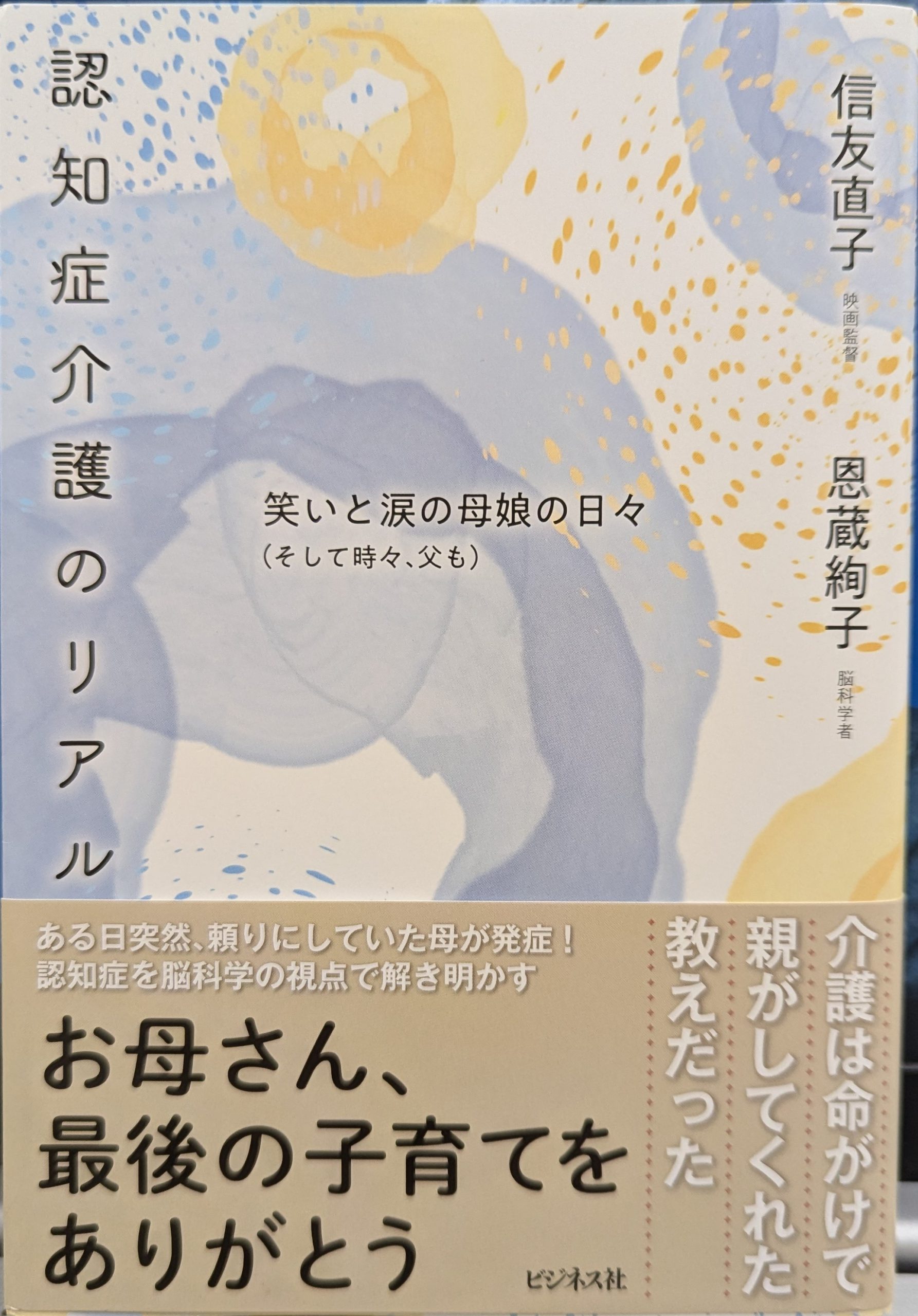
2024.08.16
ほんわか写真館 「幾星霜」とは、幾年もの星を見て、幾年もの霜を踏みしめた
苦労の日々を送って現在に至る人ともいえるでしょうか。
そんな幾星霜の輝きを持ち、
長年法人の発展のために尽力されてきた方が
引退されました。
多くの学びがあり
多くの迷惑もかけてしまいましたが、
とても偉大な存在感のある
まさしく幾星霜の輝きを放つ方です。
引退したとはいえ、人生はまだまだ続きます。
これからも、マスター(人生の師匠)として
ご指導いただきたいですね。
ひとまず、
本当にありがとうございました!
(なお写真は、事務所内撮影のため、周辺をぼかしております)
「幾星霜」とは、幾年もの星を見て、幾年もの霜を踏みしめた
苦労の日々を送って現在に至る人ともいえるでしょうか。
そんな幾星霜の輝きを持ち、
長年法人の発展のために尽力されてきた方が
引退されました。
多くの学びがあり
多くの迷惑もかけてしまいましたが、
とても偉大な存在感のある
まさしく幾星霜の輝きを放つ方です。
引退したとはいえ、人生はまだまだ続きます。
これからも、マスター(人生の師匠)として
ご指導いただきたいですね。
ひとまず、
本当にありがとうございました!
(なお写真は、事務所内撮影のため、周辺をぼかしております)

2024.08.01
ほんわか写真館
2024.07.01
ほんわか写真館
2024.06.12
ほんわか写真館
2024.04.22
ほんわか写真館
2024.04.19
ほんわか写真館 桜が咲くのが遅くなる近年の珍事?のあと、
一気に暑くなりましたね。
春のない季節になってしまったと言えるかもしれません。
体調管理が大変なのは、人間だけでなく動植物も同じかもしれません。
[caption id="attachment_5520" align="alignnone" width="1860"] 池の中も暑くて酸素不足だわ[/caption]
身体コントロールがままならぬ認知症の人の場合、
なかなか発汗できなかったり、或いは、水分が補給できず、脱水になったりと
関わる人たちのコントロールが必要になりますね。
季節の変わり目というより、急変
ついていくのが大変です。
[caption id="attachment_5519" align="alignnone" width="2048"] 暑すぎて、頭がぼーっとして、滑り落ちそうになったよ~[/caption]
昨日は認知症の人の行方不明について、NHKで特集が組まれていました。
内容はともかく、確かに社会として大きな課題となっていることは事実です。
はたして個人の行動をも見守る(監視されるともいえる)のがいいのだろうかという疑問も残ります。
AIシステムが進めば進むほど、管理、監視下に置くことは容易になるかもしれません。
しかし、認知症であっても一人の人としての自由は守らなければならないのではないだろうか。
AIシステムに頼りすぎると、個人の尊厳が侵されるのではないか。
ただ、実際行方不明になってしまったら、無事に早く見つかることが何よりです。
昔から比べると、GPSの導入も進んできています。
一次的にはやはり地域住民による見守り体制が、単に認知症の人のことだけでなく、
地域の繋がりという点では必要になるでしょう。
二次的には、GPSや発信タグなどの活用も必要かもしれません。
が、常にその方の権利が擁護されているのか、
そのようなチエック機能がなければ、管理や監視が第一の世界になってしまうかもしれません。
桜が咲くのが遅くなる近年の珍事?のあと、
一気に暑くなりましたね。
春のない季節になってしまったと言えるかもしれません。
体調管理が大変なのは、人間だけでなく動植物も同じかもしれません。
[caption id="attachment_5520" align="alignnone" width="1860"] 池の中も暑くて酸素不足だわ[/caption]
身体コントロールがままならぬ認知症の人の場合、
なかなか発汗できなかったり、或いは、水分が補給できず、脱水になったりと
関わる人たちのコントロールが必要になりますね。
季節の変わり目というより、急変
ついていくのが大変です。
[caption id="attachment_5519" align="alignnone" width="2048"] 暑すぎて、頭がぼーっとして、滑り落ちそうになったよ~[/caption]
昨日は認知症の人の行方不明について、NHKで特集が組まれていました。
内容はともかく、確かに社会として大きな課題となっていることは事実です。
はたして個人の行動をも見守る(監視されるともいえる)のがいいのだろうかという疑問も残ります。
AIシステムが進めば進むほど、管理、監視下に置くことは容易になるかもしれません。
しかし、認知症であっても一人の人としての自由は守らなければならないのではないだろうか。
AIシステムに頼りすぎると、個人の尊厳が侵されるのではないか。
ただ、実際行方不明になってしまったら、無事に早く見つかることが何よりです。
昔から比べると、GPSの導入も進んできています。
一次的にはやはり地域住民による見守り体制が、単に認知症の人のことだけでなく、
地域の繋がりという点では必要になるでしょう。
二次的には、GPSや発信タグなどの活用も必要かもしれません。
が、常にその方の権利が擁護されているのか、
そのようなチエック機能がなければ、管理や監視が第一の世界になってしまうかもしれません。

2024.04.10
ほんわか写真館