「トピックス」で記事を検索しました。

2019.09.26
トピックス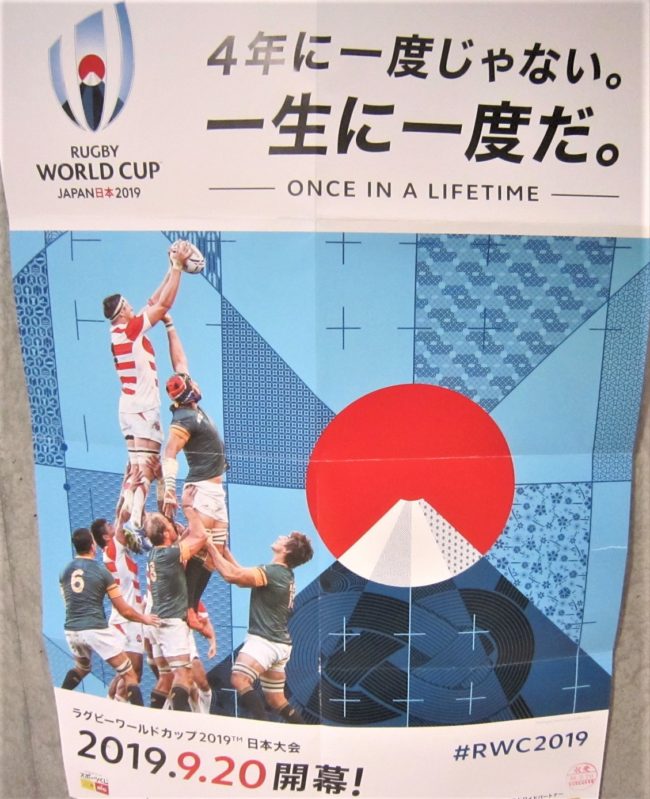
2019.09.24
トピックス
2019.09.19
トピックス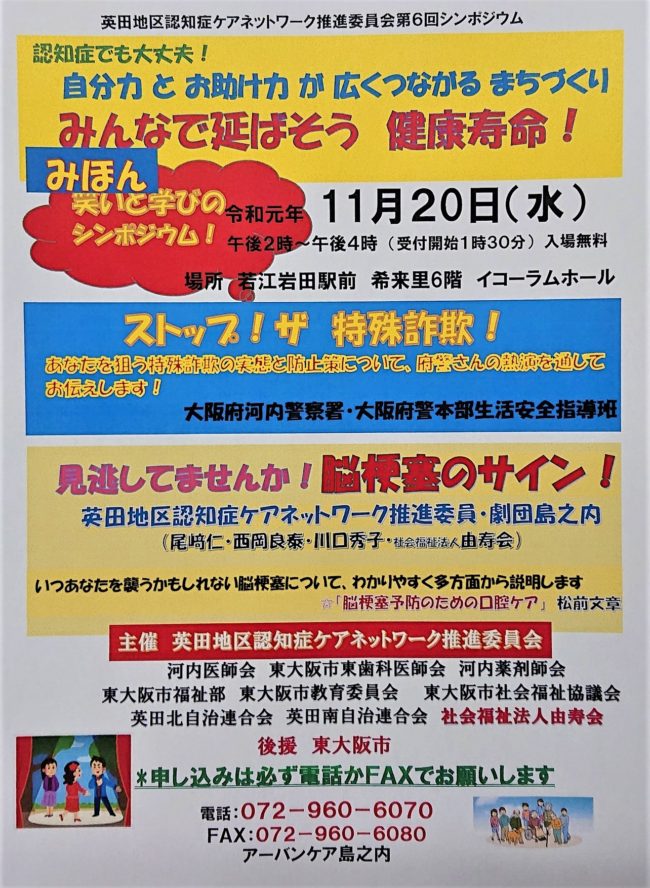
2019.09.18
トピックス
2019.09.18
トピックス
2019.09.16
トピックス
2019.10.01
トピックス
2019.09.26
トピックス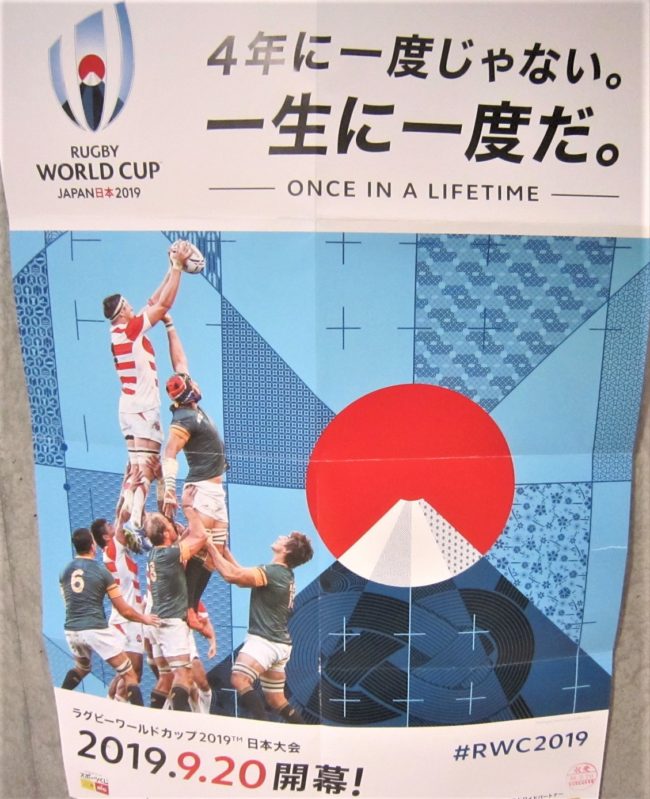
2019.09.24
トピックス
2019.09.19
トピックス
2019.09.19
トピックス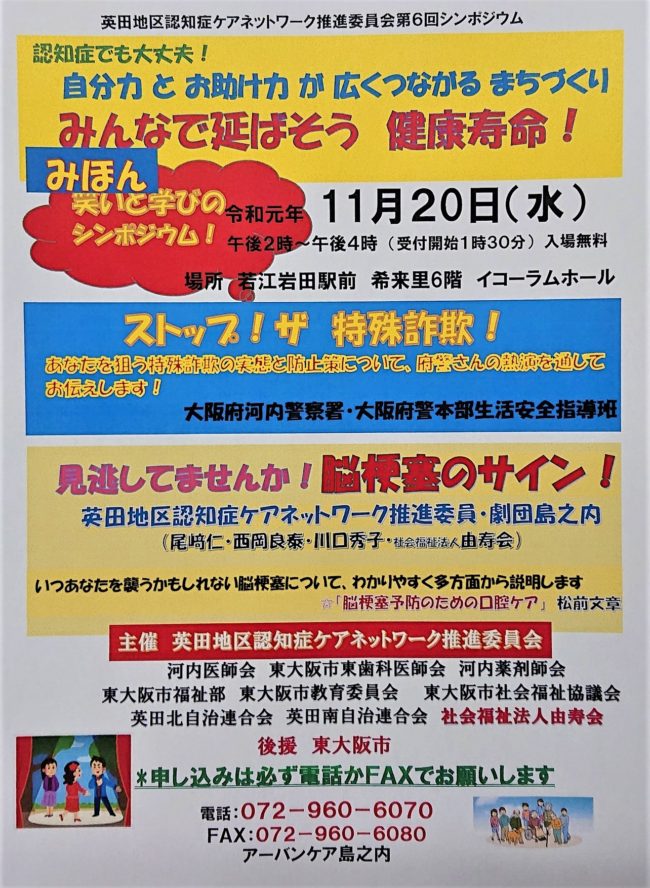
2019.09.18
トピックス
2019.09.18
トピックス
2019.09.18
トピックス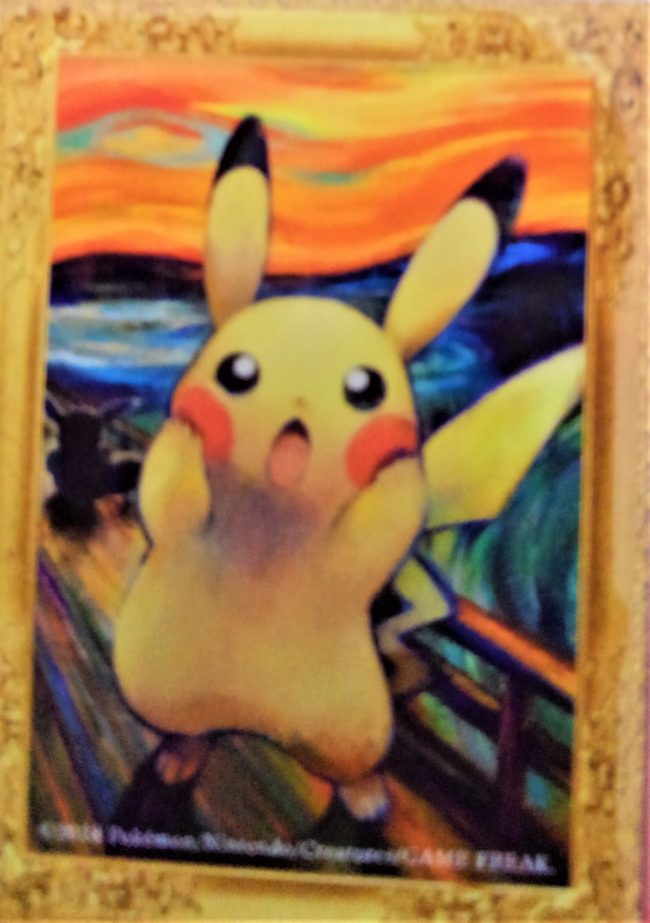 センター長の石川です。
長年親しまれてきたペッパー君が、ついに里帰りすることになりました。
とんでもなくピンボケな返事をするペッパー君でしたが、
そこがまた愛らしさを感じさせてくれましたね。
いなくなると、それはそれで寂しいものです。
ペッパー君、4年間、ありがとう!
感謝!
センター長の石川です。
長年親しまれてきたペッパー君が、ついに里帰りすることになりました。
とんでもなくピンボケな返事をするペッパー君でしたが、
そこがまた愛らしさを感じさせてくれましたね。
いなくなると、それはそれで寂しいものです。
ペッパー君、4年間、ありがとう!
感謝!

2019.09.16
トピックス