「トピックス」で記事を検索しました。

2021.05.27
トピックス
2021.05.25
トピックス
2021.05.21
トピックス
2021.05.20
トピックス
2021.05.17
トピックス
2021.05.12
トピックス
2021.05.08
トピックス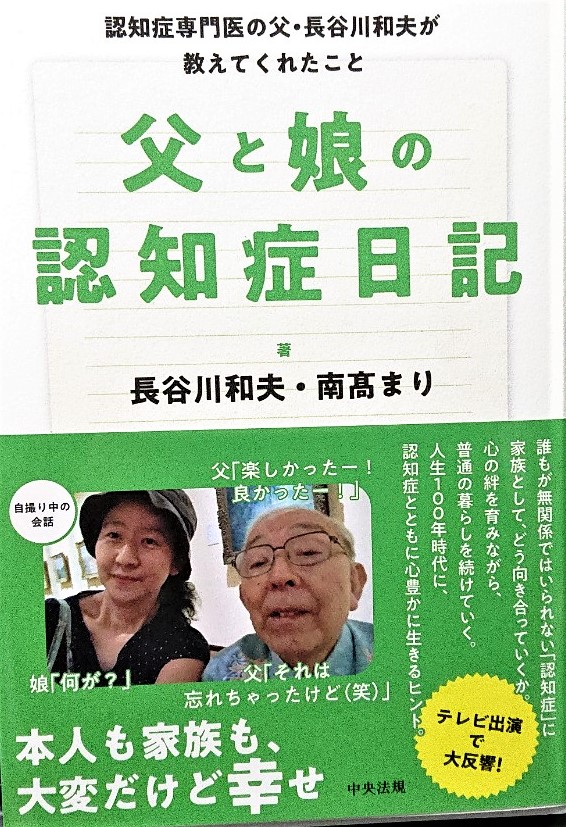
2021.05.06
トピックス
2021.05.04
トピックス
2021.05.04
トピックス
2021.05.27
トピックス
2021.05.25
トピックス
2021.05.21
トピックス
2021.05.20
トピックス
2021.05.17
トピックス
2021.05.12
トピックス
2021.05.08
トピックス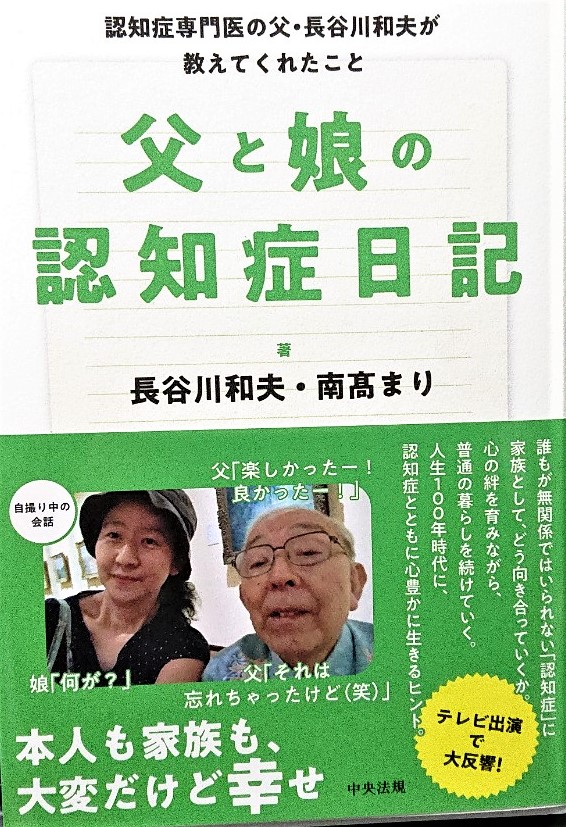
2021.05.06
トピックス
2021.05.04
トピックス
2021.05.04
トピックス