
2023.05.16
トピックス
2023.05.15
トピックス
2023.05.10
トピックス
2023.05.06
トピックス
2023.05.05
トピックス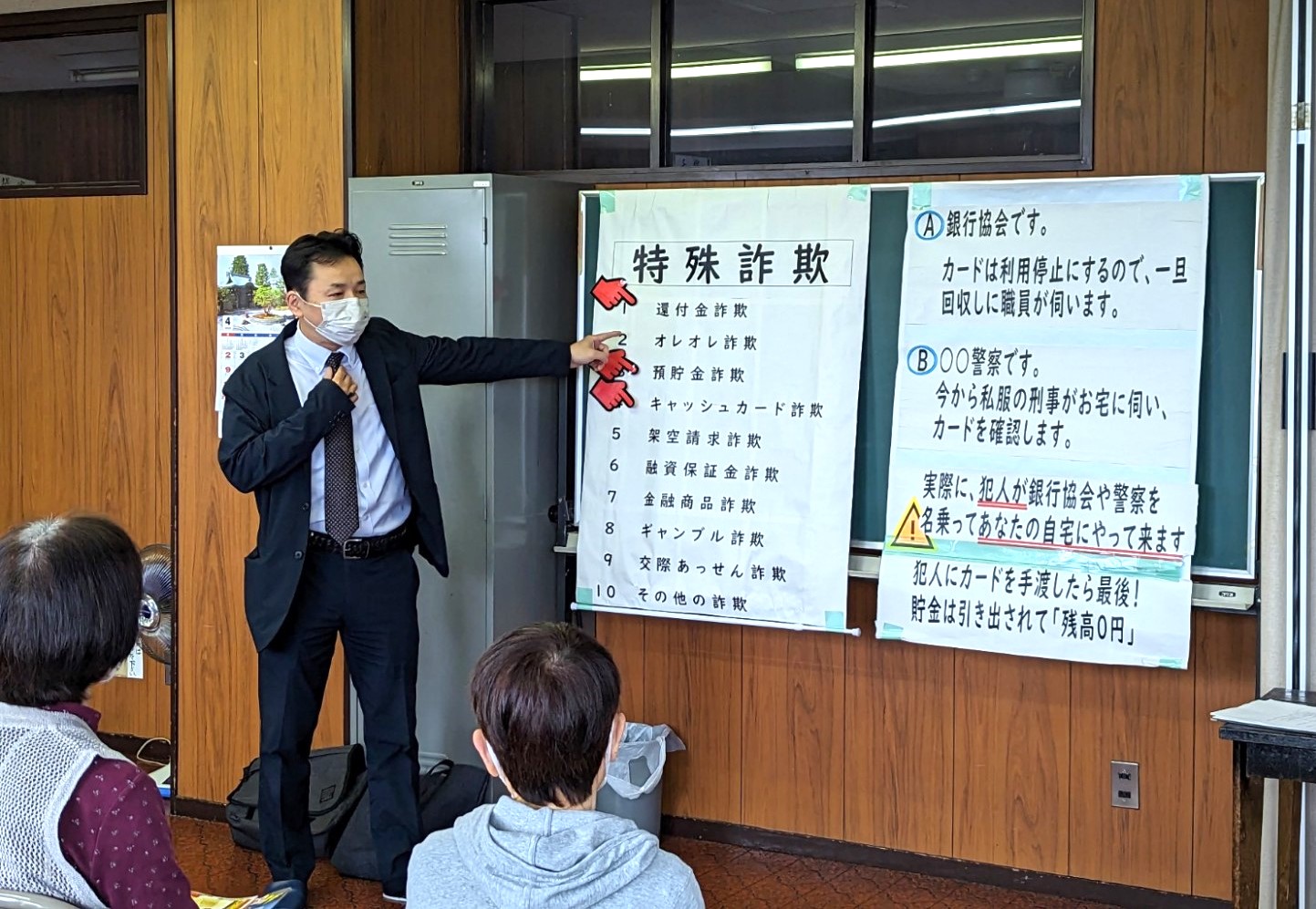
2023.05.01
トピックス
2023.04.28
トピックス
2023.04.22
トピックス
2023.04.21
トピックス
2023.04.20
トピックス
2023.05.16
トピックス
2023.05.15
トピックス
2023.05.10
トピックス
2023.05.06
トピックス
2023.05.05
トピックス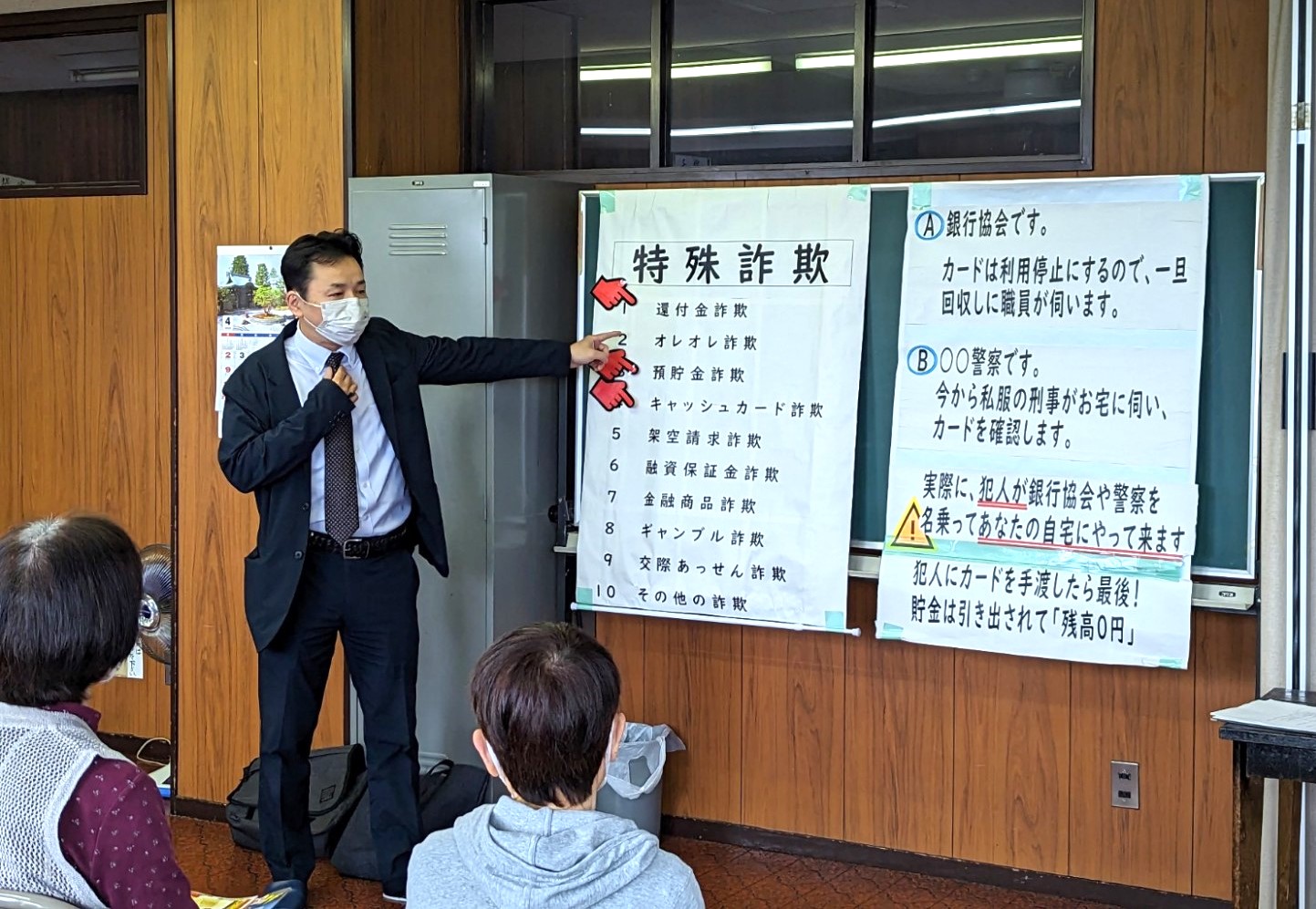
2023.05.01
トピックス
2023.04.28
トピックス
2023.04.22
トピックス
2023.04.21
トピックス
2023.04.20
トピックス