
2019.12.18
トピックス
2019.12.16
トピックス
2019.12.05
トピックス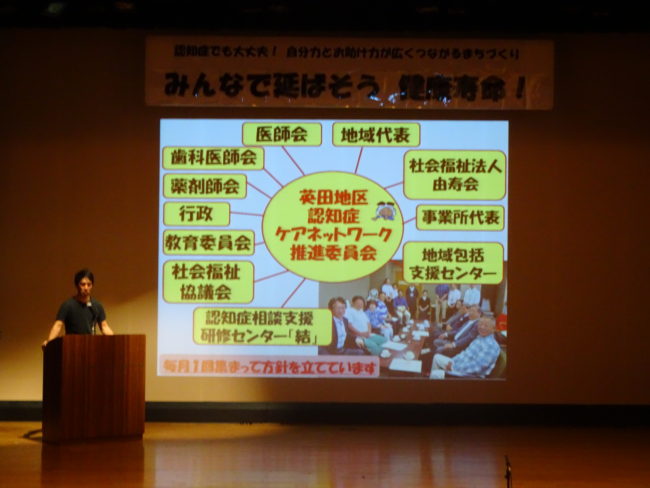
2019.11.22
トピックス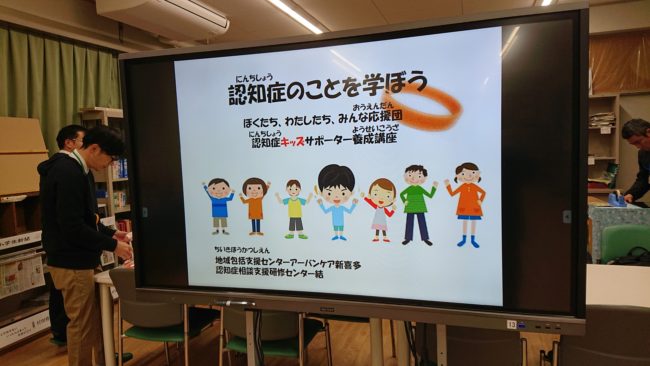
2019.11.18
トピックス
2019.11.13
トピックス
2019.12.18
トピックス センター長の石川です。
最近はブログをさぼり気味です。
実は、ネタはたくさんあるのです。
特にラグビーネタは山ほどに(笑)
もちろん認知症のお話も。
でもなかなか、たどり着けない…
そういえば、稲田の訓練の様子。稲田が載せてない!
なんてことだ!
まぁそのうちに私が撮った写真を元に載せることにします。
と言うように、時間はあっという間に過ぎていきます。
その時間、1秒1秒の積み重ね。
新しい時間はあっという間に訪れ、あっという間に過去の時間になってしまいますね。
そんな、1秒を感じるときが、
もう随分過ぎ去った時間になりますが、
令和元年11月11日11時11分11秒にありました!
[caption id="attachment_1198" align="aligncenter" width="650"] 宇宙との繋がりは、計り知れないほどの時間の積み重ねですね。(野辺山にて)[/caption]
この日、私はデイサービスの皆さんと共にカウントダウン?
いや、11分0秒から読み上げていったので、カウントアップ!?をしました。
瞬く間に12秒になってしまいましたが、
令和元年11月11日11時11分11秒の1秒を、皆さんで共有した時間でした。
さて、作為ではなく、本当に偶然だったそうですが、
阪急電車では、なんと車両番号が1111の電車がこの日の11時11分に出発したそうです。
偶然にしてはあまりにも奇跡的な偶然ですね。
[caption id="attachment_1200" align="aligncenter" width="640"] 朝日デジタルより[/caption]
阪急は10、20分などの時間に急行や特急が出発し、1分後に普通が出発するので、
11時11分発があったのですね。
それにしてもこの日のこの時間の電車の車両番号までが1111とは…
次は令和11年11月11日ですかね。
その前に、令和2年2月22日2時(或いは22時)22分22秒ですかね~
う~ん、デイサービスでのカウントダウンはできないな(苦笑)
午後2時という考えならば、出来そうですね~
センター長の石川です。
最近はブログをさぼり気味です。
実は、ネタはたくさんあるのです。
特にラグビーネタは山ほどに(笑)
もちろん認知症のお話も。
でもなかなか、たどり着けない…
そういえば、稲田の訓練の様子。稲田が載せてない!
なんてことだ!
まぁそのうちに私が撮った写真を元に載せることにします。
と言うように、時間はあっという間に過ぎていきます。
その時間、1秒1秒の積み重ね。
新しい時間はあっという間に訪れ、あっという間に過去の時間になってしまいますね。
そんな、1秒を感じるときが、
もう随分過ぎ去った時間になりますが、
令和元年11月11日11時11分11秒にありました!
[caption id="attachment_1198" align="aligncenter" width="650"] 宇宙との繋がりは、計り知れないほどの時間の積み重ねですね。(野辺山にて)[/caption]
この日、私はデイサービスの皆さんと共にカウントダウン?
いや、11分0秒から読み上げていったので、カウントアップ!?をしました。
瞬く間に12秒になってしまいましたが、
令和元年11月11日11時11分11秒の1秒を、皆さんで共有した時間でした。
さて、作為ではなく、本当に偶然だったそうですが、
阪急電車では、なんと車両番号が1111の電車がこの日の11時11分に出発したそうです。
偶然にしてはあまりにも奇跡的な偶然ですね。
[caption id="attachment_1200" align="aligncenter" width="640"] 朝日デジタルより[/caption]
阪急は10、20分などの時間に急行や特急が出発し、1分後に普通が出発するので、
11時11分発があったのですね。
それにしてもこの日のこの時間の電車の車両番号までが1111とは…
次は令和11年11月11日ですかね。
その前に、令和2年2月22日2時(或いは22時)22分22秒ですかね~
う~ん、デイサービスでのカウントダウンはできないな(苦笑)
午後2時という考えならば、出来そうですね~

2019.12.05
トピックス
2019.12.04
トピックス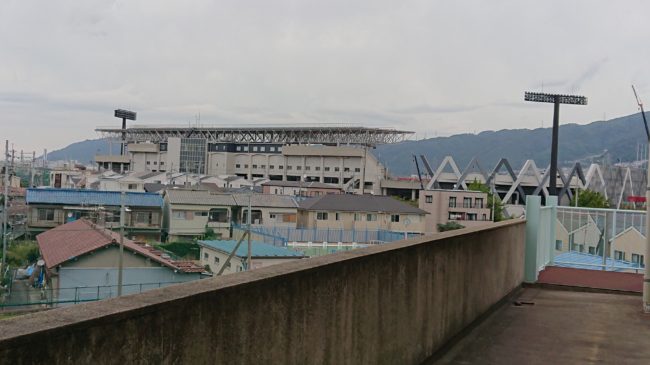
2019.12.04
トピックス センター長の石川です
相変わらず最近はブログにたどり着けないでいます。
今回は25日に行われたバスツアーから。
私は写真班でもなんでもなかったので、皆さんの写真というよりも、
最初に訪問した場所の風景写真を数枚。
バスツアー詳細については、他の方があげてもらえると思うので、そちらをご覧ください。
[caption id="attachment_1155" align="aligncenter" width="650"] ベンチと言えば、猫[/caption]
[caption id="attachment_1156" align="aligncenter" width="650"] 精密にできた猫の置物[/caption]
[caption id="attachment_1158" align="aligncenter" width="650"] これはこう使います。[/caption]
[caption id="attachment_1157" align="aligncenter" width="650"] プリンスとミシガン[/caption]
[caption id="attachment_1159" align="aligncenter" width="650"] ミシガン展望テラス[/caption]
[caption id="attachment_1160" align="aligncenter" width="650"] 雨は降らず[/caption]
[caption id="attachment_1161" align="aligncenter" width="650"] カモメのヨナサン[/caption]
[caption id="attachment_1162" align="aligncenter" width="650"] 抽選会 最大の楽しみ??[/caption]
センター長の石川です
相変わらず最近はブログにたどり着けないでいます。
今回は25日に行われたバスツアーから。
私は写真班でもなんでもなかったので、皆さんの写真というよりも、
最初に訪問した場所の風景写真を数枚。
バスツアー詳細については、他の方があげてもらえると思うので、そちらをご覧ください。
[caption id="attachment_1155" align="aligncenter" width="650"] ベンチと言えば、猫[/caption]
[caption id="attachment_1156" align="aligncenter" width="650"] 精密にできた猫の置物[/caption]
[caption id="attachment_1158" align="aligncenter" width="650"] これはこう使います。[/caption]
[caption id="attachment_1157" align="aligncenter" width="650"] プリンスとミシガン[/caption]
[caption id="attachment_1159" align="aligncenter" width="650"] ミシガン展望テラス[/caption]
[caption id="attachment_1160" align="aligncenter" width="650"] 雨は降らず[/caption]
[caption id="attachment_1161" align="aligncenter" width="650"] カモメのヨナサン[/caption]
[caption id="attachment_1162" align="aligncenter" width="650"] 抽選会 最大の楽しみ??[/caption]
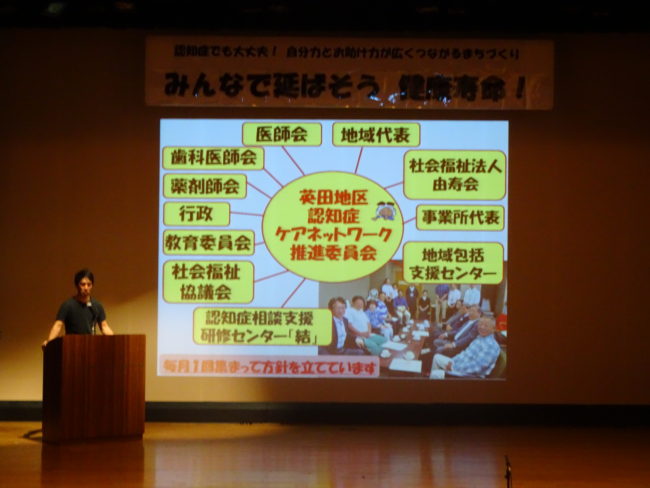
2019.11.22
トピックス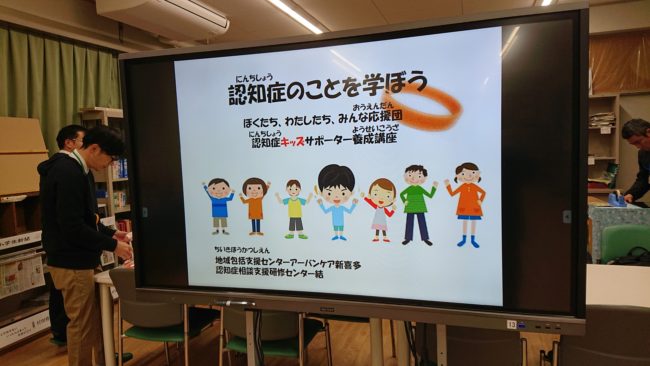
2019.11.18
トピックス
2019.11.13
トピックス
