
2020.04.24
トピックス
2020.04.23
トピックス
2020.04.21
トピックス
2020.04.20
トピックス
2020.04.16
トピックス
2020.04.15
トピックス
2020.04.24
トピックス
2020.04.23
トピックス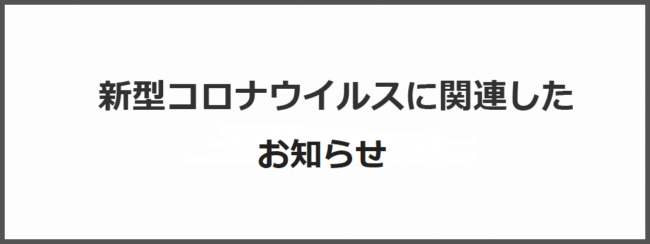 センター長の石川です
厚労省でまとめられた、事業所向けの情報です。
ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome.html
センター長の石川です
厚労省でまとめられた、事業所向けの情報です。
ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome.html
 センター長の石川です。
手前味噌になるかもしれませんが、
宮沢賢治の有名な詩、「雨ニモマケズ」を使って在宅分野で頑張るスタッフたちの
応援メッセージを作ってみました。
もちろん、入居施設で働くケア職員も同じです。
「雨ニモマケズ」
雨にも負けず
風にも負けず
雪にも夏の暑さにも負けず
新型コロナウイルスの脅威と恐怖の中でも
丈夫なからだと心をもち
決して怒らず
いつも冷静に対処し、利用者には笑っている
一日に、相談・訪問・デイ・ショート
守るべき人たちのことを
よく見聞きし分かり
そして忘れず
地域の住民や高齢者にとって
灯台のような建物から
東に病気の高齢者あれば
行って適切なマネジメントをし
西に疲れた介護者あれば
行ってそのつらさを受け止め
南に死にそうな人があれば
行って看取りを支え
北に認知症の人が不安の中にいれば
あたたかなまなざしと言葉をかけ
新型コロナウイルスの恐怖に怯えながらも
日照りの時は汗を流して自転車をこぎ
寒い冬も北風に負けずに歩き
マスコミにはその地味な努力を
褒められもせず
苦にもされず
それでもひたすら頑張っている
そういうケア職員たちを
私は
誇りに思いたい。
[caption id="attachment_1451" align="aligncenter" width="650"] コロナウイルス対策実施中![/caption]
センター長の石川です。
手前味噌になるかもしれませんが、
宮沢賢治の有名な詩、「雨ニモマケズ」を使って在宅分野で頑張るスタッフたちの
応援メッセージを作ってみました。
もちろん、入居施設で働くケア職員も同じです。
「雨ニモマケズ」
雨にも負けず
風にも負けず
雪にも夏の暑さにも負けず
新型コロナウイルスの脅威と恐怖の中でも
丈夫なからだと心をもち
決して怒らず
いつも冷静に対処し、利用者には笑っている
一日に、相談・訪問・デイ・ショート
守るべき人たちのことを
よく見聞きし分かり
そして忘れず
地域の住民や高齢者にとって
灯台のような建物から
東に病気の高齢者あれば
行って適切なマネジメントをし
西に疲れた介護者あれば
行ってそのつらさを受け止め
南に死にそうな人があれば
行って看取りを支え
北に認知症の人が不安の中にいれば
あたたかなまなざしと言葉をかけ
新型コロナウイルスの恐怖に怯えながらも
日照りの時は汗を流して自転車をこぎ
寒い冬も北風に負けずに歩き
マスコミにはその地味な努力を
褒められもせず
苦にもされず
それでもひたすら頑張っている
そういうケア職員たちを
私は
誇りに思いたい。
[caption id="attachment_1451" align="aligncenter" width="650"] コロナウイルス対策実施中![/caption]
 センター長の石川です。
私が住む地域は、山がすぐ近くにあり、散歩する人はまばらです。
もっとも、公園はかなりの人ですね。親子で溢れています。
閉じこもりでなまった体を動かすために、近くを散歩しました。
ある小さな植物園。人はほとんどいません。
あ、猫はいましたが。
そこに咲いていた花々
[caption id="attachment_1446" align="aligncenter" width="650"] はぁ~困った困った…[/caption]
う~ん、怒っているのか、悲しんでいるのか、苦しんでいるのか、睨んでいるのか、
みんなしかめっ面に見えてしまいます。
今のご時世、気持ちがそうさせるのでしょうか。
ほんとなら、「えらそうに髭なんかはやして~」とか言って笑う所なんでしょうがね~
それでも、こんなご時世でも、花は心を和ませてくれる。
しかめっ面でも、それはそれで面白いのです。
[caption id="attachment_1443" align="aligncenter" width="650"] 一つひとつ微妙に違いますよ[/caption]
それが花たる所以の存在感でしょうか。
それは変わらないと思います。
これからも、花は人間の心を和ませてくれるでしょう。
さて、散歩はくれぐれも人と人の距離を置いて行いましょう。
ジョギングの人は、走るので、その人の後方10メートルまで危険領域になります。
前の人との距離を十分に開けて走ってください。
国立スポーツ科学センタースポーツ研究部作成
センター長の石川です。
私が住む地域は、山がすぐ近くにあり、散歩する人はまばらです。
もっとも、公園はかなりの人ですね。親子で溢れています。
閉じこもりでなまった体を動かすために、近くを散歩しました。
ある小さな植物園。人はほとんどいません。
あ、猫はいましたが。
そこに咲いていた花々
[caption id="attachment_1446" align="aligncenter" width="650"] はぁ~困った困った…[/caption]
う~ん、怒っているのか、悲しんでいるのか、苦しんでいるのか、睨んでいるのか、
みんなしかめっ面に見えてしまいます。
今のご時世、気持ちがそうさせるのでしょうか。
ほんとなら、「えらそうに髭なんかはやして~」とか言って笑う所なんでしょうがね~
それでも、こんなご時世でも、花は心を和ませてくれる。
しかめっ面でも、それはそれで面白いのです。
[caption id="attachment_1443" align="aligncenter" width="650"] 一つひとつ微妙に違いますよ[/caption]
それが花たる所以の存在感でしょうか。
それは変わらないと思います。
これからも、花は人間の心を和ませてくれるでしょう。
さて、散歩はくれぐれも人と人の距離を置いて行いましょう。
ジョギングの人は、走るので、その人の後方10メートルまで危険領域になります。
前の人との距離を十分に開けて走ってください。
国立スポーツ科学センタースポーツ研究部作成

2020.04.16
トピックス
2020.04.16
トピックス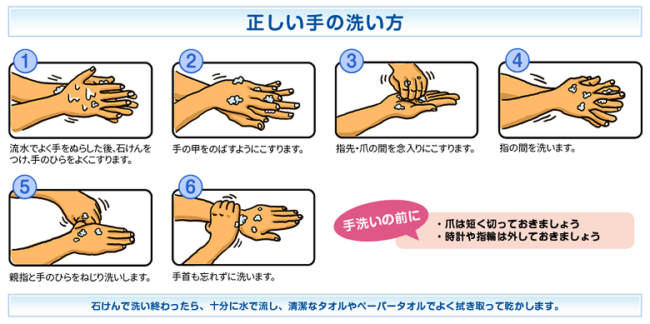 センター長の石川です
マスクの洗い方です。
参照してください。
基本一日使えば、洗ってください。
https://www.youtube.com/watch?v=AKNNZRRo74o&feature=youtu.be
センター長の石川です
マスクの洗い方です。
参照してください。
基本一日使えば、洗ってください。
https://www.youtube.com/watch?v=AKNNZRRo74o&feature=youtu.be

2020.04.15
トピックス