「2025年01月」で記事を検索しました。

2025.01.27
トピックス
2025.01.17
トピックス
2025.01.09
トピックス
2025.01.08
トピックス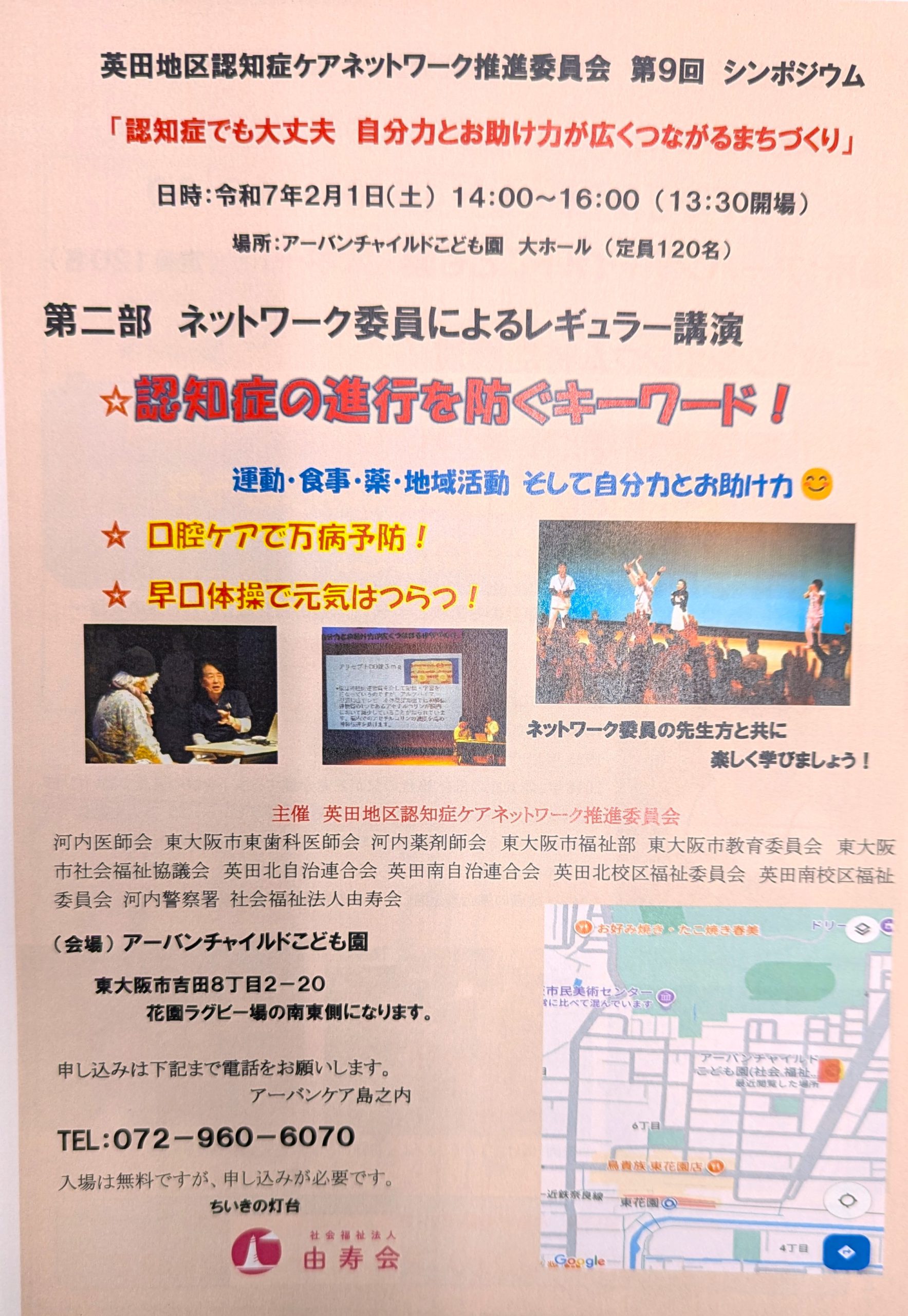
2025.01.06
トピックス 何かとあれやこれやとやっている日々を送ると
ついつい忘れがちになってしまうブログアップです。
ちょっと載せない間にも色々な出来事がありました。
それらは日々新たなる、前へ進むための一歩と言えますね。
107回目になる英田地区認知症ケアネットワーク委員会も開催されました。
2月1日のシンポジウムに向けての打ち合わせが中心となりました。
先生方も熱が入ってきましたね。
そのシンポジウムですが、凄い人数の申し込みがあり、
当初予定していた120名をはるかに超えたため、会場レイアウトを見直しました。
約190名の方が来られる予定です。
満員御礼ですね。
また、家族会も開催されました。
色々な思いを語られ、「お薬」をどう使うのか?
などと言うちょっとシビアな話もありました。
出来れば使わないことに越したことはないのですが。
また、最後には宮崎のシンガーソングライター大野勇太氏の「消えない日々」を
聴いてもらいました。
「たとえ言葉が出なくなっても、ぬくもりは感じ取れる…」
認知症の人の介護者の気持ちを唄った歌ですね。
なかなかしっとりとした唄です。
https://www.youtube.com/watch?v=pfHpNolahKI
日々新たなり
毎日様々なことが起きますが、
ネガティブに考えるのではなく、
新たな日々として、前向きに考えていきたいですね。
何かとあれやこれやとやっている日々を送ると
ついつい忘れがちになってしまうブログアップです。
ちょっと載せない間にも色々な出来事がありました。
それらは日々新たなる、前へ進むための一歩と言えますね。
107回目になる英田地区認知症ケアネットワーク委員会も開催されました。
2月1日のシンポジウムに向けての打ち合わせが中心となりました。
先生方も熱が入ってきましたね。
そのシンポジウムですが、凄い人数の申し込みがあり、
当初予定していた120名をはるかに超えたため、会場レイアウトを見直しました。
約190名の方が来られる予定です。
満員御礼ですね。
また、家族会も開催されました。
色々な思いを語られ、「お薬」をどう使うのか?
などと言うちょっとシビアな話もありました。
出来れば使わないことに越したことはないのですが。
また、最後には宮崎のシンガーソングライター大野勇太氏の「消えない日々」を
聴いてもらいました。
「たとえ言葉が出なくなっても、ぬくもりは感じ取れる…」
認知症の人の介護者の気持ちを唄った歌ですね。
なかなかしっとりとした唄です。
https://www.youtube.com/watch?v=pfHpNolahKI
日々新たなり
毎日様々なことが起きますが、
ネガティブに考えるのではなく、
新たな日々として、前向きに考えていきたいですね。

2025.01.17
トピックス
2025.01.09
トピックス
2025.01.08
トピックス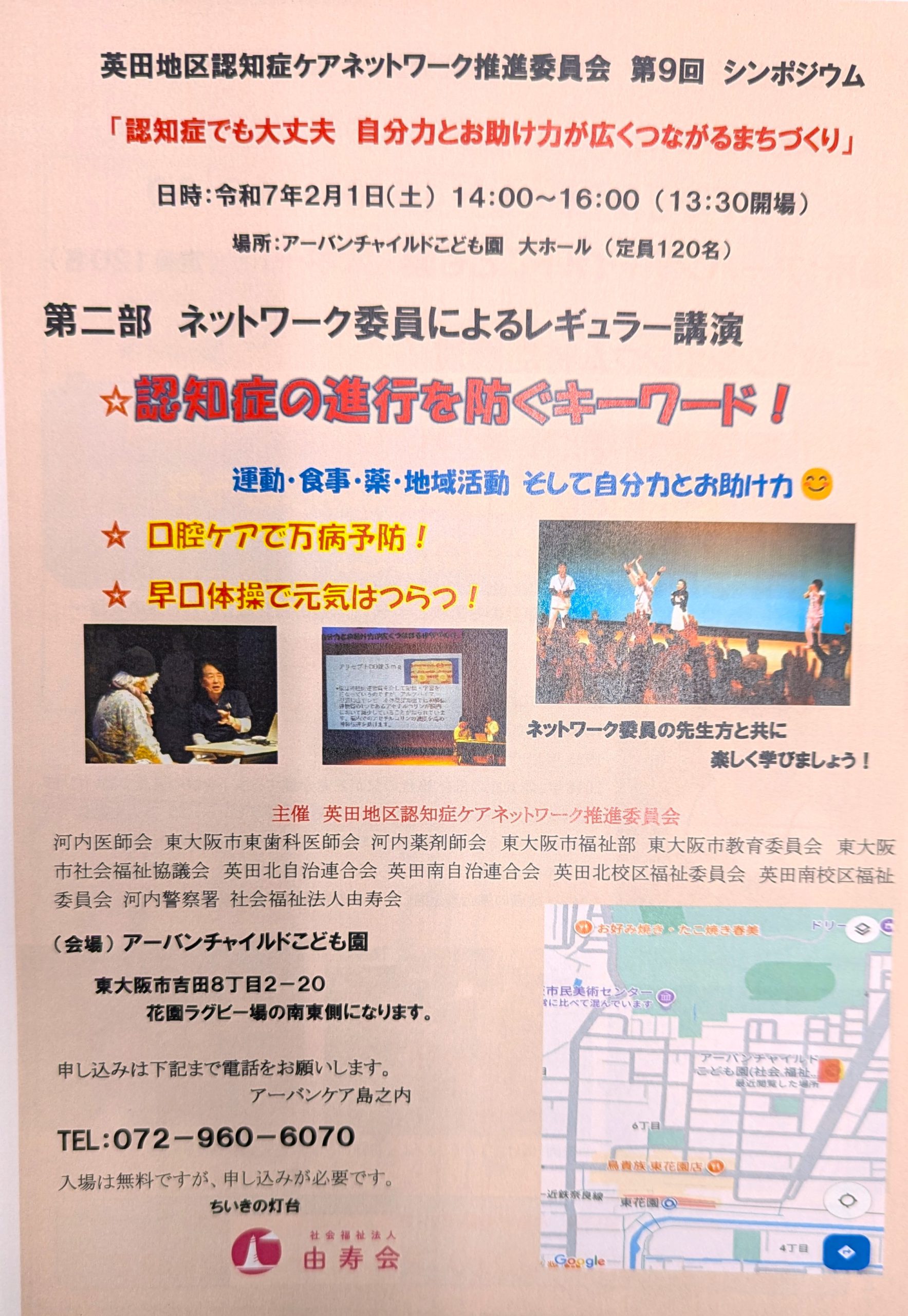
2025.01.06
トピックス